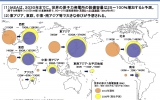福島の不安に向き合う(上)--甲状腺検査の波紋

1・地域メディエーターとしての活動
2014年8月4日に、福島県伊達市霊山町のりょうぜん里山がっこうにて、地域シンポジウムを開催したのでこの詳細を報告する。
私は地域メディエーターとして、主に福島県伊達市で2012年3月からの2年間に約200回の放射線健康講話と約100回の放射線相談窓口や家庭訪問を自治体の保健師と行ってきた。これらの活動は、市民との対話を重視し、それぞれの感情を大切にした上で地域資源や外部の支援者を活用したものであり、地域でのさまざまなな課題の解決を模索してきた。この手法の特徴を捉えるものとして、自分を「地域メディエーター」と称している。
この活動は原発事故後に私が福島県田村市で市民集会の開催などに関わったことに、さかのぼることができるもので、伊達市での活動はそれまでの経験をいかしている。伊達市の行政による個人線量計による外部被ばく実態調査、食品の放射能検査やホールボディカウンターによる内部被ばくの実態調査を市民の疑問に答える材料として活用する取り組みは、市民に受け入れられてきたと考えられる。(注1・だて市政だより 災害対策号 第70号p3)地域での放射線講話は行政の主導ではなく、地域住民の口コミにより行政側に要望が寄せられ広がった。
2・甲状腺検査を巡る県民の困惑
一方、これらの活動で課題として浮き彫りになってきたのが、福島県が行っている県民健康調査での甲状腺検査である。甲状腺超音波検査に対して、多くの保護者から不安の声が寄せられ続けている。(ふくしま国際医療科学センター、放射線医学健康管理センターによる県民健康調査、甲状腺検査の説明(リンク))
その原因の一つとして、検査を受ける側が検査の実情をよく理解していないまま検査を受け、検査結果が届いてから初めて驚くことになっていることが考えられる。つまり、検査の位置づけや検査結果が理解できないまま不安の中に陥ってしまっているのではないかと推測した。
甲状腺検査開始時の混乱は、結果通知文の不親切さによってもたらされたとされてきた。例えば、A2判定の場合には当初、『小さな結節(しこり)や嚢胞(のうほう)(液体が入っている袋のようなもの)がありますが、2次検査の必要はありません』と通知され、裏面の説明は、『「A2」は5ミリ以下のしこりか20ミリ以下の嚢胞(以下のう胞)があった場合。2次検査が必要なのは、それを超える大きさがあった場合』とだけ書かれていた。そもそも結節があったのか嚢胞があったのかも示されていなかった。結果の通知文はその後大幅に改善されたが、県民の疑念は続いていると考えられる。
一例として、第15回「県民健康調査」検討委員会(平成26年(2014年)5月19日開催)の51名のがん摘出手術者の数から、「やっぱり福島県民は被ばくしていて、放射線被ばくが原因で甲状腺がんになった」と考える方は多いことが指摘でき、先行調査は甲状腺がん罹患率のベースライン調査を目的としている県の説明が信頼されていないと言えるだろう。
ここでいう「ベースライン」とは、基礎となるデータ集めを行い、長期的に推移を見るという意味で使われている。(同センターによる説明「先行検査・本格検査の違い」)
さらに、この検討委員会では、調査の位置づけやそのものやがんと診断された方のフォローアップのあり方に関して、県側が明確にそれを示さないなど議論がかみ合わない面があり、この検討会が福島県民へ不安感を招きかねないとの意見も見受けられた。
検討委員会を受けて平成26年7月23日の福島民友新聞に甲状腺検査がもたらすかもしれない過剰診断を取り上げた記事も掲載され、甲状腺検査の難しさが改めて浮き彫りになっている。この問題はやっかいな難題である。
過剰診断を指摘する議論は、検査を受けることでの不利益にも着目するものである。しかし、原発事故に由来した放射線によりもたらされたかもしれない甲状腺がんによる不利益を最小限に抑えたいとする極めて自然な考え方からは、大切な検査の価値をおとしめるものとして強い反発を招きかねず、その主張の背景へも疑念が広がることが考えられる。
先行調査の位置づけも、それが全数調査であることからも、放射線の影響をできるだけ早く検出することを目指していると捉えるのが自然な面があるだろう。また、これまで見つかったがんはスクリーニング効果であるとの説明は県民に対して説得力を持つものとはなっていない。著者は、このような混沌の状況を懸念し、1年以上前の平成25年2月4日に「甲状腺がん検診のリスクのお知らせ」として、たむらと子どもたちの未来を考える会AFTCのHPに掲載していた。(甲状腺がん検診のリスクのお知らせ)
このような中、チェルノブイリ組織バンク所長のジェリー・トーマス氏が福島県を訪問するとの話があり、彼女が県民に貢献できる場を設定できないかとの打診があった。困難な課題である甲状腺検査の問題を真正面から捉えるシンポジウムを企画し、これに貢献していただくこととした。
3・地域シンポジウムの目的と目的達成のためのコーディネート
ⅰ)目的
福島県民の疑問に向き合い、何ができるかを意見や立場の違いを超えてみんなで考えることを目的とした。対立だけでは、社会の問題を解決するのは困難であることから福島県立医科大学や福島県保健福祉部県民健康調査課の取り組みを支援することを目指すものとした。また議論を開いたものとするために、メディアの方々にも参加を求め、彼らのさまざまな工夫によってこのシンポジウムのことを多くの人に知っていただけることも目指した。
ⅱ)開催地
シンポジウム開催地を交通の便が良い都市部では無く、あえて不便な山間部を選択した。伊達市霊山町の廃校を活用した施設であるりょうぜん里山がっこうを会場とすることで、山間部の住人のみなさんのご意見が得られることとを期待した。りょうぜん里山がっこうは、これまで保養活動など放射線対策を推進されており、意見の多様性を確保することも目指した。
それだけではなく、場所と施設の選定が個性的でかつテレビや写真の画像が背景も含めて魅力的であることから、多くのマスコミの取材を期待した。これを受けて、シンポジウム名も地域シンポジウムとした。地域の方々の手作りの歓迎セレモニーをシンポジウムの前後に開催し、シンポジウムだけではなく全体としても楽しめるイベントになるようにした。
ⅲ)パネリスト
パネリストは、以下の7名の方とした。
ジェリー・トーマス(インペリアル大学分子病理学部長・チェルノブイリ組織バンク所長)
浦島充佳(東京慈恵会医科大学分子疫学研究室・教授)
越智小枝(相馬中央病院内科診療科長)
バーバラ・ジャッジ(東京電力原子力改革監視委員会副委員長、元英国原子力公社会長)
地域住民 伊達市霊山町にお住まいのご夫婦
半谷輝己(地域メディエーター)
「県民健康調査」検討委員会の議論への貢献を踏まえて、専門家は公衆衛生を学ばれた医師とした。偶然、参加する両人ともトーマス氏が所属する英国インペリアル・カレッジにゆかりがあり、このため調整も僅かで意思疎通が実現できた。
浦島氏は、伊達市に隣接する桑折町の放射線アドバイザーを務めかつ小児科医でもあるため分かり易い説明に長けていることから甲状腺がん関係の全般の解説をお願いした。
越智氏は災害公衆衛生も学ばれていることから、地域で診療に従事されている立場としての発言をお願いした。
地域メディエーターと専門家の事前ミーティングは6時間を超えるほど密に行った。バーバラ・ジャッジ氏のオブザーバーとしての参加は、世界的に著名な方が伊達市霊山町の山間部に位置する、りょうぜん里山がっこうをご訪問していただけることを印象づけ、霊山町のみなさんから極めて好意的に受け取られ、国際色を交えた地域シンポジウムとなった。結果として、男女3名ずつのパネラーによるシンポジウムになった。
地域代表は、ご夫婦での参加を強くお願いし承諾して頂いた。事前インタビューで、甲状腺検査の受診の可否やがんの摘出手術の時期の問題では、夫婦間でも意見の相違が多く認められたので、それらの意見の違いを大切に扱いたかったからである。地域メディエーターとこのご夫婦の事前ミーティングは30分程度とし、シンポジウムはでは自由にご発言できることを約束した。
シンポジウム本番では、専門用語や福島の方言の通訳と傍聴席とパネリストを繋ぎ、赤青カードを使用し参加者の意見の多様性を確認するなどの会場の空気つくりを地域メディエーターが担った。
ⅳ)着地点
専門家からの一方通行の問題提起で終わらせない様に、重要な論点を次に繋がるように議論を進め、会場からの意見も踏まえて、課題として2つから3つの事項を提示することを目指した。
ⅴ)利益相反情報と主催団体
主催団体は地域メディエーターが所属している市民団体の家族のリスクマネジメント勉強会とした。また、利益相反情報は告知案内サイトやシンポジウムの最初にきちんと告知した。(告知サイト)
ⅵ)タイトル
地域シンポジウム(福島県伊達市霊山町から)
チェルノブイリ組織バンク所長のジェリー・トーマス先生と対話してみよう!
「甲状腺検査ってなんですか」
主催団体 家族のリスクマネジメント勉強会
とした。

半谷輝己(はんがい てるみ)BENTON SCHOOL校長、地域メディエーター。福島県双葉町生まれ、現在は田村市に在住。塾経営をしながら、2012年からは伊達市の放射能健康相談員として、市の学校を中心に180回の講話、100回を超える窓口相談(避難勧奨区域の家庭訪問)を実施。13年度より、福島県内の保育所からの求めに応じて講演を実施。日本大学生産工学部工業化学科卒、同大学院工学修士。半井紅太郎の筆名で『ベントン先生のチョコボール』(朝日新聞出版)を発表している。
以下「(下)対話深めた地域シンポ」に続く。
(2014年8月25日掲載)

関連記事
-
先日、ある学会誌に「福島の子供たちの間で、甲状腺がんが他の地域の20-50倍上がっている」という論文が受理されたようです。(注1)最近になり、この論文が今でも世間で物議をかもしているという事を聞き、とても驚きました。なぜならこの論文は、多少なりとも甲状腺やスクリーニングの知識のある研究者の間ではほとんど問題にされないものだったからです。
-
その日深夜、出力調整の試験をやるということは聞いていた。しかし現場にはいなかった。事故は午前1時36分に起こったが、私は電話の連絡を受けて、プリピャチ市の自宅から午前5時には駆けつけ、高い放射線だったが制御室で事故の対策をした。電気関係の復旧作業をした。
-
東日本大震災で発生した災害廃棄物(がれき)の広域処理が進んでいない。現在受け入れているのは東京都と山形県だけで、検討を表明した自治体は、福島第1原発事故に伴う放射性物質が一緒に持ち込まれると懸念する住民の強い反発が生じた。放射能の影響はありえないが、東日本大震災からの復興を遅らせかねない。混乱した現状を紹介する。
-
核燃料サイクル事業の運営について、政府は2月に関連法の改正案を閣議決定し国会で審議が続いている。電力システム改革による競争激化という状況の変化に対応するために、国の関与を強める方向だ。
-
福島産食品などがむやみに避けられる風評被害は、震災から4年以上たってもなお根深く残り、復興の妨げとなっている。風評被害払しょくを目指す活動は国や県だけでなく、民間でも力を入れている。消費者の安心につながる食事全体での放射線量の調査や、企業間で連携した応援活動など、着実に広がりを見せている。
-
先のブログ記事では12月8日時点の案についてコメントをしたが、それは13日の案で次のように修正されている。
-
昨年11月17日、テレビ東京の「ワールド・ビジネス・サテライト」がこれまでテレビでは取り上げられることのなかった切り口で、再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度を取り上げた。同局のホームページには当日放送された内容が動画で掲載されている。
-
マイクロソフト社の会長であるビル・ゲイツ氏は「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」を運営し、教育や医療の改善、食料生産の拡大、持続性のある経済成長、貧困問題の対応など、地球規模の社会問題の解決のための活動をしている。その中で、安く大量に提供されるエネルギーを提供する方法を探す中で、原子力に関心を向けた。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間