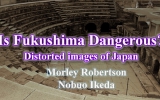河野太郎氏が核燃料サイクルを止めれば原子力はよみがえる
河野太郎氏の出馬会見はまるで中身がなかったが、きょうのテレビ番組で彼は「巨額の費用がかかる核燃料サイクル政策はきちんと止めるべきだ」と指摘し、「そろそろ核のゴミをどうするか、テーブルに載せて議論しなければいけない」と強調した。
青森県六ヶ所村の再処理工場は来年稼働することになっているが、河野首相になるとプラントそのものを解体することになるかもしれない。これは日本のエネルギー政策を根底からくつがえす大転換である。
「使用ずみ核燃料」が「核のゴミ」になる
日本は46トンのプルトニウムを保有しているが、それを増殖して無限のエネルギーを実現するはずだった高速増殖炉(FBR)もんじゅは挫折し、プルトニウムを消費する高速炉ASTRIDも開発をやめた。
1970年代に日本で核燃料サイクルが始まったころは、FBRは資源のない日本でエネルギーを無限に増殖する「夢の原子炉」とされたが、今では非在来型ウランは300年~700年、海水ウランはほぼ無尽蔵にあるので、経済的には無意味である。
FBRがなくなると、プルトニウムを消費するのはプルサーマルしかない。これはウランを再処理して、わざわざ9倍のコストのMOX燃料にして燃やす非生産的な原子炉である。
何のためにそんなことをするのか。日米原子力協定で使用目的のないプルトニウムはもたないと決めているので、余剰プルトニウムはゼロにしないといけないからだ。核拡散防止条約(NPT)締結国の中で、核兵器をもたないのにプルトニウムを生産しているのは日本だけで、これは日米原子力協定で認められている。
だから原子力協定を守るために膨大なコストをかけて再処理を進めているのだが、これは本末転倒である。使用ずみ核燃料を直接処分で埋めればいいのだ。保有プルトニウムのうち英仏で処理したまま保管されている37トンは買い取ってもらい、残りは国内のプルサーマルで時間をかけて消費すればいい。
再処理の表向きの理由は使用ずみ核燃料の体積を小さくすることだが、燃料棒のままでも核のゴミを乾式処理で置くスペースは、発電所の敷地内に十分ある。六ヶ所村には300年分以上の核廃棄物を置くことができ、再処理工場の中でも数十年間は保管できる。
核燃料サイクル廃止をめぐる3つの問題
問題はそういう技術的な制約ではなく、「六ヶ所村はゴミ捨て場ではなく工場だ」ということで使用ずみ核燃料を受け入れた地元との約束だ。民主党政権が「原発ゼロ」を閣議決定できなかったのもこれが原因だが、法律で決まっているわけではないので、河野首相が青森県知事を説得すれば、事態は動くかも知れない。
もう一つの問題は、全量再処理をやめると核燃料がゴミになることだ。いま日本にある使用ずみ核燃料1万7000トンの資産価値は約15兆円(2012年原油換算)だが、これがすべてゴミになると(使用ずみ核燃料を保有する)電力会社は大幅な減損処理が必要になり、弱小の会社は債務超過に陥る。
これは会計処理を変えれば解決できる。使用ずみ核燃料を引き続き資産として計上し、毎年少しずつ分割償却する制度を導入すればいいのだ。これは廃炉の処理で導入されたのと同じで、固定資産税は軽減され、法人税の支払いも減る。これによって電力会社の(将来にわたる)税負担は数兆円単位で軽減される。
最大の問題は、1970年代から続けてきた核燃料サイクルを中心にした原子力開発が、根底から変わることだろう。次世代炉とはプルトニウムを増殖する高速炉であり、軽水炉はそれまでのつなぎという位置づけだったが、サイクルで回るはずの核エネルギーが袋小路に入ってしまった。
余剰プルが減らせないと日米原子力協定が破棄され、日本はNPT違反になり、日米同盟にも深刻な影響をもたらす。だから「再処理工場で余剰プルを減らす努力をしている」と言い訳することが、今ではほとんど唯一の核燃料サイクルの目的である。
再処理は地域独占と一体だった
なぜこんなことになったのか。その背景には、電力自由化をめぐる闘いがあった。2003年に核燃料サイクルを見直したとき、電力会社は再処理コストを電気料金に転嫁しようとした。経産省はこれに反対し、「19兆円の請求書」をマスコミに配布して核燃料サイクルをつぶそうとした。
村田事務次官は発送電分離して、電力業界を通信業界のように支配しようとしたが、電力業界は地域独占が失われることを恐れた。そのために彼らが「人質」にしたのが核燃料サイクルだった。再処理にかかる膨大なコストは総括原価方式でないと負担できないので、再処理と地域独占は一体だからだ。電力会社は族議員を使ってサイクルを守って発送電分離を阻止し、闘いは経産省の敗北に終わった。
しかし3・11のあと、経産省は火事場泥棒的に自由化を決め、原発を止めたまま発送電分離した。その結果、原発のキャッシュフローは大幅な赤字になり、核燃料サイクルは宙に浮いてしまった。
このまま再処理工場が稼働すると、今後20年で19兆円から50兆円のキャッシュフローが浪費され、最終的には国民負担になる。しかしサイクルをなくすと電力会社の垂直統合モデルは消滅し、工場や核燃料を清算したコストを誰が負担するかが大きな問題となろう。
原子力産業の国有化
河野氏もこのリスクは理解しているようにみえる。原発の再稼動を認めたのは一歩前進だが、それでは2050年カーボンニュートラルどころか、2030年46%削減も不可能だ。原発のリプレースは避けられないが、日本では原子力は民間企業でリスクの負いきれない事業になった。
そこで日本原子力発電を受け皿会社にして、BWR(沸騰水型原子炉)の東電・中部電力・東北電力・北陸電力・北海道電力の原子力部門を原子力公社に統合し、核燃料サイクルを含めて国有化する構想が経産省で検討されているという。
国有化には巨額の国費が必要になるが、原子力損害賠償・廃炉等支援機構にはすでに国が出資し、交付国債という形で東電に約8兆円の融資が行われている。廃炉・賠償・除染にかかる21.5兆円を東電が今後40年かけてすべて負担する、という政府の計画を信じる人はいない。最終的には、数兆円規模の国費投入が行われるだろう。
つまりこれは国の原子力救済を間接的にやるか直接的にやるかだけの違いである。その最初のステップとして、東電を破綻処理して存続会社と清算会社に分離し、後者に原子力部門を含める経営再編も専門家が提案している。資金は建設国債で調達することもできるし、炭素税を当てることもできる。
このような「外科手術」は、あまりにもドラスティックなので先送りされてきたが、政府が原子力を救済することは脱炭素化を進める上でも重要だ。再エネだけでカーボンニュートラルが不可能なことは明らかである。プルトニウムをゼロにすると核武装のオプションを失うが、日本が核武装するにはNPTを脱退し、日米同盟を破棄する必要があるので、現実的なオプションとはいえない。
今の「生かさず殺さず」の状態では、原子力産業に未来はない。技術者の士気は下がり、若い人材は集まらない。再処理や高速炉に投入されてきた人的・物的資源を、政府が次世代原子炉(SMRなど)に再配分し、世界でもトップレベルの原子力技術を残すべきだ。
損失を清算して経営が再建されれば、かつて国有化された長信銀のようにふたたび民営化することも可能だ。国有化は激しい反発をまねくので、普通の首相にはできないが、河野首相が政治決断するなら反対派も納得するだろう。

関連記事
-
昨年11月の原子力規制委員会(規制委)の「勧告」を受けて、文部科学省の「『もんじゅ』の在り方に関する検討会(有馬検討会)」をはじめとして、様々な議論がかわされている。東電福島原子力事故を経験した我が国で、将来のエネルギー供給とその中で「もんじゅ」をいかに位置付けるか、冷静、かつ、現実的視点に立って、考察することが肝要である。
-
東日本大震災から2年。犠牲者の方の冥福を祈り、福島第一原発事故の被害者の皆さまに心からのお見舞いを申し上げます。
-
今週、ドイツ最大の週刊紙であるDie Zeit(以下、ツァイトとする。発行部数は100万部をはるかに超える)はBjorn Stevens(以下、スティーブンス)へのインタビューを掲載した。ツァイトは、高学歴の読者を抱えて
-
今回も嘆かわしい報道をいくつか取り上げる。 いずれも、筆者から見ると、科学・技術の基本法則を無視した「おとぎ話」としか受け取れない。 1. 排ガスは資源 CO2から化学原料を直接合成、実証めざす 排ガスは資源 CO2か
-
14年10 月28日公開。モーリー・ロバートソン(作家、DJ)、池田信夫(アゴラ研究所所長)。福島の現状について、海外でどのように受け止められているかをまとめた。(大半が英語)
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
「原子力文明」を考えてみたい筆者は原子力の安全と利用に長期に携わってきた一工学者である。福島原発事故を受けて、そのダメージを克服することの難しさを痛感しながら、我が国に原子力を定着させる条件について模索し続けている。
-
10月22日、第6次エネルギー基本計画が7月に提示された原案がほぼそのままの形で閣議決定された。菅前政権において小泉進次郎前環境大臣、河野太郎前行革大臣の強い介入を受けて策定されたエネルギー基本計画案がそのまま閣議決定さ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間