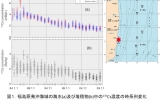今週のアップデート - 福島にリスクはあるのか?1mSvの意味(2015年2月9日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
川合将義高エネルギー加速器研究機構名誉教授に寄稿をいただきました。川合さんら原子力研究者の有志は、福島原発事故から、福島に入って知識を提供しています。1mSvの意味についての資料の紹介です。
元日本原電勤務で、福島原発事故では被災者になった北村俊郎さんの寄稿です。福島の状況で。帰還が遅れ、復興が進みません。それを住民目線で紹介しています。
今週のリンク
ITメディア2月3日記事。総合資源エネルギー調査会で2030年の最適な電源構成(エネルギーミックス)を決める有識者会合が30日に始まりました。(経産省は2月8日時点、議事録公開せず)昨年決まったエネルギー基本計画、さらに温暖化をめぐる国際交渉での主張のためです。しかし、原発稼働の見通しがつかない中で意味があるか疑問です。
日本経済新聞2月8日社説。16年以上止まったもんじゅについて、もう後がないと認識すべきと、文科省、日本原子力研究開発機構に訴える社説です。
政策家の石川和男氏の1月15日付コラム。ガス改革について、小売り自由化と都市ガスの導管分離が検討されているものの、調整ができずに、自由化については結論を示しませんでした。内閣法制局との調整が行いきれなかったためです。その問題を取り上げています。
経済産業省。1月30日公開資料。ガスシステム改革のとりまとめですが、経産省が中身を詰め切れない異例の答申になりました。
5)「発送電分離」実施は20年 政府・与党が最終調整 大手電力に配慮
産経ビズ2月5日記事。大手電力会社から送配電部門を切り離す「発送電分離」の実施時期は2020年とする方向で政府・自民党は最終的な調整に入ったもよう。従来は「18~20年をめど」としていたが、最も遅い時期になります。

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
低線量の電離放射線被曝による発がんリスクについては、議論が分かれる。低線量ではデータが正確ではなく、しばしば矛盾するため、疫学的方法のみでは評価することはできない。
-
海洋放出を前面に押す小委員会報告と政府の苦悩 原発事故から9年目を迎える。廃炉事業の安全・円滑な遂行の大きな妨害要因である処理水問題の早期解決の重要性は、国際原子力機関(IAEA)の現地調査団などにより早くから指摘されて
-
福島原発事故以来、環境の汚染に関してメディアには夥しい数の情報が乱れ飛んでいる。内容と言えば、環境はとてつもなく汚されたというものから、そんなのはとるに足らぬ汚染だとするものまで多様を極め、一般の方々に取っては、どれが正しいやら混乱するばかりである。
-
国連科学委員会の中の一部局、原子放射線の影響に関する国連科学委員会は、昨年12月に報告書をまとめ、国連総会で了承された。その報告書の要約要旨を翻訳して掲載する。迂遠な表現であるが、要旨は国連の報告書間で整合性が取れていないこと、また低線量被曝についてのコンセンサスがないことを強調している。
-
3月11日の大津波により冷却機能を喪失し核燃料が一部溶解した福島第一原子力発電所事故は、格納容器の外部での水素爆発により、主として放射性の気体を放出し、福島県と近隣を汚染させた。 しかし、この核事象の災害レベルは、当初より、核反応が暴走したチェルノブイリ事故と比べて小さな規模であることが、次の三つの事実から明らかであった。 1)巨大地震S波が到達する前にP波検知で核分裂連鎖反応を全停止させていた、 2)運転員らに急性放射線障害による死亡者がいない、 3)軽水炉のため黒鉛火災による汚染拡大は無かった。チェルノブイリでは、原子炉全体が崩壊し、高熱で、周囲のコンクリ―ト、ウラン燃料、鋼鉄の融け混ざった塊となってしまった。これが原子炉の“メルトダウン”である。
-
原発事故から3年半以上がたった今、福島には現在、不思議な「定常状態」が生じています。「もう全く気にしない、っていう方と、今さら『怖い』『わからない』と言い出せない、という方に2分されている印象ですね」。福島市の除染情報プラザで住民への情報発信に尽力されるスタッフからお聞きした話です。
-
1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原子力発電所原子炉の事故は、原子力発電産業においてこれまで起きた中でもっとも深刻な事故であった。原子炉は事故により破壊され、大気中に相当量の放射性物質が放出された。事故によって数週間のうちに、30名の作業員が死亡し、100人以上が放射線傷害による被害を受けた。事故を受けて当時のソ連政府は、1986年に原子炉近辺地域に住むおよそ11万5000人を、1986年以降にはベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナの国民およそ22万人を避難させ、その後に移住させた。この事故は、人々の生活に深刻な社会的心理的混乱を与え、当該地域全体に非常に大きな経済的損失を与えた事故であった。上にあげた3カ国の広い範囲が放射性物質により汚染され、チェルノブイリから放出された放射性核種は北半球全ての国で観測された。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間