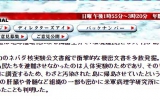福島第一原発のデブリ処理は「石棺」方式で
福島第一原発のデブリ(溶融した核燃料)について、東電は「2018年度内にも取り出せるかどうかの調査を開始する」と発表したが、デブリは格納容器の中で冷却されており、原子炉は冷温停止状態にある。放射線は依然として強いが、暴走する危険はなく、今はほぼ安定した状態である。これを取り出す作業は、強い放射線を浴びて危険だ。
そもそもデブリを取り出す必要はない。チェルノブイリ原発と同じように「石棺」方式で密閉すればいいのだ。チェルノブイリの新しい石棺は写真のような高さ約100mのアーチ型のシェルターで、少なくとも100年間は放射性物質を封じ込められるという。コストは21億5000万ユーロ(約2800億円)で、8兆円かかる福島の「廃炉」とは桁違いだ。

チェルノブイリ原発の石棺(WSJより)
福島でも、同じようなドームで密閉することは、技術的には容易だ。しばらくは冷却が必要で、放射線のモニタリングも続けなければならないが、デブリを取り出すよりはるかに安全で、コストも1兆円以内ですむだろう。問題はデブリの冷却水を湾内に排出できないことだ。その原因は冷却水の中のトリチウムが完全に除去できないためだが、そのレベルは自然界と変わらず、健康に影響はない。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構も、2016年の「戦略プラン」で石棺に言及した。このときは地元も了解していたが、マスコミが騒ぎ始め、福島県の内堀知事が経済産業省に抗議した。支援機構の山名理事長は「引き続きデブリの取り出しをめざす」と釈明し、その後は石棺はタブーになってしまった。
知事の抗議は、政治的スタンドプレーである。デブリを取り出しても、福島第一原発のまわりに住民は住めない。このままでは、東電は事故被災者の賠償と除染に加え、今後は30年にわたって毎年3000億円の積み立てが必要になる。
この問題について、関係者の誰に聞いても取り出すのは無理だというが、今は努力するしかないという。「あらゆる手を尽くしたができなかった」といわないと、地元が納得しないからだ。これはトリチウム水も同じで、タンクが一杯になって「これ以上は無理だ」といわないと流せない。
そういう日本的な問題解決のために事故から7年以上も問題を放置し、これからさらに何兆円もかけるコストは、結局は電力利用者と納税者の負担になる。これは形式的には東電の経営判断だが、国が決めないとできない。石棺という言葉に抵抗があるなら、「ドーム」といってもよい。経済産業省が決めないと、東電は動けない。

関連記事
-
朝日新聞7月10日記事。鹿児島県知事に、元テレビ朝日記者の三反園訓氏が当選。三反園氏は、川内原発の稼働に懐疑的な立場で、再検査を訴えた。今後の動向が注目される。
-
これが日本の産業界における気候リーダーたちのご認識です。 太陽光、屋根上に拡大余地…温室ガス削減加速へ、企業グループからの提言 245社が参加する企業グループ、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)は7月、GH
-
去る6月23日に筆者は、IPCC(国連気候変動政府間パネル)の議長ホーセン・リー博士を招いて経団連会館で開催された、日本エネルギー経済研究所主催の国際シンポジウムに、産業界からのコメンテーターとして登壇させていただいた。
-
北極の氷がなくなって寂しそうなシロクマ君のこの写真、ご覧になったことがあると思います。 でもこの写真、なんとフェイクなのです! しかも、ネイチャーと並ぶ有名科学雑誌サイエンスに載ったものです! 2010年のことでした。
-
テレビ朝日が8月6日に「ビキニ事件63年目の真実~フクシマの未来予想図~」という番組を放送すると予告している。そのキャプションでは、こう書いている。 ネバダ核実験公文書館で衝撃的な機密文書を多数発掘。ロンゲラップ島民たち
-
少し前の話になりますが、2016年12月20日に経済産業省に設置されていた「東京電力改革・1F問題委員会」において、「東京電力改革提言」なる報告書がまとめられました。この提言では福島における原発事故の対策費用の全体像が初
-
(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か②) 送電線を増強すれば再生可能エネルギーを拡大できるのか 「同時同量」という言葉は一般にも定着していると思うが、これはコンマ何秒から年単位までのあらゆる時間軸で発電量と需
-
いつか来た道 自民党総裁選も中盤を過ぎた。しかしなかなか盛り上がらない。 5人の候補者が口を揃えて〝解党的出直し〟といっているが、その訴えが全く響いてこない。訴求力ゼロ。 理由は明確だ。そもそもこの〝解党的〟という言葉だ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間