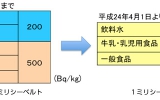トランプ政権と米国の温暖化政策の行方
いよいよ、米国でトランプ政権が誕生する。本稿がアップされる頃には、トランプ次期大統領が就任演説を終えているはずだ。オバマケア、貿易、移民、ロシア等、彼に関する記事が出ない日はないほどだ。トランプ大統領の下で大きな変更が予想される施策分野の一つはエネルギー・温暖化対策だ。これについては、大統領選直後にGPERに論考を出したところである。
トランプ氏は、過去、ツイッター等で「気候変動問題は中国が米国の競争力をそぐためにつくりあげたでっち上げ(hoax)だ」と公言してきた。大統領選当選後、環境保護庁(EPA)の移行チームヘッドに気候変動懐疑派のマイロン・エーベル氏が任命されたこともあり、当選直後、トランプ政権が温暖化対策について後ろ向きな対応をとるとの観測が支配的であった。
ところが、11月末にトランプ氏がニューヨークタイムズのインタビューを受けた際、パリ協定からの離脱については「オープンマインドで検討している」、気候変動についても「何らかの関係はあると思う。問題は(温暖化対策で)企業にどれだけコストがかかるかだ」等、選挙期間中に比べれば「穏当な」受け答えをした。また12月初めには「不都合な真実」で知られるアル・ゴア副大統領がトランプタワーを訪問し、トランプ氏及び長女のイヴァンカ氏と気候変動問題について意見交換を行ったとの報道が流れた。このため、環境関係者の間では、「トランプ政権は選挙中の過激な発言とは裏腹に、温暖化対策についてもそれなりに取り組むのではないか」との期待感が高まった。
しかし、12月に入り、トランプ氏が主要閣僚人事を発表し始めると、こうした環境派の期待感は空しいものに終わりそうだ。例えば環境保護庁長官に指名されたのはスコット・プルイット・オクラホマ州司法長官である。発電部門での低炭素化を目的にオバマ大統領が導入したクリーン・パワー・プランに対しては、28の州から訴訟が提起されているが、プルイット氏は「地球温暖化の程度と人間活動との関連性についての科学的コンセンサスはない」と広言し、オクラホマ州による訴訟を取り仕切った人物である。またエネルギー長官に指名されたリック・ペリー前テキサス州知事は、「気候変動は人間がもたらしたものであるが故に、温暖化防止のために米国経済を傷つけても良いという議論に自分は与しない。そのために気候懐疑派と呼ばれることを恐れない」と発言しており、これまた温暖化アジェンダには冷淡であると考えられる。皮肉なことにトランプ氏が指名した主要閣僚の中で最も「グリーン」に見えるのは、国務長官に指名されたレックス・ティラーソン・エクソン・モービルCEOである。欧州系の石油・ガス企業のシェルやBPに比して、米系のエクソン・モービルやシェブロンは環境関係者の間では評判が芳しくない。エクソン・モービルは1990年代にかけて温暖化を否定する論陣を張ったロビー団体GCC(Global Climate Coalition)の創設メンバーであった。しかし2006年にCEOに就任したレックス・ティラーソン氏の下で軌道修正が図られ、最近ではエクソン・モービルは温暖化問題の重要性を認識し、パリ協定も支持する旨の声明を出している。このため、「化石燃料企業のヘッドとはいえ、温暖化問題の所在そのものを疑問視するプルイット氏やペリー氏よりは余程まし」というわけである。
確かにティラーソン氏が国務長官に就任することで、米国がパリ協定はおろか、その親条約である気候変動枠組み条約からも離脱するという可能性が低下したとの見方もできるかもしれない。そもそも気候変動枠組条約はブッシュ(シニア)政権の時代に批准されたものである。ブッシュ(ジュニア)政権は京都議定書からは離脱したが、温暖化問題そのものは否定せず、気候変動枠組条約にも留まり続けた。
しかし、米国の国内対策を主導するのは国務省ではなく、エネルギー省であり、環境保護庁である。両省のトップの顔ぶれを見る限り、クリーン・パワー・プランを含め、オバマ大統領が導入した国内対策の見直し・撤回が進むことは不可避と思われる。環境関係者の間では、カリフォルニア州をはじめ、温暖化防止に熱心な州政府への期待感が強い。確かにトランプ政権の下でクリーン・パワー・プランが形骸化、無力化したとしても、州政府が発電部門の排出削減に取り組むことを排除することはできない。しかし発電部門が米国の全排出量に占めるシェアも3分の1以下であり、温暖化に前向きなカリフォルニア州、ニューヨーク州の排出量は全米の10%未満に過ぎない(エネルギー多消費産業が立地していないのだから当然であろう)。州レベルの対策は重要であるとしても、連邦政府が後ろ向きになった場合のインパクトを中立化することは難しいということだ。
トランプ政権の下で温暖化対策がどの程度影響を受けるのかは、閣僚の議会承認プロセス、今後、発表される予算案などを見れば、更に明らかになってこよう。世界の温暖化に向けた取り組みにも影響を与えるだけに、当面、目が離せない。

関連記事
-
昨年7月に5回にわたって「欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感」を投稿したが、その後半年の間に色々な動きがあった。これから数回にわたって「続・欧州のエネルギー環境政策を巡る風景感」を綴ってみたい。
-
世耕経産相は「EV(電気自動車)の潮流は拡大してきているが、いきなりEVにいけるわけでもない」と述べ、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池車(FCV)などいろいろな次世代自動車がある中で「戦略的によく考えて中長期
-
パリ気候協定への2035年の数値目標の提出期限は2月10日だったのだが、ほとんどの国が間に合っていない。期限に間に合った先進国は、米国、スイス、英国、ニュージーランドの4か国だけ。ただしこの米国は、バイデン政権が約束した
-
東京都に引き続いて川崎市も太陽光パネルの住宅への設置義務条例を審議している。まもなく3月17日に与野党の賛成多数で可決される見込みだ。 だが太陽光パネルには問題が山積していることはすでにこの連載で述べてきた。 そして自身
-
関西電力は、6月21日に「関西電力管外の大口のお客さまを対象としたネガワット取引について」というプレスリリースを行った。詳細は、関西電力のホームページで、プレスリリースそのものを読んでいただきたいが、その主旨は、関西電力が、5月28日に発表していた、関西電力管内での「ネガワットプラン」と称する「ネガワット取引」と同様の取引を関西電力管外の60Hz(ヘルツ)地域の一部である、中部電力、北陸電力、中国電力の管内にまで拡大するということである。
-
今回も、いくつか気になった番組・報道についてコメントしたい。 NHK BS世界のドキュメンタリー「デイ・ゼロ 地球から水がなくなる日」という番組を見た。前半の内容は良かった。米国・ブラジルなど水資源に変化が現れている世界
-
台湾が5月15日から日本からの食品輸入規制を強化した。これに対して日本政府が抗議を申し入れた。しかし、今回の日本は、対応を間違えている。台湾に抗議することでなく、国内の食品基準を見直し、食品への信頼感を取り戻す事である。そのことで、国内の風評被害も減ることと思う。
-
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 最近流れたニュース「MITが核融合発電所に必要となる「超伝導電磁石の磁場強度」で世界記録を更新したと報告」を読んで、核融合の実現が近いと思った方も多いかと思うが、どっこい、そん
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間