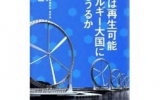COP30と「COP限界論」:理想と現実のはざまで

Heiness/iStock
アマゾンから世界へ
2025年11月、COP30がブラジル北部アマゾンの都市ベレンで開催される。パリ協定採択から10周年という節目に、開催国ブラジルは「気候正義」や「持続可能な開発」を前面に掲げ、世界に新しい方向性を示そうとしている。
アマゾンという象徴的な場所から発信することで、森林保護や先住民の権利も含めた包括的な視点を訴える構えだ。ブラジルは「アマゾンの声を世界に届ける」と強調し、途上国の存在感を高める意図もにじませている。
しかし、これまでのCOPの経緯を振り返れば、理想的な目標と現実的な行動の間には大きな乖離が存在してきた。果たして今回は「転換点」となり得るのか、それともまたもや「お茶を濁す」だけで終わるのか、注目が集まっている。
理想と現実のギャップ
COP28で実施された「グローバル・ストックテイク(GST)」は、各国の気候行動を初めて総括したものだった。その結果は厳しく、「現在の取り組みでは1.5℃目標に全く届かない」という現実を突きつけた。UNEPの報告では、各国の公約通りでも気温上昇は2.5〜2.9℃、政策が不十分なら3℃を超える可能性すらあるとされている。
とはいえ、COP28では、「再エネ容量3倍」「エネルギー効率2倍」といった数値目標や、「化石燃料からの転換」という文言が盛り込まれるという前向きな合意もあった。しかしこれは「約束」にすぎず、各国が次期削減目標(NDC)にどこまで反映させるかが問われる。COP30はその真価が試される場となる。
南北問題の核心
資金と責任をめぐる南北の対立は、COPの場で常に表面化してきた。先進国は歴史的に大量の排出を行ってきた責任を抱えながらも、途上国支援には消極的である。2020年までに年1000億ドルとされた気候資金目標も、達成は2022年にずれ込んだ。その間に気候災害は激化し、途上国からは「裏切られた」との声が噴出した。
COP29では「2035年までに年3000億ドル」という新たな資金目標が設定されたが、インドなどは「蜃気楼にすぎない」と批判した。多くが融資や民間資金頼みで、途上国が求める「無償の公的資金」とは大きく乖離している。小島嶼国やアフリカ諸国は「生存の問題」として支援を強く求めているが、先進国の政治状況や財政難が足かせとなり、思うように進まない。開催国ブラジルのルラ大統領が「気候正義なくして解決なし」と訴えるのも、こうした途上国側の不満を反映している。
化石燃料をめぐる攻防
化石燃料の扱いは、交渉の最も難しいテーマの一つである。先進国や気候脆弱国は「段階的廃止(phase-out)」を求める一方、産油国や石炭依存国は「段階的削減(phase-down)」にこだわっている。COP26では「廃止」が「削減」に弱められ、COP27では石油・ガスへの言及自体が削除された。
COP28でようやく「化石燃料からの転換」という包括的表現が合意されたが、依然として決定的な「廃止」の言葉は盛り込まれていない。産油国は「燃料ではなく排出削減が重要」と主張し、CCSや水素技術といった解決策を前面に出している。一方、環境NGOやEUは「すべての化石燃料の早期廃止」を求め、COP30でも激しいせめぎ合いが予想される。
COP限界論の台頭
こうした行き詰まりを受け、近年は「COPの限界論」が強まっている。
- 全会一致ルールの壁:1か国でも反対すれば合意文言が弱められ、結局は「最低限の妥協」に留まる。
- 議題過多と実行不足:膨大な課題を抱えながら、国内事情を優先する各国によって実行が伴わない。
- 信頼性の低下:議長国に産油国が続き、利害関係の影が色濃く「グリーンウォッシュ」批判を招いている。
市民団体や研究者からは「壊れたプロセス」との指摘も出ており、COPを補完あるいは超える仕組みの必要性が議論されている。会場の外では数万人規模のデモが繰り返され、社会運動としての圧力も強まっている。
保守政権と懐疑論の広がり
いまやアメリカではトランプ大統領が2期目の政権を担っており、国の方針そのものが大きく変わっている。政権は「気候変動の危機は誇張されている」「ネットゼロは経済を縛り、国益を損なう」と明言し、国際的な枠組みに対しても距離を置く姿勢を示している。パリ協定からの再離脱や、国際交渉での強硬姿勢は、COPにとって大きな逆風となっている。
ヨーロッパでも状況は似ている。エネルギー価格の高騰や農業規制への反発を背景に、右派・保守政党が「脱炭素政策の見直し」を掲げて支持を広げている。EUはこれまで「世界の気候リーダー」と自認してきたが、実際には電気代の上昇や産業競争力の低下といった矛盾が顕在化し、市民の不満を強めた。ウクライナ侵攻後に石炭火力を再稼働させ、天然ガス投資を容認したことは、その矛盾を象徴する出来事だった。
こうした動きの結果、COPの合意形成はますます難しくなっている。全会一致ルールのもとでは、少数の反対勢力でも合意文書を骨抜きにできるため、強い決定が生まれにくい。国際社会が掲げる「ネットゼロ」の理想と、各国の政治的現実のあいだの溝は、以前にも増して広がっている。
「根回し・手回し・搔き回し・後回し」のCOP
COPの運営は、しばしば日本の政治やビジネス文化で語られた「根回し・手回し・搔き回し・後回し」を思わせる。事前の水面下調整は「根回し」、議長国や事務局による段取りは「手回し」、産油国や対立国が議論を混乱させるのは「搔き回し」、そして難しい争点を先送りにするのは「後回し」だ。
結果として合意は曖昧になりがちで、まさに世界規模の「日本的合意形成」ともいえる構造が繰り返されている。
代替の動き
限界が見えてきたCOPを補うために、新しい動きも出ている。
- 気候クラブ:意欲的な国だけが集まり、炭素国境調整(炭素に応じた関税)を通じて行動を強める枠組みだが、どれだけの国が参集するのか甚だ疑問である。
- 化石燃料不拡散条約:新しい採掘をやめ、生産を減らすことを国際的に取り決める構想だが、化石燃料は発電以外にも、色々な製品の原料ともなっているので、生産を減らすことができるとも思えない。化石燃料、特に石油なしに、我々の衣食住は成り立たないことは自明である。
- 司法の力:国際司法裁判所(ICJ)が各国に責任を課す仕組みを模索しているが、上記の問題に加えて、南北問題をどのように処理していくのか、この模索は不可能に近い。
これらは「COP一本では足りない」という現実を反映している。特に途上国は資金が届かないことに強い不満を持っており、複数の仕組みを組み合わせて前進しようとしている。
おわりに
COP30は、国連などの関係者にとって、パリ協定から10年という節目に開かれる重要な会議である。しかし、全会一致ルールや保守政権の台頭など、壁はこれまで以上に高くなっている。COPは「最低限の共通理解を示す場」としては続くだろうが、実際の行動は小さな同盟や地域ごとの枠組みに移っていく可能性が高い。それも、スムーズには進まない。
アマゾンから発せられる「気候正義」の声に、先進国がどこまで応えられるのか。COP30は、気候外交の行方だけでなく「COPという仕組み自体の未来」を占う試金石になる。

関連記事
-
福島原発事故後、民間の事故調査委員会(福島原発事故独立検証委員会)の委員長をなさった北澤宏一先生の書かれた著書『日本は再生可能エネルギー大国になりうるか』(ディスカバー・トゥエンティワン)(以下本書と略記、文献1)を手に取って、非常に大きな違和感を持ったのは私だけであろうか?
-
11月15日から22日まで、アゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29(国連気候変動枠組条約締約国会議)に参加してきた。 産業界を代表するミッションの一員として、特に日本鉄鋼産業のGX戦略の課題や日本の取り組みについ
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。
-
11月9日、米国の環境団体「憂慮する科学者連盟」(UCS:Union of Concerned Scientists)が非常に興味深い報告書を発表した。「原子力発電のジレンマ-利潤低下、プラント閉鎖によるCO2排出増の懸
-
アメリカは11月4日に、地球温暖化についてのパリ協定から離脱しました。これはオバマ大統領の時代に決まり、アメリカ議会も承認したのですが、去年11月にトランプ大統領が脱退すると国連に通告し、その予定どおり離脱したものです。
-
「CO2から燃料生産、『バイオ技術』開発支援へ・・政府の温暖化対策の柱に」との報道が出た。岸田首相はバイオ技術にかなり期待しているらしく「バイオ技術に力強く投資する・・新しい資本主義を開く鍵だ」とまで言われたとか。 首相
-
いつか来た道 自民党総裁選も中盤を過ぎた。しかしなかなか盛り上がらない。 5人の候補者が口を揃えて〝解党的出直し〟といっているが、その訴えが全く響いてこない。訴求力ゼロ。 理由は明確だ。そもそもこの〝解党的〟という言葉だ
-
東日本大震災から、3月11日で1年が経過しました。復興は次第に進んでいます。しかし原発事故が社会に悪影響を与え続けています。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間