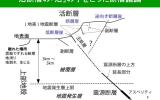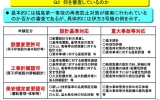低線量における放射線作用の生物学的メカニズム — 国連科学委員会の将来の事業計画の指針白書(要旨和訳)
(GEPR編集部より)国連科学委員会の中の一部局、原子放射線の影響に関する国連科学委員会は、昨年12月に報告書をまとめ、国連総会で了承された。その報告書の要約要旨を翻訳して掲載する。迂遠な表現であるが、要旨は国連の報告書間で整合性が取れていないこと、また低線量被曝についてのコンセンサスがないことを強調している。
この問題に関して、GEPRは要旨を読み込んだ米国のWNNニュースの翻訳要旨『国連、福島の放射能の人体被害を確認せず-海外の論調から』を掲載している。また日本経済新聞の米経済誌フォーブスからの転載である『放射能と発がん、日本が知るべき国連の結論』にリンクしている。ただし国連は、低線量被曝の健康被害は確認されていないことを述べたのみで、LNT仮説(しきい値なし仮説)を否定するなどの強い主張はしていない。LNT仮説は放射線防護に使われる仮説で、低線量被曝でも放射線による健康被害が起こり得る事を前提にする仮説。LNT仮説は放射線防護に使われる仮説で、説明はGEPR論文『放射線の健康影響 ― 重要な論文のリサーチ』を参照。
(以下要約)
第59回会議(2012年5月21日〜25日開催)において、UNSCEAR(原子放射線の影響に関する国連科学委員会、以下委員会)は、低線量における放射線作用の生物学的メカニズムに関する報告書について検討した。その報告書は、委員会の通常の完全な評価とは異なり、包括的になるように意図されておらず、どちらかというと、この分野での主要な進歩に重点を置き、委員会の将来の事業計画を開発するための指針を提供するように意図された。この報告書は広く関心を寄せられるものであろうため、委員会は事務局に公用文書としてそのウェブサイト上に掲載する方法を調査するよう要請した。
この報告書は、いわゆる非標的および遅発効果といわれるメカニズムについての理解は進んでおり、また高および低線量被曝による遺伝子とたんぱく質の発現量の応答差の証拠もあるが、これまでの報告書間には一貫性や統一がかけている、という結論が示されている。今のところこのような現象と放射線関連疾患の因果関係を示す兆候)はない。放射線を浴びる事による免疫応答と炎症反応などを伴う疾病とは、より明瞭な関連がある。
しかし、それらの生理学上のプロセスについて、放射線被曝の影響、特に低線量についてのコンセンサスがない。この報告書は発がんに関連するメカニズムに注目する一方、検討されたプロセスのいくつかは組織反応についても検証している。またいくつかの分野での進歩も紹介している。低線量および長期間に渡って放射線にさえあされた場合に、疾病の潜在的リスクの評価に役立つ可能性がある。
また委員会は以下の結論に達した。
(a) ヒトの疾病に寄与する可能性のある低線量の放射線作用の機構的理解についての研究促進を続ける。
(b) リスクアセスメントに機構的データを統合するため、生物学に基づいたリスクモデルおよびシステム生物学フレームワークを更に開発することを検討する。
(c) 報告書を公に利用可能とする。
(d) 3〜4年ごと適宜本件について再吟味する。
(2013年1月21日掲載)

関連記事
-
アゴラ運営のインターネット放送「言論アリーナ」。4月29日に原発をめぐる判断の混乱−政治も司法も合理的なリスク評価を」を放送した。出演は原子力工学者の奈良林直さん(北海道大学大学院教授・日本保全学会会長)、経済学者の池田信夫さん(アゴラ研究所所長)。
-
村上敬亮資源エネルギー庁新エネルギー対策課長に、FITの成果と問題点について聞いた。
-
ロシアの国営原子力企業ロスアトムが、日本とのビジネスや技術協力の関係強化に関心を向けている。同社の原子力技術は、原子炉の建設や安全性から使用済み核燃料の処理(バックエンド)や除染まで、世界最高水準にある。トリチウムの除去技術の活用や、日本の使用済み核燃料の再処理を引き受ける提案をしている。同社から提供された日本向け資料から、現状と狙いを読み解く。
-
中部電力の浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)は、昨年5月に菅直人首相(当時)の要請を受けて稼動を停止した。ここは今、約1400億円の費用をかけた津波対策などの大規模な工事を行い、さらに安全性を高めようとしている。ここを8月初頭に取材した。
-
東日本大震災の地震・津波と東京電力福島第一原子力発電所事故でダメージを受けた、福島浜通り地区。震災と事故から4年近くたち、住民の熱意と国や自治体などの支援で、自然豊かな田園地帯は、かつての姿に戻り始めようとしている。9月5日に避難指示が解除された楢葉町の様子を紹介する。
-
一般社団法人「原子力の安全と利用を促進する会」は、日本原子力発電の敦賀発電所の敷地内断層(2号炉原子炉建屋直下を通るD-1破砕帯)に関して、促進会の中に専門家による「地震:津波分科会」を設けて検討を重ね、原子力規制委員会の判断「D?1破砕帯は、耐震指針における「耐震設計上考慮する活断層」であると考える」は見直す必要がある」との結論に至った。(報告書)
-
12月22日に開催された政府の地球温暖化対策推進本部の会合で、本部長を務める安倍晋三首相が来春までの温対計画策定を指示しました。環境省の中央環境審議会と、経済産業省の産業構造審議会の合同会合で議論が始まっています。
-
2月4日に公開したアゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」の番組「原子力規制委員会は何を審査しているのか」の要旨を紹介する。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間