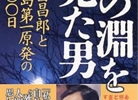映画「パンドラの約束」(下)【改訂】 — 賛成、反対の二分論の克服を
「(上)米環境派、原子力否定から容認への軌跡」から続く
3・米国での反響

画像5・東京の試写会でのロバート・ストーン監督
6月の公開前後にニューヨーク・タイムス、ワシントンポストなど主要紙の他、NEI(原子力エネルギー協会)、サイエンティフィック・アメリカン(Scientific American:著名な科学雑誌)、原子力支持および反原子力の団体や個人などが、この映画を記事にした。
米国でも東部のリベラル色の強い新聞、テレビは原子力に批判的な論調が多い。紹介記事の多くは特に支持、不支持という立場は示さず、映画の内容や映画祭での評価などを淡々に記載していた。他のネットは、原子力支持の団体・個人は映画の内容を賞賛・推奨し、反対派は否定的なコメントを残しているという状況だった。
同映画へのコメントとして、的を得ていると感じた記事の一部を紹介する。
<ニューヨーク・タイムス(6月14日の記事抜粋)>
ドキュメンタリーやそれを制作する自主映画には、制作者と意見を一つにする観客を狙った作品が多く、釈迦に説法といった非難の声が寄せられる。政治的に保守的な観客に向けたドキュメンタリー映画は少なく、映画祭での成功を模索しても、成功の度合いはさまざまである。その意味において、「パンドラの約束」はサンダンス映画祭で高い評価を受け、素晴らしい成果を残した。
<サイエンティフィック・アメリカン(6月11日の記事抜粋)>
「パンドラの約束」は、私たちのリスク認知に感情に訴えかけるようなイメージを効果的に活用することで、我々に影響を与える説得力のある作品となっている。「冷戦時代など歴史的背景からの原子力の何に対しても恐怖を持っている」、そして「反原子力団体と非常に強く結びついたアイデンティティを持っている」ベビーブーム世代の環境保護活動家の心を変えることはできないかもしれない。しかし若い世代や寛容な心を持った観客がこの作品を見ることにより、この重要なクリーンエネルギーの資源(原子力)に関してよく知られている反対の理由だけでなく、大いに賛成する理由が議論されるきっかけとなるのかもしれない。
しかし現地の日本人に聞くと、米国の映画館での客の入りは多くなかったそうだ。一般市民レベルでの反響が大きいかといえば、それは違うという。
私は、この映画が環境保護活動家や政治家など限られた対象へのメッセージを発信した映画だという印象を受けた。また米国の各種世論調査では、福島事故以降も原子力を重要なエネルギー源の一つと考える米国民の割合は各種世論調査では約70%もいる。原子力の運営を社会の支持が支えている。そのために、一般の人々の注目を集めるのは難しかったのかもしれない。
4・個人的な意見—原子力プラス評価だけへの違和感
私は、この映画を高く評価する。この映画の興味深かった点は「原子力肯定のメッセージを発信しているのが、『かつて原子力に反対していながら、現在は原子力支持に変わった人間である』」ことにあると思う。
実は私も、原子力の拒絶感から肯定へ、同じような思索の軌跡をたどった。当初原子力に感じたものは「気味の悪さ」だ。幼少のころ報道で知ったチェルノブイリ事故、そして日本国民が必ず学ぶ広島・長崎の原爆の悲惨さを知ったため、原子力には違和感が今でもある。福島事故では国土を汚染した事故にたいする怒り、そして直後の放射能をめぐる恐怖を、他の日本国民と一緒に抱いた。
しかし事故前にあるメディアのエネルギー担当記者として、日本のエネルギーを学び、取材をした。そこで原子力は日本、そして世界のエネルギーをめぐる諸問題を解決する重要な手段と考えるようになった。特に日本は「無資源国」という宿命を持つため、脱化石燃料が必要だ。世界に目を転じれば、気候変動やエネルギー需要の急増という問題がある。これらの問題を解決する手段は、現時点で原子力の利用しか思いつかない。
ただし私は無批判に原子力推進とは主張できない。福島原発事故とその後の混乱を筆者は日本で目撃した。そこでの人々の抱いた恐怖感は、いくら説明をしても、なかなかぬぐい去ることはできないものだった。そして私も原子力事故直後の数カ月は正確な情報を手に入れ、放射線について学ぶまで、心配をした。
映画でのメッセージは、「適切に説明すれば、人々は原子力に対する不安を払拭できるはずだ」というものだ。日本での現実は違った。そして、こうした感情で人々は動く。原子力の利用には多くのメリットがあっても、また流れる情報に誤りがあっても、反対の思いを持つ人を説得し尽くすことは難しい。そして、そうした反対意見も、民主主義体制を持つ社会の中では尊重しなければならない。
原発事故を経験し、人々がそれに不安を抱き続けている日本では、原子力をめぐる合意形成は難しいだろう。私は原子力の利用が必要と思うものの、日本国内での合意形成はあきらめている。その点で、手放しで原子力の未来を訴える、この映画に違和感を感じた。
5・社会的な意義—原子力をめぐるバランスの取れた議論のきっかけに
ただし、この映画は日本で広く見られるべきだと思う。原発事故以降、日本では原子力に対する批判が高まり、それまでの大半の人の無関心から一点して話題の中心になった。そして原子力への批判から、電力業界や研究者、政府当局者が萎縮し、発信が縮小してしまった。既存メディアからの情報の多くは放射能の危険、そして原発への批判一色になっているように見える。日本で流通する原子力の情報が、「反原発」へとかなり偏向している。
そして、原子力をめぐる議論が深まっているとは言えない。原子力について、問題を「賛成」「反対」と二分する人ばかりで、「別の意見を聞いて考える」という知的な営みをする人が少ないようだ。今回の日本での試写会で、配給会社は原子力に否定的な文化人を数多く招待したが、ほとんど来なかったという。そうした思考停止の状況は、日本にとってためにはならないはずだ。
この映画では、米英で中立な立場の人々が原子力について考え、原子力を肯定する意見を述べた。これらの人々は日本の原子力をめぐる騒擾の中にいない。そのためにメッセージは、見る者に説得力を持ったものとなって伝わってくる。
そして気候変動、エネルギー不足という地球規模の問題は、日本人が原子力にどのような結論を出そうとも、私たちの生活に迫り来る。原発をめぐるどのような考えを持とうと自由だ。しかし今こそ、日本でバランスの取れた検討をするために、この映画は評価される価値はある。

写真6・映画に登場した、夜のエネルギー使用の先進国への偏在。世界規模のエネルギー使用の増大で、やがて地球は夜に全体が輝く星になってしまうだろう。
(2013年10月21日掲載)

関連記事
-
原発事故当時、東京電力の福島第1原発所長だった、吉田昌郎氏が7月9日に亡くなった。ご冥福をお祈りします。GEPRでは、吉田氏にインタビューしたジャーナリスト門田隆将氏の講演。
-
気候変動対策を巡る議論は、IPCC報告書や各種の「気候モデル」が示す将来予測を前提として展開されている。しかし、その根拠となる気候モデルは、科学的厳密性を装いながらも、実は数々の構造的な問題点と限界を抱えている。 本稿で
-
はじめに 気候変動への対策として「脱炭素化」が世界的な課題となる中、化石燃料に依存しない新たなエネルギー源として注目されているのがe-fuel(合成燃料)である。自動車産業における脱炭素化の切り札として各国が政策的な後押
-
第6次エネルギー基本計画の策定が大詰めに差し掛かっている。 策定にあたっての一つの重要な争点は電源ごとの発電単価にある。2011年以降3回目のコスト検証委員会が、7月12日その中間報告を公表した。 同日の朝日新聞は、「発
-
エネルギー基本計画の改定に向けた論議が始まったが、先週の言論アリーナで山本隆三さんも指摘したように、今の計画はEV(電気自動車)の普及をまったく計算に入れていないので、大幅に狂うおそれが強い。 新しい計画では2050年ま
-
地球温暖化によってサンゴ礁が失われるとする御用科学の腐敗ぶりを以前に書いたが、今度は別のスキャンダルが発覚した。 「CO2濃度が上昇すると魚が重大な悪影響を受ける」とする22本の論文が、じつは捏造だったというのだ。 報じ
-
エネルギー政策の見直し議論が進んでいます。その中の論点の一つが「発送電分離」です。日本では、各地域での電力会社が発電部門と、送電部門を一緒に運営しています。
-
>>>(上)はこちら 3. 原発推進の理由 前回述べたように、アジアを中心に原発は再び主流になりつつある。その理由の第一は、2011年3月の原発事故の影響を受けて全国の原発が停止したため、膨大な費用が余
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間