水素社会構築のため、社会影響の「スケール感」を持とう
国際環境経済研究所(IEEI版)
「水素社会到来か?」の前に必要なこと
燃料電池自動車の市場化の目標時期(2015年)が間近に迫ってきて、「水素社会の到来か」などという声をあちこちで耳にするようになりました。燃料電池を始めとする水素技術関係のシンポジウムや展示会なども活況を呈しているようです。
しかし、「水素社会の実現のために」行われているさまざまな取り組みの中には、「水素社会の実現」が目的化してしまっているようなものも見られます。ムードに流されることなく、それぞれの取り組みが日本のエネルギー需給とCO2排出削減に与えるインパクトのスケールをきちんと評価し、取り組みの優先順位と費用対効果を見極めていくことが必要です。
今回は、そのスケール感にかかわるいくつかの材料を提供したいと思います。
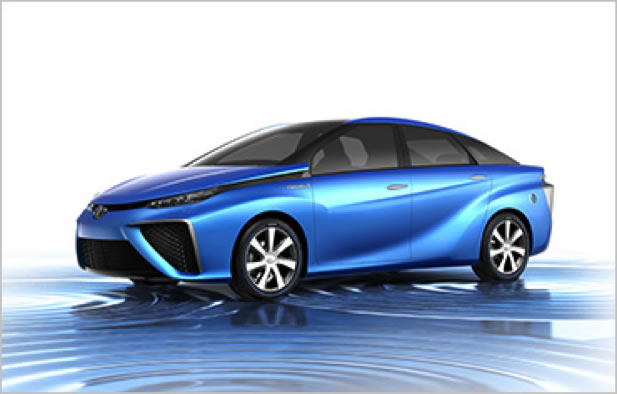
トヨタ自動車が2013年の東京モーターショーに出展した水素自動車。エンジン、タンクの小型化で、外見上は一般車と変わらない。同社ホームページより)
水素燃料自動車、200万台の影響
政府は燃料電池自動車の普及目標として「2025年に200万台」の目標を掲げ、自動車、エネルギー企業も呼応して目標達成に向けた取り組みを進めています。冒頭の「燃料電池自動車の市場化の目標時期」は、その一環でもあります。さらに政府は、家庭用燃料電池を2030年で530万台普及させるとの目標も掲げています。では、この規模の燃料電池の導入は、日本のエネルギー需給とCO2排出量にどれほどのインパクトを及ぼすものなのでしょうか。このスケール感は、以下のようなラフな計算で簡単に見ることができます。
日本国内の自動車の保有台数は約7500万台で、運輸部門で消費されている化石燃料の量は、日本の化石燃料の供給量の約20%です。ですから、燃料電池自動車の普及(万台)によって節減できる化石燃料供給量は0.5%程度ということになります。
一方、家庭用燃料電池の場合は、エネルギー効率が大幅に高まるものの、都市ガスなどの化石燃料を燃料とし、燃料電池の中で水素を取り出す際にCO2を出しますから、化石燃料フリー、CO2フリーではありません。それでも、その普及によってエネルギー効率は大幅に高まるということで、とても雑なやり方ではありますが、燃料電池自動車の場合の計算と同様のやり方で見てみましょう。
すると日本の世帯数は約5000万世帯、家庭部門で消費されている化石燃料の量は、日本の化石燃料の供給量の約6%なので、家庭用燃料電池の普及(530万台)によって節減できる化石燃料供給量は0・6%以下ということになります。(これは上述の理由で過大な数字となっていることに注意してください。)
つまり、現在の燃料電池の普及目標が日本の化石燃料の供給とCO2排出にもたらすインパクトは、ざっくり言って1%程度以下の削減スケールです。
水素社会の構築に向けて、燃料電池の開発と普及を進めることはきわめて重要なことです。しかし、この程度のスケールでは不十分なことは明らかでしょう。水素社会の構築の目的を考えたら、最低でもこれより一桁大きな規模での水素エネルギーの利用拡大が図られなくてはなりません。(注1)
そのためには、燃料電池自動車の一層の普及拡大などはもとより、化石燃料供給量の35%を消費量している発電分野や25%を消費している製造業分野においても、水素エネルギーの大幅な導入拡大策が併せて検討される必要があります。
水素供給も問題になる
次に、水素の量に関わる問題について見てみましょう。現状、国内の水素供給ポテンシャルは80〜160億m3/年あると言われています。(注2)
燃料電池自動車1台当たりの年間水素消費量は、約1000m3と見積もられているので、この量は燃料電池自動車などへの供給用には、量的には十分のように見えます(200万台でも必要量は約20億m3)。
しかし、160億m3の水素から得られるエネルギー量(=2・0×108GJ)は、日本の最終エネルギー消費量(=1・4×1010GJ)の1・4%程度に過ぎません。この程度の量では、ほとんど効果がないことは自明でしょう。さらに、そもそもこの量では2025年頃には、燃料電池自動車200万台分を賄うことも難しいと見る専門家もいるのです。(注3、4)
ですから、日本は、水素エネルギーを海外から持って来ることを考えざるを得ないということになります。
水素社会の基盤整備で何が必要か
以上のような事実認識に立てば、水素社会の構築に向けて、優先的にやらなければならないことは自ずと見えて来るはずです。
まず、日本は、海外において水素エネルギーを大量に、かつ、安価に製造する技術を磨く必要があります。化石燃料への依存を減らし、CO2の排出削減を図ることが目的であるなら、海外の質的にも量的にも恵まれた太陽、風力エネルギー資源を利用したCO2フリーの水素エネルギーの製造を目指すべきでしょう。そのためには、海外の太陽、風力エネルギー資源環境の下で優れた性能を発揮する技術を開発しなければなりません。いつまでも国内での製造を前提としていたら、日本の技術はガラパゴス化してしまいます。
海外から水素エネルギーを長距離、長時間かけて運んでくるためには、物性的に貯蔵、輸送が困難な水素を、安全に、そして大量、かつ、安価に貯蔵、輸送する方途も、十分に検討される必要があります。
先に見たように、国内の燃料電池向けに必要となる量とは桁違いに大量の水素エネルギーを取り扱うことが必要なのです。水素エネルギーを水素の形で貯蔵、輸送するのが良いのか、貯蔵、輸送が容易な有機ハイドライドやアンモニアなど、水素エネルギーを多く含有する別の化学物質に変えて利用するのが良いのか、十分に検討することが必要です。大量貯蔵、輸送用に、高価で繊細な貯蔵設備や輸送手段を用いることはできないでしょう。
さらに、水素社会の構築の目的に立ち返って考えるならば、燃料電池自動車と家庭用燃料電池の導入だけでは不十分です。先にも述べたように、発電分野や製造業の分野など、エネルギーを大量に消費している分野に水素エネルギーを導入する方策が考えられなければなりません。(例えば、発電用の燃料電池の導入などは、分散型のエネルギー・システムを構築する上でも重要です。)そういったことを考えた時、官民ともに現状のような資源配分で良いのか、やり残していることはないのか、振り返ってみる必要があると思います。
実際には、水素社会では、用途、輸送距離や場所によって、水素を始めとするいろいろな物質や技術がその特徴に応じて水素エネルギーを運ぶために用いられることになるでしょう。ただ、その根幹となるエネルギー・システムの構築に当たっては、以上に述べたようなスケール感を踏まえた取り組みが不可欠ではないでしょうか。
エネルギー制約と環境制約の解決策となり得る、夢と可能性に満ちた水素社会にできるだけ早く到達するための取り組みを、一歩一歩、確実に進めて行きたいものです。
(注1)このコラムでは、後段で記すように「水素エネルギー」という用語には、水素及び水素を多く含有する化学物質の両方を含む意味で用いる。
(注2)「貯蔵技術が変える水素戦略−課題はコストとCO2回収」、日経エコロジー、2013年10月号、P12~13
(注3)同上
(注4)これは、この160億m3/年の「余剰」水素は、工場等において副生するものであるため、他の燃料との価格関係によっては自家消費され、必ず、燃料電池自動車用に回るものではないためです。さらに、燃料電池が不純物を嫌うため、工場で副生する水素を燃料電池自動車の燃料用として販売するにはこれを精製する必要があり、そのための追加コストがかかるので、自家消費した方が経済的に有利になる可能性が大きいという事情も考慮する必要があるという指摘もあります。

関連記事
-
カリフォルニア州でディアブロ・キャニオン原発が2025年までに停止することになった。これをめぐって、米国でさまざまな意見が出ている。
-
COP28が11月30日からアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催される。そこで注目される政治的な国際合意の一つとして、化石燃料の使用(ならびに開発)をいつまでに禁止、ないしはどこまで制限するか(あるいはできないか)と
-
ロシアからの化石燃料輸入に依存してきた欧州が、ロシアからの輸入を止める一方で、世界中の化石燃料の調達に奔走している。 動きが急で次々に新しいニュースが入り、全貌は明らかではないが、以下の様な情報がある。 ● 1週間前、イ
-
マサチューセッツ工科大学(MIT)の科学者たちによる新しい研究では、米国政府が原子力事故の際に人々が避難すること決める指標について、あまりにも保守的ではないかという考えを示している。
-
前回、防災白書が地球温暖化の悪影響を誇大に書いている、と指摘した。今回はその続き。 白書の令和2年度版には、「激甚化・頻発化する豪雨災害」という特集が組まれている。これはメディアにもウケたようで、「激甚化・頻発化」という
-
以前紹介したスティーブン・クーニン著の「Unsettled」の待望の邦訳が出た。筆者が解説を書いたので、その一部を抜粋して紹介しよう。 スティーブン・クーニンは輝かしい経歴の持ち主で、間違いなく米国を代表する科学者の1人
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
「電力システム改革」とはあまり聞きなれない専門用語のように思われるかもしれません。 これは、電力の完全な自由化に向けて政府とりわけ経済産業省が改革の舵取りをしています。2015年から2020年にかけて3ステップで実施され
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間














