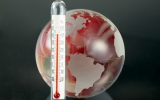原子力規制委員会の見識を疑う — 民意で安全を決めるのか?
事後的に審査要件を一般募集
原子力規制委員会により昨年7月に制定された「新規制基準」に対する適合性審査が、先行する4社6原発についてようやく大詰めを迎えている。残されている大きな問題は地震と津波への適合性審査であり、夏までに原子力規制庁での審査が終わる見通しが出てきた。報道によれば、九州電力川内原発(鹿児島県)が優先審査の対象となっている。
規制庁内審査が終わると、それぞれの原発ごとに審査結果をまとめた「審査書案」が作られ、それを原子力規制委員会が承認し、審査書となった後、設置変更許可が出されることになる。昨年の内に第1号の審査が終了すると見込まれていたので、現時点でかなり遅れている。
ところが、2月12日の定例の原子力規制委員会の定例の委員会会合において田中規制委員長から唐突に、「第1号の審査書案ができた時点でそれに対する科学的・技術的意見を一般から募集したらどうか」との提案がなされた。(同日の会議議事録)
また、併せて「自治体からの要望が有れば公聴会も考えたいので、2月19日の定例委員会に具体案を出すように」と規制庁事務当局に指示が出された。
そして19日の委員会において、審査書案ができた段階で4週間程度の公募期間の設定と、要望に応じて公聴会を開くことが大した議論もなく了承された。(同日の会議議事録)
審査の混乱が重なる懸念
適合性判断に広く国民の科学的・技術的意見を入れようというのである。妥当と思われる意見があれば、審査書案を書き直すという。土台無理である。
適合性に係る会合は既に83回を数えており、時には1回の会合で10時間を超えている。このような議論に参加してこない人に科学的・技術的判断ができるとは考えられない。また、公聴会に関しては、規制委員の原子力災害対策指針が対象とするのは30キロメートル圏以内の自治体であり、多くの自治体から要望が出ることが予想される。
さらに、公平を期すためには、第2号審査書案以下に対しても同じことを企画する必要があり、6原発全部で240日を要することになる。第1号の審査書案だけに留めるのであれば、それに対する正当な理由付けが必要になる。
新規制基準を作るに当たっては1カ月間の意見公募を行っており、一般国民の意見はその中に反映されている。規制委員会委員は国民の代表たる国会の承認を得て委員に就任しており、粛々と新規制基準への適合性審査を終了させる義務と責任を負っている。
ただでさえ審査が長引き、再稼働が遅れ年間4兆円に近い外貨が余分に流出している現状では、一刻も早い真摯な審査が求められる。無為なプロセスを導入することで再稼働を遅らせるべきでない。この点についても、経済がどうなろうと関知せずという発言を繰り返す委員長の見識を疑う。
なお、審査書案は最終的に規制委員会の審議を経なければならない。専門性において規制委員会では全てをカバーすることはできない。それを補完するために、法律で設置を義務付けられている原子炉安全専門審査会(炉安審)の検討結果を規制委員会が見て判断する必要がある。炉安審は未だにメンバーも決まっていない。早急に決めるべきである。
(2014年3月17日)

関連記事
-
日本の電気料金は高騰を続けてきた。政府は、産業用及び家庭用の電気料金推移について、2022年度分までを公表している。 この原因は①原子力停止、②再エネ賦課金、③化石燃料価格高騰なのだが、今回は、これを数値的に要因分解して
-
(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑩:CO2で食料生産は大幅アップ) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点㉒に続いて「政策決定者向け要約」を読む。 冒頭
-
G7伊勢志摩サミットに合わせて、日本の石炭推進の状況を世に知らしめるべく、「コールジャパン」キャンペーンを私たちは始動することにした。日出る国日本を「コール」な国から真に「クール」な国へと変えることが、コールジャパンの目的だ。
-
イタリアのトリノで4月28日~30日にG7気候・エネルギー・環境大臣会合が開催され、共同声明を採択した。 最近のG7会合は、実現可能性がない1.5℃目標を前提に現実から遊離した議論を展開する傾向が強いが、トリノの大臣会合
-
ESG投資について、経産省のサイトでは、『機関投資家を中心に、企業経営の持続可能性を評価するという概念が普及し、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークとして
-
後半では核燃料サイクルの問題を取り上げます。まず核燃料サイクルを簡単に説明しましょう。核燃料の95%は再利用できるので、それを使う構想です。また使用済み核燃料の中には1-2%、核物質のプルトニウムが発生します。
-
崩壊しているのはサンゴでは無く温暖化の御用科学だ グレートバリアリーフには何ら問題は見られない。地球温暖化によってサンゴ礁が失われるという「御用科学」は腐っている(rotten)――オーストラリアで長年にわたりサンゴ礁を
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間