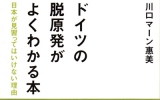総合エネルギー市場を創設-東商取浜田新社長に聞く
商品先物市場を運営する東京商品取引所(TOCOM)の社長に 浜田隆道氏が就任した。経済産業省出身で同社専務から昇格した。「総合エネルギー市場」としての発展を目指すという。抱負を聞いた。

浜田 隆道(はまだ・たかみち)1950年生まれ。東京大学経済学部卒業。50年通商産業省(現経済産業省)入省。主にエネルギー関係の部署を多く歩み、大臣官房審議官(産業技術担当)を経て退官。2002年から06年まで東京工業品取引所の専務理事を務める。14年6月、株式会社東京商品取引所代表執行役専務。15年6月取締役代表執行役社長に就任。
-TOCOMは商品先物取引の全体の落ち込みで、厳しい経営状況だ。商品先物取引法の改正により勧誘規制が強化されたことなどが一因だ。立ち直れるのか。
浜田・確かに今は厳しい状況だ。しかし私は日本の商品先物業界、そしてTOCOMの将来をまったく悲観していない。江崎格前社長(元資源エネルギー庁長官)のもと、取引システムや取引制度のグローバル化また新商品の開発などへ取り組んできたことによって、明るい兆しが見え始めている。また昨年9月に中期経営計画で「1・安定した経営基盤の構築」「2・電力市場の創設とLNG市場の活性化を柱とする総合エネルギー市場の創設」「3 ・JPX(日本取引所グループ)など国内外の取引所との連携強化」という方向を打ち出した。それが形になりつつある。
-現状はどうか。
浜田 ・経営では合理化を進め、他取引所との協力も深めている。JPX(日本取引所グループ)との取引システムの共同利用を進めている。シティバンク銀行が金融機関では初めて今年7月にクリアリングハウスのJCCH(株式会社日本商品清算機構)の清算資格を取得した。取引の決済の履行を保証する組織に海外の大銀行が加入したことは意義深い。取引の安全が一段と保証されたことを契機に国際的な機関投資家の参加が増えることを期待している。
エネルギーでは、同国の石油最大手の台湾中油(CPC)と、国内全域に供給する台湾電力 が7月に、関連会社のJOE(Japan OTC Exchange)が運営するLNG市場への参加を決めた。JOEは将来の先物市場への発展をにらみながらLNG(液化天然ガス)のOTC(店頭取引) 市場を14年秋から運営しているが、今年7月に初めて取引が成立した。
TOCOMは2001年から中東産原油の先物市場を運営しているが、その価格は世界のベンチマークになりつつある。TOCOM市場の価格指標性を高めることで、アジアのエネルギー取引の中心にTOCOMが育つことは可能だ。
電力先物市場の開設は16年度中を目標
-商品先物は一般になじみがなく、 個人投資家にとっては難しい取引の印象がある。
浜田・先物がコワイというのは10年前の話だ。業界も取引所も粛々と改革を進めている。かつて日本の商品先物市場は8−9割が国内の個人投資家の売買だった。現在のTOCOMでは、個人の注文は2−3割程度。残りは事業者のヘッジ取引(先物で事前に売買し値段を確定する手法)や、機関投資家、プロップハウス(自己資金による投資家)などの取引。また、海外からの参加も増えており、石油市場では5割程度まで取引高に占めるその割合が高まっている。
-電力、ガス、石油、それぞれのエネルギー事業者との関係をどのように構築していくか。
浜田 ・ぜひ、TOCOMの市場を活用していただきたい。TOCOMの強みは商品の多様さだ。ドバイ原油、ガソリン、灯油、軽油を上場している。LNGはOTC市場を運営し、そして16年度中には電力先物も上場する予定だ。
今後、小売り自由化で、電力もガスも、販売価格の変動に直面することになる。発電に必要な燃料費についても、昨年から の石油価格の急落など を見れば、その振れ幅は大きい。先物で注文を入れれば、その時点で未来での取引価格が固定される。欧米のエネルギー事業者がすでにやっているように、リスク管理の観点から経営において商品マーケットを活用していくことは必須になるのではないか。
2011年以降の日本は、LNGで「ジャパン・プレミアム」を払うことになった。現物を突如、大量に、現物で調達したからだろう。エネルギー価格の指標となる市場があることは、需給を反映した価格形成の意味で日本のためにもなる。
参加者に使い勝手のよい市場をつくる
-電力先物市場はどのような姿になるのか。
浜田 ・今年7月、経済産業省が電力先物市場の枠組みを検討・協議するために設置した研究会においてとりまとめがなされた 。(経産省ホームページ電力先物市場報告書)電力先物市場は、15ヶ月の取引期間とし、現金決済(現物の受け渡しなく、金銭のみで決済する)による取引が行われる 。
最終決済価格は日本卸電力取引所(JEPX)のシステムプライス(スポット取引の全国統一の約定価格)の月間平均としており、両市場は相互に連携している。だいたいの市場の姿は共有できた。取引期間を15ヶ月としたのは官公庁・自治体の大口電力に係る入札が1年前からとするものが多く、こうした商慣習や事業者の意見を参考にした。
電力会社の方と意見交換を当社は重ねているが、その優秀さ、まじめさを改めて認識している。システム改革の方向が定まったために、どの会社も社内で研究を進めている。また先物市場の利用について、急速に理解が進んでいるようだ。
-電力先物市場は発展するのか。
浜田 ・成長を期待している。電力システム改革の完全な姿は現時点ではまだ見通せないが、明らかなのは多様なプレイヤーが参加して、その産業が活性化することだ。新しく参入するあらゆる立場の人にヘッジニーズはあるだろう。例えば、電気事業者が将来の電力調達価格を決めるとか、発電事業者が将来のLNGなどの調達費用と売電価格を先物取引でロック(固定)し利益に直結する発電コストを確定するなど、さまざまな使い方が考えられる。また、機関投資家などの参入も期待できる。
日本のエネルギーの事業者にとって、価格が動くことで利益を見通せない形のビジネスは、これまでと違うものだ。その対応策として先物市場を使えば、リスクを減らし、将来への対応をしながら、ビジネスを進められると思う。欧米の事業者がすでに行っていることだ。
取引市場は一種の公共財だ。一民間企業でありながらも、その役割は公的な要素が極めて強い。日本経済にとっても、電力、ガス、石油の各業界にとっても、必要不可欠な産業インフラになりたいと思う。私たちは参加者の方の意見を聞きながら常に市場を使い勝手のよいものに変えていく。ぜひエネルギー事業者の皆さんの力をお借りしたい。
(この原稿は、エネルギーフォーラム9月号から転載した。許諾をいただいた同社に感謝を申し上げる。)
(2015年9月14日掲載)

関連記事
-
エネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営するアゴラ研究所は、インターネット放送「言論アリーナ」という番組を公開している。8月27日は午後8時から1時間にわたって、『原発は「トイレなきマンション」か? — 核廃棄物を考える』を放送した。
-
経産省・資源エネルギー庁は、現在電力システム改革を進めている。福島原発事故の後で、多様な電力を求める消費者の声が高まったことが背景だ。2020年までに改革は完了する予定で、その内容は「1・小売り全面自由化」「2・料金規制撤廃」「3・送配電部門の法的分離」などが柱で、これまでの日本の地域独占と「10電力、2発電会社」体制が大きく変わる。
-
自民党は「2030年までに温室効果ガスの排出量を2013年度比で26%削減する」という政府の目標を了承したが、どうやってこの目標を実現するのかは不明だ。経産省は原子力の比率を20~22%にする一方、再生可能エネルギーを22~24%にするというエネルギーミックスの骨子案を出したが、今のままではそんな比率は不可能である。
-
1997年に採択された京都議定書は、主要国の中で日本だけが損をする「敗北」の面があった。2015年の現在の日本では国際制度が年末につくられるために、再び削減数値目標の議論が始まっている。「第一歩」となった協定の成立を振り返り、教訓を探る。
-
日本のすべての原発は現在、法的根拠なしに止まっている。それを確認するために、原子力規制委員会・規制庁への書面取材を行ったが、不思議でいいかげんな解答をしてきた。それを紹介する。
-
映画好きのAさんは最近、自宅に大画面テレビとホームシアターの設備を備えつけた。「大型テレビは電気の消費が増えるからエコじゃないね」と友人に揶揄されたAさん、「我が家の大画面テレビの電気は、北海道の稚内にある風力発電所から届いたものなんだよ」と得意気だ。
-
東日本大震災で事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所を5月24日に取材した。危機的な状況との印象が社会に広がったままだ。ところが今では現地は片付けられ放射線量も低下して、平日は6000人が粛々と安全に働く巨大な工事現場となっていた。「危機対応」という修羅場から、計画を立ててそれを実行する「平常作業」の場に移りつつある。そして放射性物質がさらに拡散する可能性は減っている。大きな危機は去ったのだ。
-
7月2日付の各紙の報道によれば、7月1日の原子力規制委員会での審議とそのあとの記者会見の場でまたまた、とんでもないことが起こっている。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間