水素発電で火力発電を代替するという幻想
政府の第6次エネルギー基本計画(案)では、2030年までにCO2排出量を46%削減する、2050年までにCO2排出を実質ゼロにする、そのために再生可能エネルギーによる不安定電源を安定化する目的で水素発電やアンモニア発電、炭酸ガス回収貯留(CCS)付き火力発電を大幅に導入して、石炭・LNG(液化天然ガス)発電に置き換えるという政策を取ろうとしています。また、太陽光発電の余剰電力を水素やアンモニア製造に回して貯蔵し、夜間・曇・雨時の発電用に供給するという政策も意図されています。
この政策に対応して、水素の供給量目標は、2030年300万トン、2050年2000万トンと掲げられています。
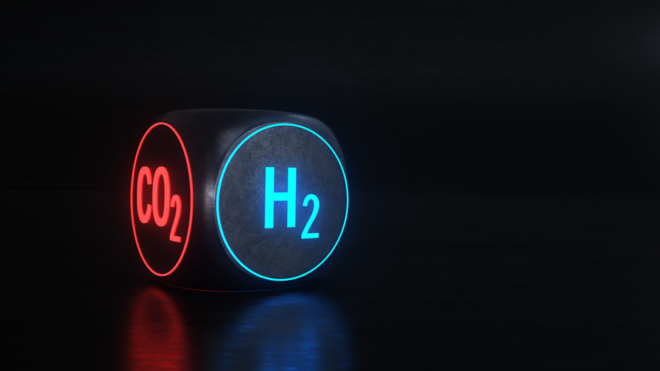
style-photography/iStock
目標に組み込まれている各種の発電技術は、あたかもすぐに大規模に実用化でき、国レベルのCO2排出を何割も削減できるかのように表現されていますが、実際は、基本技術さえ開発途上であり、これから実証試験を行って大規模化の技術を確立して行かなければならないものです。更に、実現できた設備の運転・維持にどれだけのCO2を排出するかを評価しなければならない段階にあります。
ここでは、水素発電で石炭火力発電やLNG火力発電を置き換え、CO2排出をゼロに持って行く場合を考えてみます。
まず、CO2排出が最も多い石炭火力発電を水素発電に切り替える場合です。
日本での火力発電用石炭消費量(2018年)は約1億1100万トンです。石炭の発熱量は、6900kcal/kg 注1)ですので、年間総発熱量は7.7x10の14乗kcalです。水素の発熱量は、34000kcal/kg ですから、石炭と同じ熱量を出すためには、年に2260万トンの水素が必要です。
2050年までに現在の石炭消費量をゼロにしていくためには、水素発電用の水素を2260万トン供給できるようにする必要があるわけですが、エネルギー基本計画では2050年に水素を2000万トン供給するという目標になっており、この数字だけで既に水素が不足するという計算になります。
火力発電では、LNG火力も大きな割合を占めています。LNG火力発電も水素発電に置き換えなければ、CO2の排出はゼロになりません。
日本でのLNGの発電用消費量(2019年)は約4800万トンです。LNGの発熱量は13000kcal/kgですので、年間発熱量は6.2x10の14乗kcalです。水素の発熱量は34000kcal/kgですから、LNGと同じ量の熱量を出すためには、年に1800万トンの水素が必要です。
石炭火力とLNG火力の両方を水素発電に置き換えるには、4060万トンの水素が必要であり、2050年目標の水素供給量2000万トンでは、発電量の半分も担えないことになります。
つまり、CO2排出をゼロにはできません。
以上のように、2050年目標の水素供給量2000万トンという数字は、それを全量水素発電に供給しても火力発電の半分を代替できる程度です。電気自動車用に大量に必要となる水素燃料電池用の水素供給を行う余力は全く無いということになります。
これらを纏めると、2050年カーボンニュートラル目標を達成するためには、発電用に使う水素量を減らし、その分を自動車用水素燃料電池に振り向け、発電分野のC02排出削減には原子力を使うのが合理的であるということになります。
日本の経済力を維持し、エネルギーや食糧、ワクチンなどの輸入を可能にするだけの資金を確保するためには、エネルギーの安定供給とリーズナブルな価格による産業力の維持が重要であり、原子力の活用が不可欠な条件になると考えられます。第6次エネルギー基本計画(案)の中の、「可能な限り原発依存度を低減」という文言を削除し、「可能な限り原発を活用する」という文言を入れて、現時点から原子力の再稼働・新増設・リプレースを推進していかなければ、次世代の若者の活躍の場を提供することはできないと考えられます。
注1)「エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数(資源エネルギー庁2018年度改訂)」によると、石炭の発熱量は、28.7MJ/kg = 28.7X106J/kgx0.24cal/J = 6.9x106cal/kg=6.9x103kcal/kg =6900kcal/kg

関連記事
-
半世紀ほど前から原子力を推進することを仕事としていたが、引退したとたんに自分自身が原発事故で避難しなくてはならなくなった。なんとも皮肉な話だ。
-
1. 洋上風力発電は再エネ発電の救世主だったはず?? 図1は、東北電力エリア内の2025年1月31日の太陽光発電と風力発電の実績値(30分間隔)です。横軸は24時間、縦軸は発電量(MW)です。太陽光発電の発電量は赤線で示
-
「持続可能な発展(Sustainable Development)」という言葉が広く知られるようになったのは、温暖化問題を通してだろう。持続可能とは、簡単に言うと、将来世代が、我々が享受している生活水準と少なくとも同レベル以上を享受できることと解釈される。数字で表すと、一人当たり国内総生産(GDP)が同レベル以上になるということだ。
-
以前書いたように、再生可能エネルギー賦課金の実績を見ると、1%のCO2削減に1兆円かかっていた。 菅政権が26%から46%に数値目標を20%深堀りしたので、これは年間20兆円の追加負担を意味する。 20兆円の追加負担は現
-
1月12日の産経新聞は、「米マクドナルドも『多様性目標』を廃止 トランプ次期政権発足で見直し加速の可能性」というヘッドラインで、米国の職場における女性やLGBT(性的少数者)への配慮、『ポリティカルコレクトネス(政治的公
-
2024年11月9日20時22分、四国電力管内で最大36万5,300戸の停電が発生した。今回の停電は、送電線が停止してその先に電気が送れなくなったことによるものではなく、他電力との連系線の制御がうまくいかず、四国管内の需
-
菅首相が「2050年にカーボンニュートラル」(CO2排出実質ゼロ)という目標を打ち出したのを受けて、自動車についても「脱ガソリン車」の流れが強まってきた。政府は年内に「2030年代なかばまでに電動車以外の新車販売禁止」と
-
福島では、未だに故郷を追われた16万人の人々が、不自由と不安のうちに出口の見えない避難生活を強いられている。首都圏では、毎週金曜日に官邸前で再稼働反対のデモが続けられている。そして、原子力規制庁が発足したが、規制委員会委員長は、委員会は再稼働の判断をしないと断言している。それはおかしいのではないか。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間















