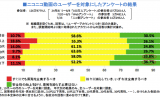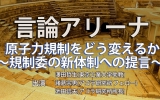豪首相「COP26で石炭は終焉」との主張に猛然と反論
COP26におけるグラスゴー気候合意は石炭発電にとって「死の鐘」となったと英国ボリス・ジョンソン首相は述べたが、これに反論して、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、石炭産業は今後も何十年も事業を続ける、と述べた。

スコット・モリソン オーストラリア首相 Wikipediaより
海外各紙が報じている(SBS (ビデオインタビュー付き), Dailymail、Washingtonpost)
モリソンの発言概要は以下のとおり:
- 2050年までに排出量を完全にゼロにするという目標のためにオーストラリアの農村部や地域の人々に「代償を払わせる」ことはしない。(注:オーストラリアは主に民間の自主的取り組みによって目標を達成するとしている)
- 2030年の排出目標の深堀はしない(注:COP26で採択されたグラスゴー気候協定では、来年エジプトで開催されるCOP27サミットまでに各国が「パリ協定の気温目標と整合的な」2030年の排出削減目標の深堀を検討することになっている。現在のオーストラリアの目標は2005年比で2030年までに30%削減となっている。)
- 低排出ガスの新技術への移行は長い時間をかけて行われるため、石炭部門で雇用されているオーストラリア人は、今後何十年もその業界で働き続けることになる。
- オーストラリアの国益を守るために立ち上がることを謝罪するつもりはない(no apologies)。(注:オーストラリアは、世界第2位の石炭輸出国であり、世界第5位の石炭生産国である。オーストラリアから石炭を購入している主な国は、日本、インド、中国、台湾)。
- 温暖化問題を実際に解決することができるとわかっている技術進歩に焦点を当て、安全保障と経済とのバランスのとれた方法で温暖化対策を行うつもりだ。温暖化対策のためにオーストラリア人に税金を課したり、法律で規制したり、強制したりするつもりはない。
外国の圧力に阿らず毅然として国益を守る。これが本当の政治家だ。日本にはこのような人物はいないのか?
■

関連記事
-
東京都が「カーボンハーフ」を掲げている(次々とカタカナのキャッチフレーズばかり増えるのは困ったものだ)。「2030年までCO2を半減する」という計画だ。ではこれで、いったいどのぐらい気温が下がり、大雨の雨量が減るのか、計
-
はじめに 本稿では「有機物質地下資源」という聞き慣れない言葉を用いる。これは石油、石炭、天然ガス、シェールオイルなど、一般に「化石燃料」と呼ばれるものを指す。筆者が「化石燃料」という言葉を避けるのは、その名称が燃焼用途(
-
「リスクコミュニケーション」という考えが広がっています。これは健康への影響が心配される事柄について、社会で適切に管理していくために、企業や行政、専門家、市民が情報を共有し、相互に意見交換して合意を形成していくことを言います。
-
気候変動を気にしているのはエリートだけだ――英国のアンケート結果を紹介しよう。 調査した会社はIpsos MORIである。 問いは、「英国で今もっとも大事なことは何か?」というもの。コロナ、経済、Brexit、医療に続い
-
(前回:米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発
-
世の中で専門家と思われている人でも、専門以外のことは驚くほど無知だ。特に原子力工学のような高度に専門分化した分野だと、ちょっと自分の分野からずれると「専門バカ」になってしまう。原子力規制委員会も、そういう罠にはまっている
-
バイデン政権で気候変動特使になったジョン・ケリーが米国CBSのインタビューに答えて、先週全米を襲った寒波も地球温暖化のせいだ、と言った。「そんなバカな」という訳で、共和党系ウェブサイトであるブライトバートでバズっている。
-
11月11日~18日にかけてボンのCOP23に行ってきた。パリ協定の詳細ルールは2018年にポーランドのカトヴィツェで開催されるCOP24で合意を目指すことになっている。このため今回のCOPはストックテーキングとの位置づ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間