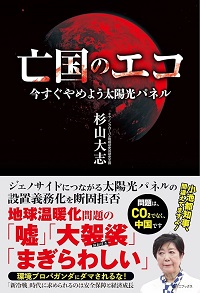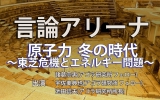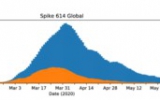石器時代が終わったのは政府が禁止したからではない

shotbydave/iStock
「石器時代は石が無くなったから終わったのではない」
これは1973年の石油ショックの立役者、サウジアラビアのヤマニ石油大臣の言葉だ。
当時、イスラエルとアラブ諸国の間で第四次中東戦争が起きて、サウジアラビアは「石油戦略」を発動、石油を減産した上で、イスラエル支持の国々に対して石油の輸出を禁止した。慌てた日本政府はサウジアラビアを訪問し、輸入の継続をとりつけた。
その後、ザキ・ヤマニ大臣の言葉は、温暖化対策、なかんずく太陽光発電や風力発電の推進者によって引用されてきた。化石燃料も、その枯渇を待つことなく、やがて時代は終わる、という訳だ。
それで世界諸国は、化石燃料利用を規制し、また太陽・風力を巨額の予算によって大量導入してきた。だがその結果はどうかと言えば、世界の化石燃料消費は増え続けているし、CO2排出も減らない。なぜか?
それは、石器が使われなくなった理由は、石器を政府が禁止したからではないからだ。
石器が使われなくなった理由は、それより優れた技術が登場し、石器が必要無くなったからだ。鉄器は、鋤や鍬などの農具の性能を飛躍的に高めた。戦争においても鉄器は石器を圧倒した。
化石燃料時代が終わるとすれば、それは、化石燃料より優れた技術が登場し、化石燃料が不要になったときだ。
残念ながら、太陽・風力は、コストは高く、出力は安定しないので、化石燃料には負ける。
化石燃料を上回るのは何か?
原子力は、発電に関しては化石燃料と互角かそれ以上に戦える。
それから、省エネは、化石燃料を燃やすよりも経済性が高い場合が多い(金ばかりかかる筋ワルの省エネもあるのでそれは注意は必要だが)。エアコンの効率や自動車の燃費などは、石油ショック以降、ずいぶんと向上した。これは化石燃料消費の削減になった。
今後、筆者が期待するのは、この原子力、省エネに加えて、核融合だ。核融合は、いま国際協力でう進めている実験炉ITER(イーター)は2兆円超、それに続く原型炉(実証炉とも呼ばれる)にもやはり2兆円超かかるが、その後、実用化されれば、既存の原子力発電と互角のコストになると期待している。
一方で、化石燃料の最大の敵はこれまで何だったかというと、じつは化石燃料自身だった。
石油ショック後、50年にわたり、石油価格が高くなりすぎることのないよう、サウジアラビアが主導して、OPECはたびたび減産し、価格を調整してきた。高すぎる石油価格は、代替的なエネルギーや省エネの開発を促すのみならず、ライバルである米国産の石油に負けることも意味するからだ。ここのところ、OPECは価格維持のために石油減産をしてきたが、それ以上に米国が石油を増産して空前の生産量となり、OPECの努力を打ち消してしまった。
また近年、G7諸国はCO2削減のためとして石炭火力発電を目の敵にしているが、中国、インドをはじめとして、グローバルサウスは石炭の開発・利用を進めている。もっとも安価で優れたエネルギーだからだ。
イギリス、ドイツ、米国など、欧米では石炭火力発電は軒並み減少してきたが、最大の理由は、天然ガス火力発電に経済性で負けてきたからだ。要は化石燃料の中で代替が起きているだけで、化石燃料が負けた訳では無い。
化石燃料を禁止するのでは、イタチごっこになるだけである。
化石燃料に代わる、安価で安定した優れたエネルギーこそが、化石燃料の時代を終わらせるのだ。
■

関連記事
-
「ポスト福島の原子力」。英国原子力公社の名誉会長のバーバラ・ジャッジ氏から、今年6月に日本原子力産業協会の総会で行った講演について、掲載の許可をいただきました。GEPR編集部はジャッジ氏、ならびに同協会に感謝を申し上げます。
-
【原発再稼動をめぐる政府・与党の情勢】 池田 本日は細田健一衆議院議員に出演いただきました。原発への反感が強く、政治的に難しいエネルギー・原子力問題について、政治家の立場から語っていただきます。経産官僚出身であり、東電の柏崎刈羽原発の地元である新潟2区選出。また電力安定推進議員連盟の事務局次長です。
-
文藝春秋の新春特別号に衆議院議員の河野太郎氏(以下敬称略)が『「小泉脱原発宣言」を断固支持する』との寄稿を行っている。その前半部分はドイツの電力事情に関する説明だ。河野は13年の11月にドイツを訪問し、調査を行ったとあるが、述べられていることは事実関係を大きく歪めたストーリだ。
-
11月15日から22日まで、アゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29(国連気候変動枠組条約締約国会議)に参加してきた。 産業界を代表するミッションの一員として、特に日本鉄鋼産業のGX戦略の課題や日本の取り組みについ
-
昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 気候モデルが過去を再現できないという話は何度
-
きのうの言論アリーナで、諸葛さんと宇佐美さんが期せずして一致したのは、東芝問題の裏には安全保障の問題があるということだ。中国はウェスティングハウス(WH)のライセンス供与を受けてAP1000を数十基建設する予定だが、これ
-
今年7月からはじまる再生可能エネルギーの振興策である買取制度(FIT)が批判を集めています。太陽光などで発電された電気を電力会社に強制的に買い取らせ、それを国民が負担するものです。政府案では、太陽光発電の買取額が1kWh当たり42円と高額で、国民の負担が増加することが懸念されています。
-
東京で7月9日に、新規感染者が224人確認された。まだPCR検査は増えているので、しばらくこれぐらいのペースが続くだろうが、この程度の感染者数の増減は大した問題ではない。100人が200人になっても、次の図のようにアメリ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間