柏崎刈羽原発はなぜ動かないのか:再稼働を止める構造的要因
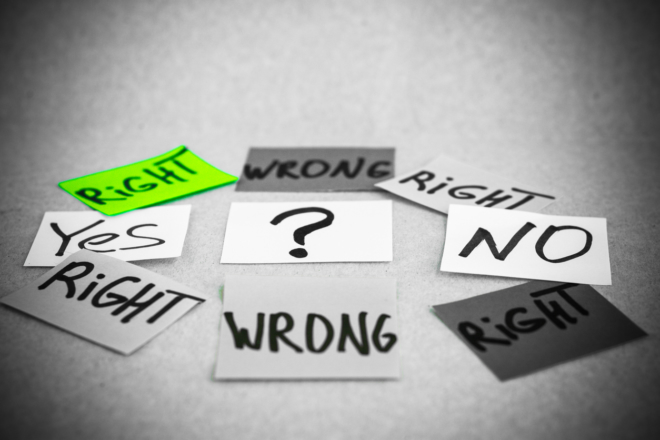
2025年7月2日NHKニュースによると、柏崎市の桜井市長は、柏崎刈羽原子力発電所の7号機の早期の再稼働が難しくなったことを受け、再稼働の条件としている1~5号機の廃炉の方針について、改めて東京電力と協議して小早川社長に説明を求める考えを示しました。
7号機の再稼働と1~5号機の廃炉に何か関係があるのか、疑問に思う人も多いでしょう。実はこの1~5号機の廃炉問題は、2017年までさかのぼる話になります。その前に、柏崎刈羽原子力発電所の各号機の製造年を確認しておきましょう。

表1 柏崎刈羽原子力発電所各号機の運転開始年と稼働年数
廃炉問題は2017年から提起されていた
2017年6月、柏崎市の桜井市長は、東京電力が早期の再稼働を目指している6・7号機について、再稼働から2年以内に1〜5号機の廃炉計画を示すよう要請しました。
柏崎刈羽原子力発電所の再稼働および廃炉に関する基本的な考え方
この要請の背景には、原子力規制委員会が「原発は原則として運転開始から40年までしか認めない」という方針を示していたことがあります。この当時は、関西電力が美浜・高浜原発の運転期間を40年超から60年へ延長することを目指す以前であり、原発の寿命は40年という認識が強く根付いていました。
このような状況で表1を見てみると、仮に6・7号機が2025年頃に再稼働できたとしても、1号機はすでに運転開始から40年を超えており、比較的新しい4号機でさえも運転開始から31年が経過しています。
私が市長の立場であれば、次のように考えるでしょう。
「現在は再稼働のための対策工事が活発に進められており、作業員が大量に柏崎市や刈羽村周辺に滞在している。しかし、再稼働が実現すれば、確かに柏崎市の税収は増加するが、作業員の数は通常の運転・保守に関わる人員だけになり、大幅に減少する。13ヶ月ごとに行われる定期点検では一定数の作業員が入るが、再稼働工事に比べればその数は限られている。柏崎市の活性化を考えるならば、すでに運転開始から40年近く経過している1〜5号機について、いずれ廃炉にするのであれば、今のうちに東電に廃炉の工程を作成させ、工事需要を見込んで作業員の宿泊需要を確保したい。1基の廃炉には30年程度かかるため、5基を順次廃炉にすれば100年以上の長期的な雇用や経済効果が見込める。」
桜井市長が実際にこうした考えを持っていたかどうかは定かではありませんが、少なくとも2017年6月に廃炉の工程作成を東電に要請している事実があります。
それから2ヶ月後の2017年8月、東電は「6・7号機の再稼働後5年以内に、1〜5号機のうち1基以上について廃炉を視野に入れたステップを踏む」と回答しました。明確に「廃炉します」とは言っていないものの、実質的には廃炉に向けた準備を進める意向をにじませる回答でした。
ただし、「1基以上」として具体的な基数や対象機種には言及せず、あいまいなままに留めました。東電としては、再稼働の同意を得るために、最も古い1基程度の廃炉であれば容認できると判断したのでしょう。
実際、最も古い1号機は東北電力との共同開発によるもので、発電された電力のうち500MWは東北電力に供給され、東電が利用できるのは残りの500MWに限られます。そのため、東電としては「1号機だけ廃炉にして、他の号機は運転延長の対策を講じればよい」と考えていたのかもしれません。
柏崎市長も、この東電の回答は同社の立場を踏まえた「ギリギリの譲歩」と受け取り、再稼働容認の方向へと動きました。ただし、実際に再稼働を進めるには、新潟県議会の同意も必要です。
世の中はどんどん変わっている、東電の再稼動だけが停滞したまま
柏崎刈羽原発の再稼働が遅々として進まない一方で、関西電力では美浜3号機や高浜1・2号機が、40年を超える運転について原子力規制委員会から許可を得ており、60年の運転期間に入っています。さらに、高浜3・4号機についても、同様に40年超の運転が認められ、運転延長に向けての準備が進んでいます。
一方で柏崎刈羽原発は、2017年から2025年にかけての8年間において、再稼働に関して目立った進展が見られたとは言いがたい状況です。
そうした中、今回、東京電力は「7号機はテロ対策施設の完成が間に合わないため一旦見送り、先に6号機を再稼働させる。7号機の再稼働は、施設が完成する約4年後になる。1〜5号機の扱いについては、7号機の再稼働後に検討する」との方針を示しました。
このような説明では、柏崎市長としても納得できるはずがありません。なお、6号機についてもテロ対策施設の設置期限が2029年9月に定められており、それまでに完成しなければ運転を継続できません。
もちろん、テロ対策施設が本当に必要かどうかについて、私自身は疑問を感じるところもあります。しかし、現行のルールのもとでは、施設を完成させなければ再稼働は認められません。このような東電の消極的な姿勢に対して、柏崎市長が不満や不信を表明するのも当然のことです。
さらに柏崎市長は、2025年1月の新潟県議会において、地元の再稼働同意を得やすくするために、「地元への安価な電力供給を実現してほしい」との要請も行いました。
しかし、これに対しても東京電力からは今のところ一切の提案がなく、まるで無視されているかのような対応が続いています。
再稼働反対の世論作りで、地元メディアは何を目指しているのか
2025年7月3日の「みんかぶマガジン」では、『「もはやプロパガンダ」新潟日報、原発反対報道を元経済誌編集長が批判』という記事が掲載されました。
確かに東京電力の対応には数々の問題があるものの、この記事で私が共感したのは以下の指摘です。
「地元の新聞である新潟日報は一見中立を装いながら、些細な事象を大げさに報じ、不安を煽る報道姿勢などによって、巧妙に世論を反原発へと誘導する姿勢が見られる。このことは原発だけではなく、地元の他の大手企業にも、同様に厳しい報道姿勢で臨むことで知られているという。地元の大手企業や原子力発電所は、地域経済の基盤であり、多くの雇用と税収を生んでいるが、その企業を地元メディアが叩き続ければ、新たな企業進出はおろか、既存の企業さえも県外へ逃げ出しかねない。その先に何があるのかといえば、企業活動が停滞し、国からの補助金に頼らなければ立ち行かなくなるような、新潟県を作ろうとしているのだろうか?」
実際、新潟県の財政状況は厳しく、2022年度の「実質公債費比率(県収入に占める借金返済の割合)」は18.2%に達し、国の許可なしに県債を発行できない「起債許可団体」に転落しました。都道府県でこの指定を受けているのは、全国で新潟県と北海道のみです。
一方、新潟県は東日本全体のエネルギー供給を担う重要拠点であり、東新潟火力発電所と柏崎刈羽原子力発電所を抱える県です。しかし、その原子力発電所を有効活用しようとする東京電力の積極的な姿勢は見えず、地元メディアは再稼働反対の世論形成に熱心。これでは、日本全体の電力価格は今後も上昇し、新潟県は自らが持つ「経済的資産」を活かせないまま、ますます財政的に追い詰められていくでしょう。
今や、柏崎市の経済は「廃炉作業員が地域に落とすお金」に頼るしかなくなりつつあります。しかし、こうした負のスパイラルは、本来であれば逆回転させることも可能なはずです。
原子力という強力な資産を、雇用・投資・電力価格の安定といった経済成長の起点に再転化できるかどうか――それは、企業だけでなく、政治・メディア・住民が冷静な現実認識を持てるかにかかっています。

関連記事
-
前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE
-
オーストラリア戦略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)の報告「重要技術競争をリードするのは誰か(Who is leading the critical te
-
前回の記事で、①EUが実施しようとしている国境炭素税(CBAM)は、世界を敵に回す暴挙で、世界諸国によって潰されることになる、②このCBAMへの対応を理由に日本は排出量取引制度法案を今国会で審議しているが、経済自滅を招く
-
おかしなことが、日本で進行している。福島原発事故では、放射能が原因で健康被害はこれまで確認されていないし、これからもないだろう。それなのに過剰な放射線防護対策が続いているのだ。
-
7月21日、政府の基本政策分科会に次期エネルギー基本計画の素案が提示された。そこで示された2030年のエネルギーミックスでは、驚いたことに太陽光、風力などの再エネの比率が36~38%と、現行(19年実績)の18%からほぼ
-
昨年の地球の平均気温は、観測史上最高だった。これについて「その原因は気候変動だ」という話がマスコミには多い。 気候変動の話をすると、「地球の歴史からするとこの程度は昔もあった」というコメントがつくのだが、現生人類も文明も
-
GEPR編集部より。このサイトでは、メディアのエネルギー・放射能報道について、これまで紹介をしてきました。今回は、エネルギーフォーラム9月号に掲載された、科学ジャーナリストの中村政雄氏のまとめと解説を紹介します。転載を許諾いただきました中村政雄様、エネルギーフォーラム様に感謝を申し上げます。
-
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで3回にわたって、筆者は日本の水素政策を散々にこき下ろしてきたが、日本政府はまだ全然懲りていないようだ。 「水素に賭ける日本、エネルギー市場に革命も」と言う驚くべき記事が
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間















