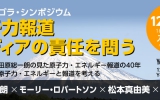再エネ利用で、成長をつかめ・村上新エネ対策課長【再エネ・(下)】
村上敬亮資源エネルギー庁新エネルギー対策課長に、FITの成果と問題点について聞いた。
— 高い買取価格とグリーン投資減税は、今後どうなりますか。
調達価格等算定委員会での審議を経て、太陽光の価格は実態に合わせて引き下げ、また、減税措置も別途縮小の方向になるでしょう。
ただしヨーロッパの失敗から学ばなければなりません。2009年の急激な買取価格の引き下げで、ドイツでは、Qセルズなど国内メーカーの倒産を引き起こす一方、逆に安価な中国製パネルが大量流入し、買取負担が逆に増えてしまう事態をもたらしました。
乗り越えるポイントの一つは、事業者のマーケット・リテラシー(能力、習熟度)を高めることにあると思います。関連の情報、知恵の体系化と集積を東大と進め、ビジネスに役立つ知識を、どのように伝えるかの研究をしています。これを提供する予定です。
— 悪質な事業者の参入が懸念されています。
FITでは金融面に配慮し、認定を早い段階で行う制度としました。それは意図通りに成功した半面、手抜き工事や認定だけ取得して着工にとりかからない業者の例が報告されており、私たちも問題と考えています。今実態の調査を進めていますが、認定時の価格を維持する必要が無いと思われる場合は、認定の取り消しを行います。
— 電力系統作り替えをはじめ、国民負担が増えませんか。
電力系統の強化は、再エネ普及の両輪です。電力が双方向で流れるための逆潮流の規制緩和と料金メニュー化など、電力系統整備の制度を整えました。
目先に問題となるのは北海道電力管内の接続です。地域内の系統強化の支援を進めていますが、抜本的な解決策としては、津軽海峡を横断し本州と北海道をつなぐ連系線の強化が必要です。広域連系のあり方を決める電力システム改革論議次第ですが、強化の方向に進めて行きたいと考えています。
再エネ増加は、国民の支持を得た時代の流れ。今後は、開発には時間がかかるけれども太陽光より相対的に安価な風力や地熱発電を伸ばさなくてはいけません。それに応じた系統整備も電力各社では必要になるでしょう。地域経済と密着した中小水力やバイオマス発でなども着実に動き始めています。
— 電力業界は、FITとどのように向き合うべきでしょうか。
少子高齢化の中で電力需要は減り、電力ビジネス環境はますます厳しくなります。この分野では、再エネは消費者に歓迎され、成長可能性がある数少ない商品でしょう。「グリーンエネルギー」というブランドは、さまざまな業種が活用を望むはずです。
FITは国民の皆さんのご支援を基に、グリーンという新たなエネルギービジネスの投資に確実な投資回収可能性を与える仕組みです。再エネの量的拡大はもとより、エネルギーから取り組む地域経済や地銀・信金等地域金融の活性化、蓄電池などと組み合わせ電力の自給自足を目指したオフグリッドなど、様々な取り組みや技術を後半にサポートします。これを上手に活用することが大切かは、電力業界の方も、十分認識なさっているでしょう。
電力会社や関連会社の能力は、人材も、技術も本当にすばらしい。ただし現在の電力供給体制と事業体制の中で、その潜在力がマーケットに適正に評価されていないと感じています。徹底的な電力自由化の推進と、市場原理を補う固定価格買取制度などの仕組みの効果的な組み合わせは、電力産業自体を成長産業に復活させるポテンシャルを持っています。電力会社の皆さんは、この好機を必ず活用されると期待しています。
— 再生可能エネルギーをめぐる状況は変わりました。変化をどのように考えますか。
FITの導入で数多くの前向きな変化が生まれました。その一つは、新しいプレイヤーがエネルギー事業に参入したことです。これは電力市場に新たな競争をもたらし、さまざまな他産業との融合をもたらします。
また行政から見れば、エネルギーと地域活性化など、エネルギーについて新しい視点から国民の皆さんとの関係を築けました。
そして太陽光だけではなく、地熱、風力などが今後拡大していくでしょう。エネルギー政策は10年単位で考えるべき。そうした中で、最初の1年半で社会に新しい流れを作れたことはうれしいし、それが大きなうねりになることを期待します。
(むらかみ・けいすけ)90年通商産業省(現経済産業省)入省。担当は、95年から約10年間IT政策を担当。他にエネルギー、ソフトパワー戦略、地球温暖化対策の国際条約交渉などを担当。2011年9月から現職。
(取材・構成 石井孝明(経済ジャーナリスト))
(2013年3月24日掲載)

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
経営再建中の東芝は、イギリスで計画中の原子力発電所の受注を目指して、3年前に買収したイギリスの企業をめぐり、共同で出資しているフランスの企業が保有する、すべての株式を事前の取り決めに基づいて買い取ると発表し、現在、目指している海外の原子力事業からの撤退に影響を与えそうです。
-
アゴラ研究所は12月8日にシンポジウムを開催します。出演は田原総一朗さん(ジャーナリスト)、モーリー・ロバートソンさん(ジャーナリスト)、松本真由美さん(東京大学客員准教授)が参加します。静岡県掛川市で。ぜひご参加ください。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
浜野喜史参議院議員(民主党)は、原子力規制委員会による規制行政、また日本原電敦賀2号機の破砕帯をめぐる問題を国会で10回以上、質問で取り上げている。規制行政への意見を聞いた。
-
6月17日記事。国民投票前の記事ですが、仮に離脱の場合にはエネルギーセクターが、大変な悪影響を受けるという見通しを示している。
-
日経新聞1月10日記事。同原発は加圧水型軽水炉(PWR)で、現在稼働中の2基は1974年と76年に運転を開始した。最大出力の合計は200万キロワットで、ニューヨーク市と近郊のウエストチェスター郡で消費される電力の約4分の1に相当する。
-
2014年3月のロシアによるクリミア編入はEUに大きな衝撃を与えた。これはロシア・ウクライナ間の緊張関係を高め、更にEUとロシアの関係悪化を招いた。ウクライナ問題はそれ自体、欧州のみならず世界の政治、外交、経済に様々な影響を与えているが、EUのエネルギー政策担当者の頭にすぐ浮かんだのが2006年、2009年のロシア・ウクライナガス紛争であった。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間