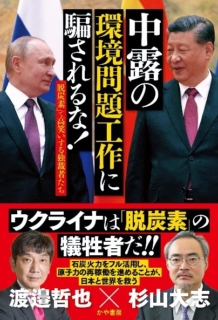欧州エネルギー暴騰で肥料工場の生産が7割も激減

igorartmd/iStock
前回、非鉄金属産業の苦境について書いたが、今回は肥料産業について。
欧州ではエネルギー価格の暴騰で、窒素肥料の生産が7割も激減して3割になった。
過去、世界中で作物の生産性は上がり続けてきた。これはひとえに技術進歩のお陰だが、とくに窒素肥料の効果は大きかった。
窒素肥料は、大気中に豊富に存在する窒素から、高温・高圧の化学反応プロセスを経てアンモニアを合成するという「ハーバー・ボッシュ法」によってもたらされた。
20世紀初頭のドイツ化学産業は世界一だった。その歴史の中でも燦然と輝く偉業がこの窒素肥料合成であった。
この技術の恩恵で、その後世界人口は大幅に増加したにも関わらず、今日に至るまで人々の栄養状態は劇的に改善してきた。
さてこの窒素肥料製造の工程には大量の天然ガス(ないしは国によっては石炭)を使用する。
欧州、特にドイツでは、従前はロシアのパイプラインによる安価な天然ガスを利用して窒素肥料を生産してきた。
だがいま、EUの天然ガス価格は、2年前の15倍にもなった。これは米国の10倍の価格である。
これでは全く国際競争力が無いため、欧州の窒素肥料工場は停止し、生産が激減した訳だ。
欧州肥料協会(Fertilizers Europe)は、欧州機関とEU加盟国に対し、この肥料産業の危機を回避するために早急に救済措置を取るよう要請している。
そして問題は欧州に止まらない。世界全体で肥料供給が不足し、国際価格が暴騰している。
理由のひとつは欧州の工場停止で、欧州は肥料の純輸入国になりつつある。これに加えて、ロシアのウクライナ侵攻によって、ロシア・ウクライナ両国からの肥料輸出も滞っている。
世界市場での肥料価格の暴騰の影響を日本も受けている。JA全農は6~10月の肥料価格を大幅に引き上げた。
だがもっとも煽りを受けるのは、貧しい国々になりそうだ。
国際肥料協会によれば、アフリカの何百万人もの人々がすでに飢餓に直面している。そのような状況において、来シーズンの世界の肥料供給は7%減と予測されている。
貧しい人々にとって、高い肥料を買うことの経済的負担は大きい。のみならず、もし買い負けて肥料が手に入らなければ、作物も育たず、食料が確保できなくなる。
欧州の窒素肥料産業は、政府の救済によって企業体としては生き長らえたとしても、ロシアからの安い天然ガスはもはや供給されない。
操業を続けたければ、少なくとも今後数年は、高騰した液化天然ガスを輸入して肥料生産をすることになるが、ガスも電力も価格が暴騰し供給が不足している欧州で、果たしてそのような判断になるだろうか。
すると欧州の窒素肥料工場の操業停止はしばらく続くのではないか。
その後も、欧州の産業は高いエネルギーコストに直面することになる。脱炭素政策も追い打ちをかける。窒素肥料産業は、発祥の地である欧州から無くなってしまうのかもしれない。
■

関連記事
-
先日、フロリダ州がCDPとSBTiを気候カルテルに指定し調査を開始した件を紹介しました。 フロリダ州がCDPとSBTiを気候カルテルと指摘し召喚 ジェームズ・ウスマイヤー司法長官は本日、CDP(旧カーボンディスクロージャ
-
IAEA(国際原子力機関)の策定する安全基準の一つに「政府、法律および規制の安全に対する枠組み」という文書がある。タイトルからもわかるように、国の安全規制の在り方を決める重要文書で、「GSR Part1」という略称で呼ばれることもある。
-
英国気象庁の気温測定局のほぼ3つに1つ(29.2%)は、国際的に定義された誤差が最大5℃もある。また、380の観測所のうち48.7%は最大2℃も誤差がある。NGOデイリースケプティックのクリス・モリソンが報告している。
-
昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。今回から、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読んでいこう。 まず今回は「政策
-
1. 東日本大震災後BWR初の原発再稼動 2024年10月29日東北電力女川原子力発電所2号機が再稼動しました。東日本大震災で停止した後13年半ぶりで、東京電力福島第一と同じ沸騰水型(BWR)としては初の再稼動になります
-
多くのテレビ、新聞、雑誌が事故後、放射能の影響について大量に報道してきた。しかし伝えた恐怖の割に、放射能による死者はゼロ。これほどの報道の必要があるとは思えない。
-
私は太陽光発電が好きだ。 もともと自然が大好きであり、昨年末まで勤めた東京電力でも長く尾瀬の保護活動に取り組んでいたこともあるだろう。太陽の恵みでエネルギーをまかなうことに憧れを持っていた。いわゆる「太陽信仰」だ。 そのため、一昨年自宅を新築した際には、迷うことなく太陽光発電を導入した。初期投資額の大きさ(工事費込み304万円)には少々尻込みしたが、東京都と区から合わせて約100万円の補助金を受けられると聞いたこと、そして何より「環境に良い」と思って決断した。正確に言えば、思考停止してしまった。
-
エリートが勝手に決めた「脱炭素」目標の実現のための負担が明らかになるにつれて、庶民の不満が噴出しつつある。 警鐘を鳴らすのはイギリスの右寄りタブロイド紙Daily Mailである(記事、記事)(イギリスの新聞事情について
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間