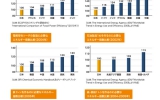処理水問題の10年で日本が失ったもの
処理水の放出は、いろいろな意味で福島第一原発の事故処理の一つの区切りだった。それは廃炉という大事業の第1段階にすぎないが、そこで10年も空費したことは、今後の廃炉作業の見通しに大きな影響を与える。
本丸は「デブリの取り出し」
廃炉の最大の難関は水処理ではなく、格納容器の底にたまった核燃料のデブリの取り出しである。まだ原子炉の中には入れないので、今年1月に水中ロボットによる内部調査が再開され、デブリを1gぐらい採取したというが、燃料とその周辺の廃棄物は全体で880トンある。

ロボットアームで持ち上げたデブリ(東電撮影)
事故から12年たってこの状況では、東電の「30年で廃炉を完了する」という目標が達成できる見込みはない。今の調子でやっていると100年以上かかり、そのコストは数十兆円になるだろう。
取り出したデブリは危険な高レベル放射性廃棄物だが、置き場所も決まっていない。そもそも何のために取り出すのかという目的がわからない。
技術的には、発電所の中に閉じ込めたまま蓋をするチェルノブイリのような石棺方式(閉じ込めシェルター)で十分だ。しばらくは冷却水を循環させる必要があり、モニタリングも必要だが、デブリの状態は安定しており、取り出しよりはるかに安全である。

チェルノブイリ原発の石棺(WSJ)
シェルターのコストはチェルノブイリでは3000億円程度だったが、福島は3基あるので、1兆円ぐらいかかるだろう。それでも今の廃炉費用8兆円よりはるかに安い。難点は大量の冷却水が出ることだが、これは海洋放出で解決する。
「お気持ち」のために何十兆円もかけてデブリを取り出すのか
ではなぜわざわざ高いコストをかけて取り出すのか。その理由は「事故の残骸が地元にあるのはいやだから、デブリを取り出して撤去してほしい」という地元のお気持ちである。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、2016年の技術戦略プランで石棺方式に言及した(現在は修正ずみ)。当初は地元も暗黙のうちに了解していたが、マスコミが騒ぎ始め、福島県の内堀知事が経済産業省に乗り込んで抗議した。
その結果、支援機構の山名理事長は「引き続きデブリの取り出しをめざす」と釈明し、シェルターはタブーになってしまった。知事の抗議は、政治的スタンドプレーだった。デブリを取り出しても原発の跡地に住民は住めないので、撤去する意味はない。
関係者の誰に聞いても「取り出すのは無理だが、今は努力するしかない」という。これは処理水と同じである。もともと薄めて流すしかない水をALPSで除去する努力をし、「あらゆる手を尽くしたができなかった」といわないと、地元が納得しないのだ。
日本経済の「エネルギー敗戦」
1970年代にも、エネルギー危機があった。石油ショックで日本経済は大きな打撃を受けたが、通産省は石油に依存している日本経済の脆弱性を自覚し、原子力開発に舵を切った。他方で日本の自動車は低燃費だったので、世界に爆発的に売れるようになり、80年代には日本の製造業が世界を制覇すると恐れられるようになった。
しかし1990年代に不動産バブルが崩壊したあと、その処理を先送りしているうちに日本経済は体力を消耗し、企業の貯蓄が投資を上回る異常事態になった。これが「失われた10年」だったが、その次の10年には回復が始まった。
それは当時、世界市場に参入した中国を生産拠点にするグローバル化だった。2008年からの世界金融危機で、これは一挙に加速した。特に電気・機械などの主要産業がアジアに生産拠点を移し、連結ベースで経常利益を発表するようになってから、目に見えて業績が回復したが、国内投資は減り、賃金は下がった。
このような産業空洞化を促進したのが、エネルギー政策の失敗である。そのきっかけは福島事故であり、その責任はもちろん東電にあるが、事故が民主党政権で起こったのは不幸な偶然だった。
エネルギー政策の失敗が産業空洞化を促進した
福島事故は「メルトダウン」ではなく、炉心が過熱したために水蒸気が外部に放出されただけで、周辺の住民が数日、家の中にいればすむ程度の事故だった。のちに国連科学委員会も検証したように、死者はゼロだった。
しかし当時すでに支持を失っていた菅直人首相は、原発事故を政治利用し、その被害を最大限に誇張し、全国の原発を違法な行政指導で止めてしまった。同時に再エネFITで40兆円も「課税」し、電力自由化を強行した。
その結果、電力供給は不安定化し、電気代は上がり、製造業は日本から脱出して空洞化が加速した。かつてエネルギー危機を梃子にして世界にのし上がった日本が、エネルギー政策の失敗で衰退を加速したのだ。
「過剰なコンセンサス」が日本を滅ぼす
かつての戦争から処理水に至るまで、敗戦がわかっていても、あらゆる手を尽くして「降伏するしかない」と国民が納得するまで方向転換できない。この過剰なコンセンサスが、日本の衰退の最大の原因である。
福島の廃炉費用は当初の想定をはるかに超え、デブリ取り出し作業が行き詰まることは確実だ。これを強行すると、東電が40年かけて営業利益から廃炉費用22兆円を返済するという机上プランも成り立たなくなる。
これも答はわかっている。シェルター方式に切り替えるしかない。処理水問題の決着を機に、デブリ問題をまじめに検討すべきだ。このままでは廃炉費用も22兆円をはるかに超え、民間企業としての東電には負担できない。
今まですでに支援機構を通じて国費が投入されているが、今後は東電の原子力部門を国有化し、国の責任で事故処理を完了する必要がある。それぐらいの外科手術をしないと、日本経済は建て直せない。

関連記事
-
ドイツ・憲法裁判所の衝撃判決 11月15日、憲法裁判所(最高裁に相当)の第2法廷で、ドーリス・ケーニヒ裁判長は判決文を読み上げた。それによれば、2021年の2度目の補正予算は違法であり、「そのため、『気候とトランスフォー
-
国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%
-
去る7月23日、我が国からも小泉環境大臣(当時)他が参加してイタリアのナポリでG20のエネルギー・気候大臣会合が開催された。その共同声明のとりまとめにあたっては、会期中に参加各国の合意が取り付けられず、異例の2日遅れとな
-
2024年3月18日付環境省報道発表によれば、経済産業省・環境省・農林水産省が運営するJ-クレジット制度において、クレジットの情報を管理する登録簿システムやホームページの情報に一部誤りがあったそうです。 J-クレジット制
-
エネルギー政策について、原発事故以来、「原発を続ける、やめる」という単純な話が、政治家、民間の議論で語られる。しかし発電の一手段である原発の是非は、膨大にあるエネルギーの論点の一つにすぎない。
-
トランプ大統領は1月20日に就任するや、国内面では石油、ガス、鉱物資源の国内生産の拡大を図り、インフレ抑制法(IRA)に基づくクリーンエネルギー支援を停止・縮小し、対外面では米国産エネルギーの輸出拡大によるエネルギードミ
-
ウイグルを含むテュルク系民族の母なる大地であった「東トルキスタン」は18世紀、戦いに敗れ、清朝の版図に入った。その後、紆余曲折を経てこの領土は中華人民共和国に受け継がれることとなり、1955年に「新疆ウイグル自治区」が設
-
福島原発事故の後で、日本ではエネルギーと原子力をめぐる感情的な議論が続き、何も決まらず先に進まない混乱状態に陥っている。米国の名門カリフォルニア大学バークレー校の物理学教授であるリチャード・ムラー博士が来日し、12月12日に東京で高校生と一般聴衆を前に講演と授業を行った。海外の一流の知性は日本のエネルギー事情をどのように見ているのか。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間