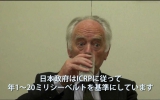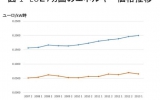海外の論調から「ドイツの風力発電による負荷で、東欧諸国が停電の危機」 — 米通信社報道

風力発電の風車(東京電力提供)
「ドイツが余剰電力を望まない隣国に垂れ流し、今年の冬には反目が一層深まるであろう」「東欧が停電の危機にある」。米系経済通信社のブルームバーグが、ドイツの風力発電の拡大で近隣諸国が悪影響を受けている状況を10月26日に伝えた。記事は「ドイツの風力発電による負荷で、東欧諸国が停電の危機」(Windmills Overload East Europe’s Grid Risking Blackout)。
再生可能エネルギーの中で発電コストが比較的低い風力は脱原発の世界各国でその成長が期待されている。脱原発の手段としてこの種のエネルギーシフトを進める日本では特にそうだ。しかし風力が全発電量に占める割合が8%(2011年)を占めるドイツで顕在化した問題は、今後の日本に参考となるだろう。
東欧と独の送電が結びつき、電力が過剰に流れる
「ドイツは問題があることを認識している。しかし問題の解決には多額のコストが掛かるため、ドイツ政府は解決の政治的意図を持っていない」、「したがって私たちは事故やシステム崩壊を避けるために一方的な防護措置を取ることを余儀なくされている」。記事でチェコ通商産業省の幹部は語った。冬場は欧州では風が強まるが、チェコなどの東欧諸国は、一時的な電力網の切断を検討しているという。
電気は大量に貯めることができないため、発電量と使用量が均衡することが必要だ。需給ギャップを放置すると、大規模停電などの弊害が起こる。しかし、自然任せの風力では、発電分が即座に送電網に流れてしまう。しかもドイツは再生可能エネルギーの買取制度を導入している。発電事業者は電気を売ろうとし、国も負担を避けるために海外への売電を進めている。その方法が、コストが一番安くなるためだ。
現時点で、世界にある発電用風車は20万基以上、建設費は海上を含めて時価総計4600億ドル(37兆円)と推計される。記事によれば、ドイツの送電システムを再生可能エネルギー対応のために、容量と技術の拡張・改善すると、320億ユーロ(3兆2000億円)のコストが掛かると今年5月にドイツの4大送電会社が試算した。
ドイツの風力発電所はバルト海沿岸の北部に偏在。そこと西部と南部の工業地帯の送電網は未整備だ。扱えない分が出てくると、その電力は送電網のつながるチェコやポーランドに流れ込んでくる。今年2月にバルト海で強い風が吹いた時にはドイツの送電網が崩壊寸前となり、チェコとポーランドは自国の送電網を一時的に切り離した。
脱原発政策も影響−「ドイツ人は『ただ飯』を食べている」チェコ人
さらに記事は、2022年までに原発を止めるというドイツ政府の政策が、「問題をさらに悪化させている」と指摘。問題があっても風力発電に頼らざるを得ないためだ。
記事によれば、ドイツの送電会社の担当者は「チェコとポーランドの運営者が市場とシステムの安全問題を心配していることを十分理解している。私たちは前向きの解決方法を追及している」と述べた。しかし、この発言と異なり、ポーランドとチェコの電力、送電会社は批判を強める。
記事によれば、ポーランドの電力会社の幹部は次のように語っている。「私たちが取っている対処方法は高いコストに付くものであり、時に十分でない場合もある」「発電所のスケジュールをこちらが調整しなければならない」。
またチェコの電力会社幹部は述べる。「ドイツ人は私たちのインフラを過剰に利用している。現時点で言えば、彼らはただ飯(めし)を食べている」。また、ドイツの電力が不足した場合に、先に同国と共通電力市場をつくったオーストリアの電力が買われて、チェコの電力が閉め出されてという。「私たちの国の送電網を利用しているのに、こちらの電力は必要とされない。誰が金を払ってくれるのだろうか。これこそ差別だ」とこのチェコ人幹部は述べていた。
日本への教訓−−風力増加のコストとリスクの検証を
日本では民主党政権が9月にまとめた「革新的・エネルギー環境戦略」で、再生可能エネルギーの全発電量に占める割合を、現在の5%(水力含む)から、30年までに30%まで増やす目標を掲げた。しかし、その文章では、再生可能エネルギーの拡大によるデメリットが書かれていない。
日本は孤立した島国であるために、欧州のように電力網で各国が結びつかず、そこで国益がぶつかり合う状況にはなっていない。しかし各地域での独占状態にある電力会社間での送電網は十分な容量を持って結びついていない。
日本で風力発電の適地は、北海道北部と東北太平洋岸に偏在している。ここと大消費地の関東圏と結びつける電力網整備の議論が放置されたまま、この地域での風力発電の振興が計画されている。一例だが、津軽海峡を挟んだ北海道と東北を結ぶ送電線を整備するだけで最低で約3000億円の工事費が必要とされている。
再生可能エネルギーのメリット、そして良いイメージだけに注目してはならない。欧州で起こっている問題を精査して、日本に教訓を取り入れることが必要ではないだろうか。
(アゴラ研究所フェロー・石井孝明)
(2012年10月29日掲載)

関連記事
-
石川・認可法人には第三者による運営委員会を設けます。電力会社の拠出金額を決めるなど重要な意思決定に関与する。ほかの認可法人を見ると、そういった委員会の委員には弁護士や公認会計士が就くことが多い。しかし、再処理事業を実施する認可法人では、核燃料サイクルの意義に理解があり、かつ客観的に事業を評価できる人が入るべきだと思います。
-
この論文は農業の技術的な提言に加えて、日本の現状を分析しています。
-
事故を起こした東京電力の福島第一原子力発電所を含めて、原子炉の廃炉技術の情報を集積・研究する「国際廃炉研究開発機構」(理事長・山名元京大教授、東京、略称IRID)(設立資料)は9月月27日までの4日間、海外の専門家らによる福島原発事故対策の検証を行った。(紹介記事「「汚染水、環境への影響は小さい」― 福島事故で世界の専門家ら」)
-
アゴラ研究所の行うシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」の出演者が、GEPRに寄稿した文章を紹介します。
-
田原・原子力船むつというプロジェクトがあった。それが1974年の初航海の時に放射線がもれて大騒ぎになった。私はテレビ東京の社員で取材をした。反対派の集会に行くと放射線が漏れたことで、「危険な船であり事故が起これば、日本が終わる」と主張していた。
-
問・信頼性を確保するためにどうしましたか。 クルード博士・委員会には多様な考えの人を入れ、議論の過程を公開し、多様な見解をリポートに反映させようとしました。
-
雑誌「プレジデント」の4月14日号に、「地球温暖化か、貧困か」とのサブタイトルで「 雑誌「プレジデント」の4月14日号に、「地球温暖化か、貧困か」とのサブタイトルで「注目のキーワード‐エネルギー貧困率」についての私のコメントが掲載された。記事の一部が分かり難いので、少し詳しく説明したい。
-
私は太陽光発電が好きだ。 もともと自然が大好きであり、昨年末まで勤めた東京電力でも長く尾瀬の保護活動に取り組んでいたこともあるだろう。太陽の恵みでエネルギーをまかなうことに憧れを持っていた。いわゆる「太陽信仰」だ。 そのため、一昨年自宅を新築した際には、迷うことなく太陽光発電を導入した。初期投資額の大きさ(工事費込み304万円)には少々尻込みしたが、東京都と区から合わせて約100万円の補助金を受けられると聞いたこと、そして何より「環境に良い」と思って決断した。正確に言えば、思考停止してしまった。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間