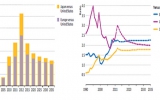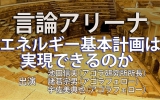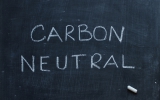シェール革命、可能性とリスクにどう向き合うか【エネ庁部長インタビュー】

住田孝之
資源エネルギー庁 資源・燃料部長
世界の天然ガス情勢に大きな影響を及ぼしている北米のシェールガス革命。この動きを、経産省・資源エネルギー庁はどのように分析し、その変化を日本にどう取り込もうとしているのか。
同庁の資源エネルギー部長の住田孝之氏にインタビューを行った。住田氏は変化への強い期待を述べる一方、日本のエネルギー企業が向き合うことに警鐘を鳴らした。
なお、このインタビューは、エネルギーフォーラム2014年12月号に掲載された。許諾をいただいた住田氏、ならびに同誌編集部に感謝を申し上げる。またこのインタビューは11月中旬に行われたため、12月から始まった石油の暴落と、ロシアと新興国の通貨の下落については、言及していない。
(以下本文)
ポジティブに受け止めるべきシェールガス革命
―北米から始まったシェールガス革命を、エネ庁はどう受け止めていますか。
住田 もちろんポジティブに見ています。3つの点で世界のエネルギー事情に良い影響を与えつつあります。まず世界的な増産は、天然ガスの値段の抑制と供給安定性の向上に役立つ。実際に、米国でのシェールガスの増産が価格抑制、ガス産出国の行動に変化を与えています。
2つ目は供給先の多様化です。化石燃料資源は、旧共産圏、中東など地政学的リスクを持つ地域の産出が多かった。政治的に安定した米国がガス供給国になれば、世界のエネルギーセキュリティーに大変プラスになります。
3つめは、価格安定化の効果です。シェールの場合はシェール層に水や薬液を注入し必要な分だけ採掘する形です。生産調整がこれまでのオイルやガスと比べて小刻みに行われる。その結果、価格の乱高下が抑制されやすくなることが期待されます。
―日本にも好影響を与えそうですか。
住田 楽観視するわけではないですが、シェールガス革命は日本にもさまざまな良い影響をもたらすと思います。今の日本での電源構成を見ると、火力発電が9割、全体の半分以上がLNG火力です。これは異常な状態といえます。単一の資源に発電が依存しリスクが高まっているのです。
日本のLNG調達価格は、現在のところ世界で一番高い。大半が中東産原油とリンクして値決めされ、売り手がなかなかそれを変えません。しかし、北米産のシェールガスは、米国のガス取引指標のヘンリー・ハブで価格が決まります。日本までの輸送コストを考えてもこれまでの価格に比べて、2~3割安いのではないかと思います。
日本の天然ガスはほぼ100%海外に依存し、中東から約30%、そして有事の場合に封鎖の可能性があるホルムズ海峡を約25%が通過しています。外交、経済の両面で安定的かつ緊密な関係を持つ米国からの、安いガスの輸入は、厳しい状況にある日本のエネルギー事情を少しなりとも変えることになるでしょう。
―経産省はシェールガス開発に、どのような支援を行う予定ですか。
住田 JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)では、ガス開発支援で13年度に510億円の予算を設け、上流部分でのガス田買い取りなどの支援を行っています。その内訳でシェール開発の支援に振り向ける量は増えています。この金額は、日本の厳しい財政状況を考えればかなり大きいと思います。一方、世界のエネルギー開発ではビリオン(10億)ドル単位の大規模投資がたくさんあります。その比較で考えれば決して巨額ではありません。
米国の場合、エネルギー資源の輸出には一つ一つの政府の承認が必要です。関係する日本企業と連携を取りながら、認可が取りやすくなるように、米政府への働きかけを行っていきます。関係者の努力により、日本企業がかかわる米国のガス開発プロジェクトは最速のもので2016年からの日本への輸出が開始される見込みと報告を受けています。
―シェール革命を利用したビジネスの環境づくりで、何か支援策はありますか。
住田 エネ庁は、電気料金の値上げ申請時に、価格の算定で「トップランナー方式」を昨年から導入しました。簡単に言えば、調達可能な一番安い価格をベースに算出した上で、値上げを認める仕組みです。省エネの政策を参考にしたものです。
これは従来以上に、電力・ガス会社の価格引き下げ努力を促しています。シェールガスの調達が本格化すれば、この仕組みの下でそれがLNG調達価格のひとつの指標になっていきます。
経済産業省では、LNG産出国・消費国の関係者を一堂に集める産消会議を毎年開催し、認識を共有し意見交換を行っています。今年11月6日に開かれた3回目の今年のテーマは「シェール革命が太平洋を越える」で、参加者の変化への期待は高かったです。
産ガス国の大臣らが日本企業の価格引き下げの姿勢が強く「手強い」交渉をしていると、メディアに述べていたのが印象的です。私たち当局者は前から聞いていましたが、それを公言するようになったわけですから。日本が高いガスを買ってきた状況が、少しずつ変化している。これもシェール革命の影響だと思います。
異質なビジネス、リスクの認識を
―一方で、シェール開発関連の損失も目立っています。住友商事がシェールオイル開発の失敗で2400億円の特別損失を今年9月に計上。大阪ガスもシェールガスの開発失敗で昨年度290億円の特損を出しました。
住田 行政は法律の定める範囲を超えて企業活動に口は出せません。しかし、多額の損失が、消費者や国民経済に悪影響をもたらす事態は回避したいものです。シェール革命の長所と同時に、その裏にあるリスクに十分配慮する必要があります。
どの会社にも得意、不得意があります。資源開発の経験がある企業は、その不確実性とリスクを認識しているように見えます。一方で経験が少ないと、投資の対象や判断が必ずしも適切にならず、判断や大きな損失を被りかねません。失敗した案件においては、その分析と決断でどこかに甘さや見落としがあった可能性があります。
ただし、私は損失を出した企業に「この経験を次の大きな利益につなげてください。『羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く』にならないでください」と申し上げています。失敗はよくないが、そこで得られた知見は必ずあるはず。それを生かし、ビジネスを育てていただきたいと思います。
―電力、ガスのシステム改革が進む中で、シェール革命にエネルギー事業者はどのように向き合うべきか、メッセージを。
住田 シェール革命は大きなチャンスです。私と同じように事業者の多くが期待していると思います。日本のエネルギー事業に新しい可能性が開かれつつある。
日本のガス事業は、原料を調達して国内で売るのが基本の形でした。しかし世界のガス事情が変わる中で、余ったガスを転売する、新しい供給先から掘り出し物を安く買う、上流開発案件を手がけ利益を得るなど、これまでにないビジネスのチャンスが生まれるでしょう。
ただ、海外の政策当局者やエネルギー事業者は、日本の商習慣とは異質な行動をする、手強い人たちだと思います。そして、日本企業の人はまじめで優秀だが「良い人」が多い。そういう百戦錬磨の海外勢とタフな交渉をするのは大変だろうし、向き合ったことのないリスクに直面する機会も増えるはずです。
電力・ガス事業者の方はもちろん肝に銘じているでしょうが、新しい状況のメリット、その裏にあるリスクの存在の双方をしっかり認識していただきたい。そしてチャンスから利益を得て、ぜひ日本経済、消費者に成果を還元してほしいと思います。
住田孝之 資源エネルギー庁資源・燃料部長。東京大学法学部、ジョージタウン大学国際政治大学院卒。1985年通産省入省。経産省情報通信機器課課長などを経て13年6月から現職。
(取材 構成 石井孝明 ジャーナリスト)
(2014年12月22日掲載)

関連記事
-
「再エネ100%で製造しています」という(非化石証書などの)表示について考察する3本目です。本来は企業が順守しなければならないのに、抵触または違反していることとして景表法の精神、環境表示ガイドラインの2点を指摘しました。
-
福島第一原子力発電所事故の後でエネルギー・原子力政策は見直しを余儀なくされた。与党自民党の4人のエネルギーに詳しい政治家に話を聞く機会があった。「政治家が何を考えているのか」を紹介してみたい。
-
池田・石破さんの意見には、印象に残る点がいくつかありました。メディアがこの問題、安全に傾きがちな面はあるという指摘ですが、小島さん、この点をどう考えますか。
-
以前書いたように、再生可能エネルギー賦課金の実績を見ると、1%のCO2削減に1兆円かかっていた。 菅政権が26%から46%に数値目標を20%深堀りしたので、これは年間20兆円の追加負担を意味する。 20兆円の追加負担は現
-
高まる国際競争力への懸念欧州各国がエネルギーコストに神経を尖らせているもう一つの理由は、シェールガス革命に沸く米国とのエネルギーコスト差、国際競争力格差の広がりである。IEAの2013年版の「世界エネルギー展望」によれば、2012年時点で欧州のガス輸入価格は米国の国内ガス価格の4倍以上、電力料金は米国の2-2.5倍になっており、このままでは欧州から米国への産業移転が生ずるのではないかとの懸念が高まっている。
-
言論アリーナ「エネルギー基本計画は実現できるのか」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 政府の新しいエネルギー基本計画が決まりました。再エネを主力にして「脱炭素社会」をめざすことになっていますが、その目標は果たして
-
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を「カーボンニュートラル」と呼ぶ習慣が流行っているようだが、筆者には種々の誤解を含んだ表現に思える。 この言葉は本来、バイオマス(生物資源:
-
福島における原発事故の発生以来、世界中で原発の是非についての議論が盛んになっている。その中で、実は「原発と金融セクターとの関係性」についても活発に議論がなされているのだが、我が国では紹介される機会は少ない。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間