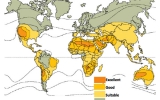BRICSサミットとエネルギー温暖化問題
前回報告した通り、6月のG7カナナスキスサミットは例年のような包括的な首脳声明を採択せず、重要鉱物、AI、量子等の個別分野に着目した複数の共同声明を採択して終了した。
トランプ2.0はパリ協定離脱はいうに及ばず、安全保障、貿易等でも友好国に対しても容赦ない対応をしており、G7でのコンセンサス形成の余地がトランプ1.0以上に限られていることは明らかであった。
そうした中で半導体と並んでハイテク機器に欠かせず、クリーンエネルギー技術のみならず軍事技術にも重要な役割を果たす重要鉱物の供給安全保障問題は、脱炭素やクリーンエネルギー転換において立場を異にする米国とその他G7諸国の間で共通の利害を有する分野である。
①基準に基づく市場の形成、②資本の動員及びパートナーシップへの投資、③イノベーションの促進を三本柱とする重要鉱物行動計画が採択されたのは、そうした背景によるものである。
他方、7月にはリオデジャネイロでBRICSサミットが開催された。今回は習近平国家主席とプーチン大統領が欠席(中国からは李強首相が、ロシアからはラブロフ外相が代理参加)する等、影響力の陰りを指摘されるBRICSであるが、過小評価すべきではない。
BRICSの加盟国は拡大傾向にあり、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アという原加盟国に加え、エジプト、エチオピア、インドネシア、イラン、サウジアラビア、UAEが名前を連ねている(なおサウジアラビアについては米国との関係に配慮し、BRICS会合に参加しつつ、正式加盟表明はしていない模様である※1))。
個別分野の共同声明採択に終わったG7サミットと異なり、BRICSサミットの首脳声明※2)は31ページに及び、その内容も①多国間主義の強化とグローバル・ガバナンスの改革、②平和、安全保障、国際安定の促進、③国際経済・貿易・金融協力の深化、④気候変動との闘い、持続可能で公正かつ包括的な開発の促進、⑤人間・社会・文化開発の促進のためのパートナーシップに及び、④の気候変動、エネルギー関連の主要メッセージは以下のとおりである。
- 持続可能な成長と気候変動対策の両立には、開かれた支援的な国際経済システムが不可欠であると強調。気候変動対策における一方的措置が、差別的あるいは貿易制限的な手段となることに懸念を表明。環境目的と貿易措置が結びついた法的枠組みの課題と機会を認識。特に一方的な貿易措置の増加に強い懸念を示し、反対を表明。
- CBAM(炭素国境調整措置)、森林破壊規制、デューデリジェンス要求等に対し、国際法に沿わない懲罰的・保護主義的措置として反対。COP28での「一方的貿易措置回避」の呼びかけへの支持を再確認。供給・生産チェーンを故意に混乱させる措置への反対を表明。
- SDG7に沿った安価・信頼性あるエネルギーアクセスと公正な転換へのコミットメントを再確認。BRICS間のエネルギー協力強化を呼びかけ。2025–2030年のロードマップ更新等の進展に留意。
- エネルギー安全保障の重要性を強調(経済・国家安全保障・福祉の基盤)。市場安定、供給の多様性、インフラ保護の必要性に言及。化石燃料の依然として重要な役割を認識。各国の事情や責任に配慮した、公正・秩序ある包摂的なエネルギー移行が必要。気候対応と経済発展の両立を強調。
- 公正で包摂的な移行に向けた資金アクセスと投資拡大の必要性を強調。先進国に対し、譲許的資金の予測可能・低コストな供給を要求。市場・技術・低利金融への非差別的アクセスの確保を求める。
- ゼロ・低排出エネルギー技術や供給網強靭化における重要鉱物の役割を認識。資源主権を尊重しつつ、信頼性・責任ある持続可能な鉱物サプライチェーンの促進を支持。
気候変動面ではパリ協定、気候変動枠組み条約の目的追及への結束を再確認しつつも、トランプ前のG7サミットのような2050年カーボンニュートラルや1.5℃目標へのコミットメントは全く見られない。むしろ、気候変動資金動員に向けた先進国の責任と、途上国への資金移転を円滑化するような公正な国際通貨金融システムの役割が強調されている。
更にEUの国境調整措置等、気候変動対策における一方的措置を「懲罰的・保護主義的」として強く批判している。一方的措置の問題は本年6月の気候変動枠組み条約補助機関会合でも大きな争点となり、11月のCOP30でも引き続き議論されることは確実だ。
エネルギー面では安価で信頼性のあるエネルギーアクセスと公正な移行、各国の国情の尊重が謳われ、エネルギー転換途上における化石燃料の役割が明確に認知されている。以前のG7サミットでは化石燃料や石炭火力のフェーズアウトがプレイアップされていたが、そうした理念先行型のエネルギー転換論は皆無である。
重要鉱物については鉱物生産国としての立場を前面に出し、「鉱物資源に対する主権を完全に保持し、資源国の利益分配、付加価値、経済多様化を保証するための公正なサプライチェーン」を強調しており、鉱物消費国としてサプライチェーンの多様化、環境や人権基準に基づく市場ルール設定を企図しているG7に対峙している。
G7がエネルギー・温暖化問題で共同歩調を取れていないのと対照的に、BRICSは新興国、資源国の立場を前面に出し、団結を誇示しているように見える。
率直に言って1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルにとらわれたG7サミットのこれまでのトーンに比してエネルギーの現実を反映しているともいえる。そもそも世界のエネルギー温暖化情勢の帰趨を左右するのはG7(エネルギー消費、CO2排出量の対世界比は30%、25%)よりもBRICS11か国(同49%、58%)であり、その差は更に開いていくのだから当然であろう。
1975年の第1回G7ランブイエサミット当時と異なり、G7とBRICS、G20を併せてみなければ世界の帰趨は語れない。
■
※1)Saudi Arabia sits on fence over BRICS with eye on vital ties with US
※2)BRICS Summit signs historic commitment in Rio for more inclusive and sustainable governance

関連記事
-
政府が2017年に策定した「水素基本戦略」を、6年ぶりに改定することが決まった。また、今後15年間で官民合わせて15兆円規模の投資を目指す方針を決めたそうだ。相も変わらぬ合理的思考力の欠如に、頭がクラクラしそうな気がする
-
最近出たお勧めの本です。 著者のマイケル・シェレンバーガーは初めは環境運動家だったが、やがてその欺瞞に気づき、いまでは最も環境に優しいエネルギーとして原子力を熱心に推進している。 地球温暖化に関しては小生とほぼ意見は同じ
-
福島における原発事故の発生以来、世界中で原発の是非についての議論が盛んになっている。その中で、実は「原発と金融セクターとの関係性」についても活発に議論がなされているのだが、我が国では紹介される機会は少ない。
-
昨年の地球の平均気温は、観測史上最高だった。これについて「その原因は気候変動だ」という話がマスコミには多い。 気候変動の話をすると、「地球の歴史からするとこの程度は昔もあった」というコメントがつくのだが、現生人類も文明も
-
2年半前に、我が国をはじめとして、世界の潮流でもあるかのようにメディアが喧伝する“脱炭素社会”がどのようなものか、以下の記事を掲載した。 脱炭素社会とはどういう社会、そしてESGは? 今回、エネルギー・農業・人口・経済・
-
2022年の世界のエネルギー市場はウクライナ戦争に席巻された。ウクライナ戦争の出口が見えない状況下で、2023年10月にはイスラム組織ハマスがイスラエルへの越境攻撃を行った。イスラエルがハマス、およびその背後にいると言わ
-
今年7月末に「『気候変動・脱炭素』 14のウソ」という日本語の書が出版された。著者は渡辺正博士。全体は「気候変動」編と「脱炭素」編に分かれ、それぞれ7つの「ウソ」について解説されている。前稿の「気候変動」編に続き、今回は
-
再生可能エネルギーの導入拡大に向けてさまざまな取組みが行われているが、これまでの取組みは十分なものといえるのだろうかというのが、今回、問題提起したいことです。そのポイントは以下のようになります。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間