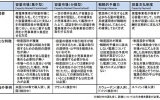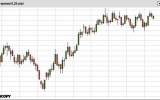中部電力、浜岡原発の現状(下) — 再稼動は「エネルギー政策正常化」の証明
厳しい経営状態の中部電力
原発の稼動の遅れは、中部電力の経営に悪影響を与えている。同社は浜岡しか原発がない。足りない電源を代替するために火力発電を増やして、天然ガスなどの燃料費がかさんでいるのだ。
同社は13年度前半期に赤字を計上し、通期でも650億円の赤字になると予想を公表した。通期赤字は3期連続となり、これは上場企業にとって厳しい経営状況だ。
今年9月に、中部電力は経産省に家庭用電気料金の平均4・95%の値上げを申請した。また政府の認可がいらない企業向け電気料金についても8・44%の値上げを決めた。浜岡原発の停止は人々の生活、そして機械産業の集積する中部地域の経済全体にコスト面で悪影響を与えている。
また同社は9月、およそ800万円の従業員の平均年収を、およそ2割引き下げる案を労働組合に提示した。働く人にとっても厳しい状況だ。
きっかけは菅首相のパフォーマンス
中部電力の浜岡原発が止まったのは、11年5月に当時の首相の菅直人氏が突如記者会見を開き、稼働中の浜岡原発の停止を要請したことによるものだ。法的・科学的根拠なく、「近い将来、地震が起こる可能性がある」というあいまいな理由を菅氏は述べた。首相の要請には逆らえないだろう。同社は、それを受け入れた。
その後に自主的に安全対策を計画、実行したが、国からは再稼動の確約はなかった。他社の原発も、法律に基づかないテストの実施が菅氏の発案で行われ、稼動が先に延びていった。そして今年8月の新基準が示された。同委員会は審査をやり直すとしており、原発の再稼動は数年先になると見込まれる。発電を火力にすることで、電力会社は13年度に3兆8000億円のコスト増となり、軒並み赤字に転落する見込みだ。
11年5月当時は原子力事故直後で、恐怖感が社会に広がっていた。支持率低迷に悩んだ菅氏が、その世論に迎合するために、深い検証のないままパフォーマンスで浜岡原発の停止要請したように思える。首相には稼働中の原発を止める権限はない。これは首相自らによる裁量行政であり、「法の支配」の破壊である。
中部電力は厳しい経営環境に、政治家の横暴で要請で追い込まれてしまった。これは他の電力会社もそうだ。東電以外の電力会社は、原発事故を起こしていないし、経営判断のミスもしていない。私は電力会社に利害関係はないが、これは社会正義の観点から不当であると思う。
中部電力は、一連の政治の横暴と言える仕打ちについて、会社も社員も対外的に評価のコメントをしていない。電力会社という公益事業である以上、政府や社会に強く反発できないのだろう。ただし発電所構内には「負けてたまるか」という、水野明久中部電力社長の書いた色紙や、それを印刷した標語が書かれていた。何も言い返せない無念さが、標語に現れているように思えた。
救いだったのが、同社の人々が前向きに行動していたことだ。浜岡原子力発電所長の梶川祐亮(かじかわ・ゆうすけ)氏は、次のように語った。「私たちは、浜岡を世界一安全な原発にして、地域と社会の方に一段と安心を持っていただこうと取り組んでいます」。この態度に、私は敬意を持った。
政策混乱の象徴、浜岡原発の早期再稼動を
福島原発事故以降、電力会社や原発に対する恐怖心と反感が社会に広がった。確かに、事故は大変な混乱を社会にもたらし、誰もが原子力の安全な運用の必要を認識した。
しかし原発の運用、規制のあり方については、電力会社と社会の負担を最小限にすることを考え、恣意性を排除した適正な手続きに基づくべきであった。原発の稼動を継続しながら、事故対策の補強工事をする。そして原発とエネルギーの未来をめぐる国民的議論を深めるという合理的な方法はあったはずだ。過去に原子力の大事故を起こした、米英ソ連では、原発を大事故直後に長期にわたって全部止めるなどという非合理な行動をしなかった。
浜岡原発を訪問して不思議に思うことがあった。私は掛川駅(静岡県)から浜岡までの移動で、周辺地域を観察した。現地までは起伏のある平地が続き、茶畑や工場が散財している。ところが浜岡原発ほど、厳重に防災対策をした施設が見あたらなかった。また海岸線にここまで巨大な堤防は見当たらなかった。もし東南海地震と津波がこの地域を襲ったら、危険と騒がれた浜岡原発が一番安全な場所になってしまうかもしれない。それは防災対策としておかしいし、喜劇的でさえある。
「原子力・エネルギー政策の混乱によって電力会社、そしてその電力の使用者である私たちの被っている損害は、必要のないものが含まれているのではないか」。
私は今回の浜岡の取材で、私はこのような疑問を改めて抱いた。「原子力の安全性の確保」。これは重要な問題だ。しかし、その単一の論点や運用リスクばかりに注目すると、エネルギーをめぐるさまざまな論点への配慮がおろそかになってしまう。リスクゼロを過剰に目指すと、重要な問題である「お金」が過剰に費やされてしまうのだ。
私は原発に思い入れはないし、電力会社とも利害関係はない。しかし原発を使わずに天然ガスを代わりに燃やすことで、毎日数百億円も不必要な損害が生じ、電力会社と利用者が負担を続ける今のエネルギー政策を「おかしい」と考えている。
私は、原発の再稼動と、エネルギー政策の正常化を願う。現時点で原子力発電を活用しながら、将来の原発の行く末を議論することは可能であるはずだ。原子力・エネルギー政策の混乱の始まりとなった浜岡原発は、一種のシンボルであろう。浜岡原発の再稼動は、エネルギー政策が正常化したことの証明になるし、菅直人氏と民主党が行った悪しきエネルギー政策との完全な決別となるであろう。
私は、浜岡原発の一日も早い再稼動を期待している。
(2013年11月11日掲載)

関連記事
-
nature.com 4月3日公開。英語題「Impacts of nuclear plant shutdown on coal-fired power generation and infant health in the Tennessee Valley in the 1980s」石炭火力発電へとシフトした結果、粒子汚染が増加し、影響を受けた場所のほとんどで乳児の健康が損なわれた可能性があることから、公衆衛生に対する悪影響が示唆されている。
-
ドイツ連邦経済エネルギー省は7月3日、ホワイトペーパーを公表、卸市場の改革とあわせ、容量リザーブ(戦略的予備力制度)を導入することを明らかにした。
-
GEPRを運営するアゴラ研究所は、言論アリーナというインターネットの映像番組を提供している。1月16日の放送は、「電力自由化の光と影」だった。(YouTube)それを報告する。
-
石油輸出国機構(OPEC)が6月5日に開催した総会では、市場の予想通り、生産目標が日量3000万バレルで据え置かれた。これにより、サウジなど生産調整による原油価格の下支えを放棄する「減産否定派」の声が今回も通ったことになる。
-
事故確率やコスト、そしてCO2削減による気候変動対策まで、今や原発推進の理由は全て無理筋である。無理が通れば道理が引っ込むというものだ。以下にその具体的証拠を挙げる。
-
ドナルド・トランプ新大統領は、グリーンエネルギー事業は同国経済にとって悪材料だと主張している。だが、そのトランプに異議を唱えたい人たちにとっては歓迎すべきデータが発表された。
-
今年の10月から消費税率8%を10%に上げると政府が言っている。しかし、原子力発電所(以下原発)を稼働させれば消費増税分の財源は十二分に賄える。原発再稼働の方が財政再建に役立つので、これを先に行うべきではないか。 財務省
-
日本では殆どの新聞に載っていませんが、6月10日にスウェーデンの与党(社会民主党、緑の党)、野党(穏健党、中央党、キリスト教民主党)の5党が、「原子力発電に掛けていた高額な税金を廃止して、原子力発電の継続を支える」ことに合意しました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間