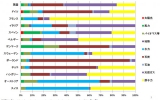今週のアップデート — アゴラ・シンポジウムのお知らせ(2013年11月25日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
1)第2回アゴラ・シンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」
アゴラ研究所・GEPRは、12月8日に国際シンポジウムを行います。福島原発事故を受けて、エネルギーの未来を考える国際シンポジウムを開催します。参加(無料)は記事中の申し込みフォームから。ぜひご参加ください。
2)第2回アゴラ・シンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」出演者の意見
アゴラ・シンポジウム出席者の意見、経歴です。
3)「政策議論のすれ違い」「温暖化とエネルギー選択」【シンポジウム資料】
4)COP19参戦記—失敗?日本の新目標発表、なぜ「今」だったのか
シンポジウムの第2セッション「原発ゼロは可能か」で、パネリストとして登場する国際環境経済研究所理事・主席研究員の竹内純子さんの論考です。前者はシンポジウム資料、後者は竹内さんが参加した、温暖化をめぐるワルシャワでの国際会議でのルポです。シンポジウムを視聴、参加する皆さまは、ぜひ参考にしてください。
国際エネルギー機関(IEA)が毎年発表する世界エネルギー展望が発表されました。そのポイントを解説したGEPR編集部の記事です。同リポートでのシェールガス増産の影響を分析した部分をまとめています。
今週のリンク
日本経済新聞11月24日記事。今回のCOP(気候変動枠組み条約締約国会議)で、日本は温室効果ガス削減目標の切り下げを批判されました。一方で、会議の内容は、前回のCOPで決まった2015年までに制度をつくるという目標に向けた「前哨戦」でした。自主目標導入は予想の範囲内でした。
IEAが毎年提供する世界エネルギー展望の2013年版が11月12日に発表されました。昨年に続き、シェールガス大増産の分析をしています。同リポートでは米国のエネルギー面での優位性の拡大を指摘しています。
読売新聞11月22日社説。進展しない放射性廃棄物問題では、処分地の選定で自治体の応募が前提となっています。経産省がこの見直し案をまとめました。こうした制度を改めて、国が前面に出るべきとの主張です。妥当な考えでしょう。
原子力規制委員会11月20日公表。福島原発事故の帰還について、空間線量ではなく、個人線量の調査によって安全性を確認することを提言しています。当初は年20mSvとして、段階的に自然被ばく量に引き下げることが望ましいとも指摘しています。現実的政策への転換です。この提言の実効化が望まれます。
日本原子力産業協会の解説ビデオです。GEPRの寄稿者であった日下部正志氏(記事)も発言。福島原発の現状が映像で分かると同時に、有識者の意見をまとめています。原子力関係団体のビデオですが、客観的な内容でした。

関連記事
-
去る6月23日に筆者は、IPCC(国連気候変動政府間パネル)の議長ホーセン・リー博士を招いて経団連会館で開催された、日本エネルギー経済研究所主催の国際シンポジウムに、産業界からのコメンテーターとして登壇させていただいた。
-
米国の気候変動特使にして元国務長官のジョン・ケリーがBBCのインタビューでトンチンカン発言をして、ネットで炎上している。 ロシアがウクライナに侵攻しているというのに、 Former U.S. Secretary of S
-
ドイツで薬不足が続いている。2年前の秋ごろも、子供用の熱冷ましがない、血圧降下剤がない、あれもない、これもないで大騒ぎになっていたが、状況はさらに悪化しており、現在は薬だけでなく、生理食塩水までが不足しているという。 生
-
福島第一原発事故から3年3カ月。原発反対という声ばかりが目立ったが、ようやく「原子力の利用」を訴える声が出始めた。経済界の有志などでつくる原子力国民会議は6月1日都内で東京中央集会を開催。そこで電気料金の上昇に苦しむ企業の切実な声が伝えられた。「安い電力・エネルギーが、経済に必要である」。こうした願いは社会に広がるのだろうか。
-
(GEPR編集部より)この論文は、国際環境経済研究所のサイト掲載の記事から転載をさせていただいた。許可をいただいた有馬純氏、同研究所に感謝を申し上げる。(全5回)移り行く中心軸ロンドンに駐在して3年が過ぎたが、この間、欧州のエネルギー環境政策は大きく揺れ動き、現在もそれが続いている。これから数回にわたって最近数年間の欧州エネルギー環境政策の風景感を綴ってみたい。最近の動向を一言で要約すれば「地球温暖化問題偏重からエネルギー安全保障、競争力重視へのリバランシング」である。
-
メディアでは、未だにトヨタがEV化に遅れていると報道されている。一方、エポックタイムズなどの海外のニュース・メディアには、トヨタの株主の声が報じられたり、米国EPAのEV化目標を批判するトヨタの頑張りが報じられたりしてい
-
「死の町」「放射能汚染」「健康被害」。1986年に原発事故を起こしたウクライナのチェルノブイリ原発。日本では情報が少ないし、その情報も悪いイメージを抱かせるものばかりだ。本当の姿はどうなのか。そして福島原発事故の収束にそ
-
ウォール・ストリート・ジャーナルやフォーブズなど、米国保守系のメディアで、バイデンの脱炭素政策への批判が噴出している。 脱炭素を理由に国内の石油・ガス・石炭産業を痛めつけ、国際的なエネルギー価格を高騰させたことで、エネル
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間