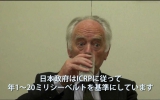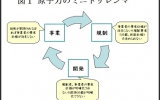「専門家が自らの役割の認識を不足」学会報告【原発事故3年】
東京電力福島第一原子力発電所の事故を検証していた日本原子力学会の事故調査委員会(委員長・田中知(たなか・さとし)東京大学教授)は8日、事故の最終報告書を公表した。
福島原発事故は、津波、過酷事故、緊急時・事故後対策のいずれも不十分と指摘。これらの原因をもたらしたものは「1・専門家の自らの役割に関する認識の不足」「2・事業者の安全意識と安全に関する取り組みの不足」「3・規制当局の安全に対する意識の不足」「4・国際的な取り組みや共同作業から謙虚に学ぶことの不足」「5・安全性を確保するための人材、および組織運営基盤の不足」の複合要因と結論づけた。
同委員会は今後、この提言を元に、廃炉と福島の復興活動を協力していく予定だ。記者会見で田中委員長は、「事故から学ばない組織、専門家は原子力にかかわる資格がなくなる。専門家の力不足を痛切に反省している」と述べた。
報告書は9章425ページの大部で、丸善から「福島第一原子力発電所事故 その全貌と明日に向けた提言––学会事故調最終報告書」として3月11日に刊行される。
事故をめぐるシグナルはあった。
原子力学会は約7000人の会員を持つ。すでに政府事故調などが検証を発表しており、既存のデータの解析などに基づいていた。ただし、一部で指摘された地震による、福島原発の3つの原子炉の損傷の可能性については、原子炉圧力などの面から、「可能性はほぼない」としている。
事故原因は津波による、安全装置の破壊と全電源喪失と指摘。過去の東北の地震、2004年のスマトラ沖地震など、津波対策に力を入れることを示す情報があった。そのに、規制当局、専門家、東電がその可能性を無視したことを反省した。
また原子力発電は巨大な複雑系という特長を持つ。そのために、各専門家が、専門分野のみに関心を向け、総合的に考えなかったことが事故の一因となったとしている。
原子力安全、専門家の役割を強調
今後の原子力の安全を高めるために、原子力安全の目標をこれまであいまいであったと反省。社会との対話の中で、原子力の利用活動に伴うリスクを、合理的に実行可能な限り低くすることと定めた。
さらに、相互に独立し、多様な手段で事故に備える、「深層防護」という考えを強調。また確率的手法を多様化してリスクを洗い出し、評価と是正を重ねることを提言した。
さらに専門家集団として、知見が事前にあったのに、それを事故の事前対策、また事後対応に活かせなかったことを反省した。学会・学術界は自由な議論と、安全研究が足りなかったことを指摘し、それらを継続的に改善していくとしている。
また日本の安全対策が、ハード(機材)偏重、そして専門家の視野の狭さという悪習があるため、ソフト、つまり人やマネジメント、発想法などの改革を重ね、人材育成にも注力すべきと、まとめている。
アゴラ研究所フェロー・石井孝明
(2014年3月10日)

関連記事
-
アゴラ研究所の行うシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」の出演者が、GEPRに寄稿した文章を紹介します。
-
4月4日のGEPRに「もんじゅ再稼働、安全性の検証が必要」という記事が掲載されている。ナトリウム冷却炉の危険性が強調されている。筆者は機械技術屋であり、ナトリウム冷却炉の安全性についての考え方について筆者の主張を述べてみる。
-
アゴラ研究所はエネルギー情報を集めたバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営している。12月に行われる総選挙を前に、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に渡って行った。(ビデオは画面右部分に公開)
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
アゴラ研究所は12月8日にシンポジウム「第2回アゴラ・シンポジウム --「持続可能なエネルギー戦略を考える」を開催する。(内容と申し込みはこちら)視聴はインターネット放送などで同時公開の予定だ。
-
政府は政府事故調査委員会が作成した吉田調書を公開する方針という。東京電力福島第一原発事故で、同所所長だった故・吉田昌郎(まさお)氏が、同委に話した約20時間分の証言をまとめたものだ。
-
中国の台山原子力発電所の燃料棒一部損傷を中国政府が公表したことについて、懸念を示す報道が広がっている。 中国広東省の台山原子力発電所では、ヨーロッパ型の最新鋭の大型加圧型軽水炉(European Pressurized
-
はじめに 原子力にはミニトリレンマ[注1]と呼ばれている問題がある。お互いに相矛盾する3つの課題、すなわち、開発、事業、規制の3つのことである。これらはお互いに矛盾している。 軽水炉の様に開発済みの技術を使ってプラントを
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間