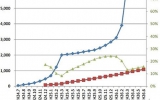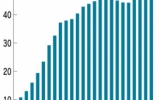どうなる福島原発、汚染水問題【言論アリーナ】(下)あいまいな対策の克服を
(上)より続く。

言論アリーナ、放送スタジオにて
たまり続ける汚染水、海に流せない事情
田原氏、池田氏は共に汚染水対策の膨大さに驚いた。「ここまでやって東電の資金が続くか分からないし、それに見合った効果があるのだろうか」(池田氏)。
東電の対策には懸念される点が多い。一例はたまった汚染水の処理だ。これを保管するタンクが壊れて、水が漏れたことをメディアが騒いだ。しかしタンク内にあるものは、セシウムを取り除いたもので、残っているのは水と一緒になって分離できないトリチウムという核物質だ。これは核分裂反応で必ず発生するもので、遮蔽の容易なベータ線を微量に出すだけという。つまり健康被害の可能性は極小だ。
「リスクゼロを追求することで、大変な負担が生じる。これがこれまでの原発事故処理で繰り返され、負担が膨大になった」と池田氏は指摘した。そして田原氏は質問した。「米英仏の制度を調べると、他国ではトリチウムは海に流している。なぜ日本でできないのか。このままではタンクを無限につくらなければならなくなる」。
姉川氏は「ためた汚染水の処理の先が決まっていない」ことは認めた。当初、東電は安全性を確認した水から海に流す計画だった。しかし事故直後の漏洩、さらに11年5月にタンクの余裕がなく少量海に放出した際に、地域住民、福島県、漁協、さらには韓国からの批判があった。それに配慮してため続けるという選択をしているという。
「事故を起こした私たちが原因だが、対応ごとに風評が生まれ、福島の皆さまに迷惑が生じてしまう」と、姉川氏は状況の難しさを説明した。

姉川東電常務
東電に全責任、それがコストを考えない処理に
「『できないことはできない』と、国に言うべきではないのか」と田原氏が質問した。すると姉川氏は「今回、国にご支援をいただくことになり、深く感謝し、責任を痛感している。ただ自分たちでやろうとして、限界をなかなか言えないのは反省する点がある」と答えた。
「東電からは言えなさそうだから、何が問題ですか」と田原氏は、池田氏に話を振った。池田氏は「今の政策は、『すべてを東電に背負わせる』という形。そんなことはできるわけがない」と述べた。賠償は5兆円、除染に5兆円、東電が背負うと見込まれる。この金額は一企業として支払える範囲を越えている。さらに東電は事故対策の負担も背負う。
大規模な原子力災害が天災やテロなどで引き起こされた時に、国が責任を持つという規定がどの国にもある。日本でも原子力損害賠償法で、そう決まっていた。ところが2011年夏に、民主党政権が事故処理策を検討する際に、その規定が適用されずに国が責任を負わない形になった。
東電が賠償を引き受け、国が賠償に限って支援するという形を採用し、東電を倒産させずに存続させた。当然、東電の経営は立ち行かなくなり、昨年国は東電の増資を引き受けて、過半数超の株を保有して実質国有化した。
「この処理スキームが、何でも東電に引き受けさせようという風潮をつくり、賠償や除染の基準引き下げと膨大な支出を生んだ。また責任も、東電が持つのか、国が持つのかあいまいな点がある」と池田氏は分析した。賠償と除染の量が多すぎ、それらの金銭負担がかなりいいかげんに支出され、東電が支払う形になっている。
田原氏は「民主党が東電を悪者にして被害者としての格好を付けるために、その処理策を後押しした面がある。仙谷由人(菅内閣官房長官)が回顧録(『エネルギー・原子力大転換』(講談社))で、自分がドロをかぶって決めたと言っている」と指摘した。
同時に田原氏は「銀行と機関投資家が東電にカネを貸している。東電にモラルハザードの懸念もあった。財務省も負担を嫌がった。そして国民感情も事故直後は国の支出を拒否した。仙谷の決定の理由も分かる。しかし、この処理策は限界にきている」と述べた。
そして国の動きが鈍いことが、事故処理にさまざまな影響をもたらす。一例が、新潟県の東電柏崎刈羽原発の再稼動問題だ。東電はこの原発について原子力規制委員会の安全審査を行う予定だ。ところが新潟県の泉田裕彦知事が、それを認めないと表明している。知事には、再稼動を認める法的な権限がない。田原氏も「原発を動かさなければ、東電が倒産する」と懸念を述べた。姉川常務は、「委員会への申請は取締役会で決めている。福島事故の教訓を活かし、対策を進めていることを知事と新潟県の皆様に説明を続ける」と言明したが、先行きは不透明だ。
「原発事故、国が責任を持つべき」、ひろがる賛成
安倍首相は「国が責任を持つ」と今回のオリンピック招致で宣言した。「470億円の支出は菅義偉官房長官主導で決まったが、東電処理策の抜本的な変更はまだ政治家の間で語られていない」と田原氏は語った。支援スキームを決めた「支援機構法」は1年経過すると見直すことが盛り込まれた。2011年夏に施行されたが、まだ見直しの検討は行われていない。
池田氏は「東電と事故処理スキームを最初に戻って考え直すことが必要だ。電力事業を行う『グッド東電』と事故処理を含む『バッド東電』に分けることも含め、事故処理体制を、根本的に見直さないと、税金による東電救済が続いてしまう」と懸念を示した。
国民感情として、東電の起こした事故を税金を使って支援することに、不快感が広がる。しかし対策の大きさ、そして責任の所在が不明確な現状は、修正しなければより大きな負担がやってくるだろう。
姉川氏は「自分たち東電がどんな場合でも、実施の主体になり、逃げるつもりはない」と述べた。しかし東電だけでは問題は解決できない状況が生まれている。汚染水問題は、福島原発事故の処理スキームという大きな視点で考え直す必要がありそうだ。
田原氏は最後に振り返った。「これは太平洋戦争のときの日本軍と同じだ。最前線の部隊は頑張るんだけど、大戦略がないんだ。それで結局負けてしまう」。
最後にニコニコ生放送の視聴者へ質問(回答総数不明)を行った。「汚染水問題を含めた原発事故処理について、国が責任を持つべきだと思いますか」というもの。それに84%が「責任を持つべき」と答えた。東電処理スキームのおかしさを、多くの人が気づきはじめている。

池田信夫氏
(2013年9月17日掲載)

関連記事
-
全国の電力会社で、太陽光発電の接続申し込みを受けつけないトラブルが広がっている。これは2012年7月から始まった固定価格買い取り制度(FIT)によって、大量に発電設備が設置されたことが原因である。2年間に認定された太陽光発電設備の総発電量は約7000万kW、日本の電力使用量の70%にのぼる膨大な設備である。
-
けさの日経新聞の1面に「米、日本にプルトニウム削減要求 」という記事が出ている。内容は7月に期限が切れる日米原子力協定の「自動延長」に際して、アメリカが余剰プルトニウムを消費するよう求めてきたという話で、これ自体はニュー
-
1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原子力発電所原子炉の事故は、原子力発電産業においてこれまで起きた中でもっとも深刻な事故であった。原子炉は事故により破壊され、大気中に相当量の放射性物質が放出された。事故によって数週間のうちに、30名の作業員が死亡し、100人以上が放射線傷害による被害を受けた。事故を受けて当時のソ連政府は、1986年に原子炉近辺地域に住むおよそ11万5000人を、1986年以降にはベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナの国民およそ22万人を避難させ、その後に移住させた。この事故は、人々の生活に深刻な社会的心理的混乱を与え、当該地域全体に非常に大きな経済的損失を与えた事故であった。上にあげた3カ国の広い範囲が放射性物質により汚染され、チェルノブイリから放出された放射性核種は北半球全ての国で観測された。
-
中部電力の浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)は、昨年5月に菅直人首相(当時)の要請を受けて稼動を停止した。ここは今、約1400億円の費用をかけた津波対策などの大規模な工事を行い、さらに安全性を高めようとしている。ここを8月初頭に取材した。
-
原子力災害は、家庭、職場、地域コミュニティという「場」を破壊するという意味において異質である。今次の東電福島原発事故のような大規模災害においては、金銭賠償では救済が困難な被害があり、それが被災者の生活再建を滞らせている要因であることをかんがみ、国あるいは地方自治体による地域コミュニティ再生の取り組みが、事故後早い段階においてなされる必要性、民法不法行為制度による対応とは別に、例えばダム開発における土地収用法を参考に、集落・地域の再建を図ること等を含む国による災害補償スキームを創設しておく必要性を指摘しておきたい。
-
英国のEU離脱後の原子力の建設で、厳しすぎるEUの基準から外れる可能性、ビジネスの不透明性の両面の問題が出ているという指摘。
-
日本経済研究センター 3月7日発表。2016年12月下旬に経済産業省の東京電力・1F問題委員会は、福島第1原発事故の処理に22兆円かかるとの再試算を公表し、政府は、その一部を電気料金に上乗せするとの方向性を示した。しかし日本経済研究センターの試算では最終的に70兆円近くに処理費が膨らむ可能性すらある。
-
四国電力の伊方原発2号機の廃炉が決まった。これは民主党政権の決めた「運転開始40年で廃炉にする」という(科学的根拠のない)ルールによるもので、新規制基準の施行後すでに6基の廃炉が決まった。残る原発は42基だが、今後10年
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間