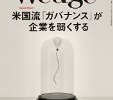今週のアップデート — 東京都のエネルギー(2014年4月21日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
1)「常識」に戻る東京都のエネルギー対策 — 政治の翻弄から再エネ振興へ
2月の東京都知事選では、細川護煕候補などは原発の是非を争点にしようとしました。ところが、有権者はそれに反応しませんでした。また東京都で実際に、どのような政策が行われているか、知る人は少ないと思います。GEPRの編集にかかわるジャーナリストの石井孝明のまとめ記事です。
2)電力値上げ6社目、中部電力の申請を分析=原発停止の影響を見る
政策家で元経産省の石川和男さんの分析です。中部電力の値上げ申請の内容を精査し、原発停止の影響の大きさを示しています。これでも赤字の懸念が出ています。同社もその顧客である東海地域の人々も、法令違反はしていないのに、電力料金値上げに直面しています。これは、問題です。石川氏のブログ「霞が関政策総研」からの紹介。
山本隆三国際環境経済(IEEI)研究所主席研究員、常葉大学経営学部教授の論考です。「エネルギー貧困」という名の問題が欧州で浮上。再エネ負担で恩恵を受けないのに、負担だけを押し付けられる人が社会問題になっているそうです。IEEIからの転載。
今週のリンク
文部科学省、4月13日公表。「気候変動の緩和策」を分析した報告です。追加的な緩和策のないと、2100年における世界平均地上気温が、産業革命前の水準と比べ中央値で3・7度から4・8度、気候の不確実性を考慮すると2・5〜7・8度上昇する可能性があることを示しました。さらに政策の統合が行われねば、効果的な緩和策は達成されないと、分析しています。
読売新聞4月19日社説。18日の参院本会議で、アラブ首長国連邦(UAE)とトルコとの原子力協定締結が結ばれました。これを肯定的に受け止める論説です。しかし、日本での原発再稼動の遅れなど、原子力政策が定まらない中で、輸出に熱心な安倍政権の姿に違和感を覚えます。
日本で珍しい、ペルシャ湾岸諸国のニュース。Gulf Businessから4月18日記事。原題はNuclear Power: Boon Or Bane For The GCC?。石油後をにらみ、アラブ首長国連邦とサウジの原発建設の意欲が高まっている一方、異論が出ていることを紹介しています。
4)(核兵器)軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)広島外相会合
外務省、4月12日発表。核保有国以外の諸国が集まり、核不拡散を働きかける外相会議が、日本のイニシアティブで広島で行われました。残念ながら核保有国、北朝鮮などの潜在的保有国は黙殺しています。しかし、こうしたまとまりが、原子力の平和利用の流れを作ることを、期待します。
産経新聞4月17日記事。原発停止の影響で、また電力供給が綱渡りとなりそうです。電力会社はトラブルに備え、5%程度の予備率を確保してきました。この予備率ではトラブルで、停電などが起こる可能性があります。

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
菅政権の下で「2030年CO2を46%減、2050年にCO2ゼロ」という「脱炭素」の目標が発表された。 しかしながら、日本は製造業の国である。製造業は石油、ガス、石炭などを燃やしてエネルギーを得なければ成り立たない。 特
-
桜井柏崎市長と東電・小早川社長の会談 2025年1月22日、柏崎市の桜井市長は、市役所を訪問した東京電力ホールディングスの小早川社長に対し、柏崎刈羽原発1号機がかつて東北電力と共同で開発された経緯に触れたうえで、6・7号
-
はじめに 地球温暖化に関する情報発信のあり方が、近年大きく変容している。 従来は科学者や教育機関が中心となって行ってきた知識の普及が、いまや国家機関や国際組織による「ナラティブの構築」と「異論排除」の政治的ツールと化しつ
-
日本に先行して無謀な脱炭素目標に邁進する英国政府。「2050年にCO2を実質ゼロにする」という脱炭素(英語ではNet Zeroと言われる)の目標を掲げている。 加えて、2035年の目標は1990年比で78%のCO2削減だ
-
脱炭素、カーボンニュートラル、ネットゼロ。これらの言葉は、いまや疑う余地のない「正解」として共有されている。一般には、木質バイオマスについて次のように説明されることが多い。 木々は成長過程で大気中の二酸化炭素(CO2)を
-
福島第1原発事故から間もなく1年が経過しようとしています。しかし、放射能をめぐる時間が経過しているのに、社会の不安は消えません。
-
このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間