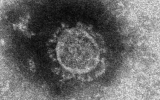「GX債をカーボンプライシングで償還」は論理破綻

bee32/iStock
岸田首相肝いりのGX実行会議(10月26日)で政府は「官民合わせて10年間で150兆円の投資でグリーン成長を目指す」とした。
政府は2009年の民主党政権の時からグリーン成長と言っていた。当時の目玉は太陽光発電の大量導入だった。だが結果として、いま年間3兆円近くの再生可能エネルギー賦課金が国民負担となっている。経済成長どころではない。
さていま日本政府は20兆円の「GX経済移行債」を原資にグリーン技術に投資することに加え、さらに130兆円の民間投資を「規制と支援を一体として促進する」としている。民間がどの技術に投資するかを政策で決めるという訳だ。これは太陽光発電を強引に導入してきたのと同じことを何倍にもするという意味だ。まるで社会主義である。
いまリストアップされている技術は洋上風力や水素利用などだ。これは、万事順調に技術開発が進んだとしても、既存技術に比べて大幅に高コストになる。光熱費はどこまで上がるのか。
政府はこれら技術の既存技術との価格差の補填までするという。これでは日本はますます高コスト体質になる。150兆円の投資というが、それは国民負担になる。経済成長に資するはずが無い。
のみならず、政府はGX債20兆円を起債するにあたり「カーボンプライシングで償還」することを検討している。この意味は、炭素税の税収か、あるいは政府による排出権の売却収入で償還するということだ。
しかしこれは論理的に破綻している。
そもそも国債というのは、それを原資に経済成長をもたらし、所得税や法人税などによる税収増をもたらし、一般財源で償還すべきものだ。建設国債はこの論理に基づいている。
つまり国債とは、本来は、新しい財源を必要とするものではない。
「GX債」も、その起債によるグリーン投資が政府の主張するように本当に経済成長をもたらすのであれば、所得税や法人税などの税収が増えるので、一般財源で償還できるはずだ。
ここで政府が、「償還のために新しい財源が必要」と言っていること自体が、じつは政府主導のグリーン投資による経済成長など信じていない、という自己否定になっている。
明らかな事は、環境税や排出権取引制度を導入すると、日本の製造業はますます疲弊することだ。論理破綻に基づくカーボンプライシングは阻止せねばならない。
■
『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事
-
12月6日のロイターの記事によれば、米大手投資銀行ゴールドマン・サックスは、国連主導の「Net-Zero Banking Alliance:NZBA(ネットゼロ銀行同盟)」からの離脱を発表したということだ。 米金融機関は
-
北海道はこれから冬を迎えるが、地震で壊れた苫東厚真発電所の全面復旧は10月末になる見通しだ。この冬は老朽火力も総動員しなければならないが、大きな火力が落ちると、また大停電するおそれがある。根本的な問題は泊原発(207万k
-
世界の天然ガス情勢に大きな影響を及ぼしている北米のシェールガス革命。この動きを、経産省・資源エネルギー庁はどのように分析し、その変化を日本にどう取り込もうとしているのか。
-
先日紹介した、『Climate:The Movie』という映画が、ネット上を駆け巡り、大きな波紋を呼んでいる。ファクトチェック団体によると、Xで150万回、YouTubeで100万回の視聴があったとのこと。 日本語字幕は
-
きのうのG1サミットの内容が関係者にいろいろな反響を呼んでいるので、少し補足説明をしておく。
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、「IPCC報告の論点⑥」で、IPCCは「温暖化で大
-
トランプ前大統領とハリス副大統領の討論会が9月10日に開催される。大統領選に向けた支持率調査によると、民主党の大統領候補であるハリス副大統領が42%、共和党候補のトランプ前大統領が37%で、ハリス氏がリードを広げていると
-
いまだにワイドショーなどで新型コロナの恐怖をあおる人が絶えないので、基本的な統計を出しておく(Worldometer)。WHOも報告したように、中国では新規感染者はピークアウトした。世界の感染はそこから1ヶ月ぐらい遅れて
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間