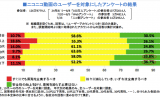今週のアップデート — 規制委員会の活断層判断(2014年6月16日)
アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関のGEPRはサイトを更新しました。
今週のアップデート
1) 敦賀発電所、活断層判定の再考を–原子力規制委員会へ公開討論申し入れ
原子力規制委員会が日本原電敦賀発電所2号機の下に活断層があると昨年5月に発表しました。その後、原電側が新証拠を示し、国外の専門家に評価ももらっています。しかし、規制委員会はそれになかなか応じようとしません。これを憂う民間団体が、公開討論の呼びかけをしています。その団体による主張の説明です。
2)電力とは何か?基礎から分かりやすく-誤解だらけの電力問題【書評】
NPO法人の国際環境経済研究所理事を務め、GEPRにも寄稿いただく竹内純子さんの新刊「誤解だらけの電力問題」の書評です。分かりやすく、電力の現場で学んだその実像を解説しています。
今週のリンク
NHK6月13日報道。原子力規制委員会の委員が9月に代わり、田中知(たなか・さとる)東大教授、石渡明東北大教授の2人が就任します。耐震審査、基準認定を行った島崎邦彦委員が退任します。国会の同意を受けて選出された後で、田中、石渡両氏がインタビューに答えました。
ノンフィクション作家門田隆将氏の6月10日付ブログ。朝日新聞が東電福島第一原発事故で、当時の吉田昌郎所長の政府事故調の調書を朝日新聞がスクープ。ところが、それが誇張され、吉田氏を貶めていると門田氏はさまざまな媒体で批判。門田氏の言うように、誇張の面があるように見られます。
日本経済新聞6月11日記事。改正電気事業法が成立しました。2016年に電力の小売り自由化が柱となる改革です。一般には歓迎する声ばかりですが、この先行きはどうなるのか、検討と評価が必要でしょう。
毎日新聞6月12日記事。7兆5000億円の規模となる電力の小売り市場について、通信業界の参入、異業種連携が始まっています。それをまとめて紹介しています。
ワールドニュークリアニュース(WNN)6月10日記事。原題は「Tsuruga faults inactive, says study」。日本原電の敦賀原発の活断層問題は、原電が海外の研究者に調査を依頼し、その人々が「活断層ではない」と見解を示したために、国際的な関心を集めています。今回のWNNの問題も、原電側の主張を大きく取り上げています。

関連記事
-
日本に先行して無謀な脱炭素目標に邁進する英国政府。「2050年にCO2を実質ゼロにする」という脱炭素(英語ではNet Zeroと言われる)の目標を掲げている。 加えて、2035年の目標は1990年比で78%のCO2削減だ
-
ベクレルという量からは、直接、健康影響を考えることはできない。放射線による健康影響を評価するのが、実効線量(シーベルト)である。この実効線量を求めることにより、放射線による影響を家庭でも考えることができるようになる。内部被ばくを評価する場合、食べた時、吸入したときでは、影響が異なるため、異なる評価となる。放射性物質の種類によっても、影響が異なり、年齢によっても評価は異なる。
-
先進諸国はどこも2050年ネットゼロ(CO2排出実質ゼロ)目標を掲げてきた。だがこんな目標はそもそも実現不可能であるのみならず、それを実現すべく実施された政策は電気代高騰などを引き起こして極めて不人気になり、移民問題に次
-
日本の電力料金は高い、とよく言われる。実際のところどの程度の差があるのか。昨年8月に経済産業省資源エネルギー庁がHPに掲載した資料によれば、為替レート換算、購買力平価換算とも2000年時点では、日本の電力料金は住宅用・産業用とも他国と比較して非常に高かった。
-
「世界で遅れる日本のバイオ燃料 コメが救世主となるか」と言う記事が出た。筆者はここでため息をつく。やれやれ、またかよ。バイオ燃料がカーボンニュートラルではないことは、とうの昔に明らかにされているのに。 この記事ではバイオ
-
「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許
-
「リスクコミュニケーション」という考えが広がっています。これは健康への影響が心配される事柄について、社会で適切に管理していくために、企業や行政、専門家、市民が情報を共有し、相互に意見交換して合意を形成していくことを言います。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間