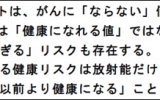今週のアップデート - 福島事故、「その後」の拡大を止めよ(2014年11月4日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
1) 福島でのリスクコミュニケーションの重要性・上=放射能より恐怖が脅威
2) 福島でのリスクコミュニケーションの重要性・下=情報流通での科学者の責務
福島を訪問した、英国人の医師、医学者のジェラルディン・アン・トーマス博士に、福島の問題を寄稿いただきました。福島の問題は、放射能よりも恐怖が健康への脅威になっていること。そして情報流通で科学者の分析が知られず、また行政とのコミュニケーションが適切に行われていないなどの問題があると指摘しています。
3) 福島事故の悪影響はなぜ続くのか-情報汚染による混乱是正を
日本の技術者の投稿です。トーマス博士の医学的な分析に加えて、除染や避難基準などにも言及しています。健康被害の可能性はない事故であったにもかかわらず、初動でおかしな基準をつくったこと、政府が萎縮して広報しなかったことが問題だったと振り返ります。今からでも、政策を見直すべきと指摘しています。
4)映像【ダイジェスト】災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか
14年9月27日開催のアゴラシンポジウム。全編4時間を40分に縮小したものです。見やすいので、ぜひ参考にしてください。
5)映像 Is Fukushima Dangerous? — Distorted images of Japan(福島は危険か? おとしめられる日本の印象)
ジャーナリスト、作家、DJなど多彩な活動をするモーリー・ロバートソンさんと、アゴラ研究所の池田信夫所長が福島の現状について、海外でどのように受け止められているかをまとめました。(大半が英語)
今週のリンク
アン・トーマス博士が2013年、首相の諮問機関である原子力災害専門家グループに寄せた文章です。チェルノブイリとの比較の中で、福島のリスクの少なさを指摘しています。
池田信夫アゴラ研究所所長、ニューズウィーク日本版サイト記事。太陽光発電の見直しについて、この混乱と負担の始まりを振り返っています。政治の手抜きと、利益を得ようとする外資や孫正義さんの蠢動。結局、日本のためにはならなかった制度のように思えます。
経産省。同省に置かれた総合エネルギー調査会の新エネルギー小委員会は、系統ワーキンググループで、電力会社による再エネの接続の一時保留問題を検討しています。揚水発電の利用、接続ルール上で決められる30日の設置設備の保留拒否などを使って、再エネの接続を拡大ししようという案が浮上。しかし制度の抜本的見直しが進むかは現時点で不透明です。
西日本新聞10月30日記事。九州電力が玄海原発の1号炉の廃炉を検討という情報です。まもなく稼働40年になる原発の修繕を断念するとのことです。福島原発事故で老朽化原発が事故を起こしました。原子力規制委員会は40年廃炉ルールを設けています。今後、旧型炉の廃炉が全国の原発に広がる可能性があります。
5)理想どおりにはいかなかったサハラ砂漠の再生可能エネルギー計画
JBpress10月29日記事。ドイツ在住の作家川口マーン恵美さんのコラム。サハラ砂漠でドイツ企業が中心になって太陽光発電でEUに電力を供給するというプロジェクトが進行していました。しかし、計画だけでうまく進んでいないようでした。これは、現地への電力供給事業に縮小する見込みです。

関連記事
-
福島第一原発の南方20キロにある楢葉町に出されていた避難指示が9月5日午前0時に解除することが原子力災害現地対策本部から発表された。楢葉町は自宅のある富岡町の隣町で、私にも帰還の希望が見えてきた。
-
東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から5年が経過した。震災と事故の復旧は着々と進み、日本の底力、そして日本の人々の健全さ、優秀さを示した。同時にたくさんの問題も見えた。その一つがデマの拡散だ。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
原子力発電所事故で放出された放射性物質で汚染された食品について不安を感じている方が多いと思います。「発がん物質はどんなにわずかでも許容できない」という主張もあり、子どものためにどこまで注意すればいいのかと途方に暮れているお母さん方も多いことでしょう。特に飲食による「内部被ばく」をことさら強調する主張があるために、飲食と健康リスクについて、このコラムで説明します。
-
こうしたチェルノブイリ事故の立ち入り制限区域で自主的に帰宅する帰還者は「サマショール」(ロシア語で「自ら住む人」という意味)と呼ばれている。欧米を中心に、チェルノブイリ近郊は「生命が死に絶えた危険な場所」と、現実からかけ離れたイメージが広がっている。サマショールの存在は最近、西欧諸国に知られたようで、それは驚きを持って伝えられた。
-
福島の原発事故から4年半がたちました。帰還困難区域の解除に伴い、多くの住民の方が今、ご自宅に戻るか戻らないか、という決断を迫られています。「本当に戻って大丈夫なのか」「戻ったら何に気を付ければよいのか」という不安の声もよく聞かれます。
-
福島第一原子力発電所の処理水を海洋放出することについて、マスコミがリスクを過大に宣伝して反対を煽っているが、冷静に考えてみれば、この海洋放出は実質無害であることが分かる。 例えば、中国産の海産物を例にとってみてみよう。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間