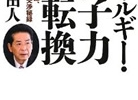COP21に向けてエネルギー政策の正常化を
今年11月にパリで開かれるCOP21(第21回国連気候変動枠組条約締結国会議)では、各国が気候変動についての対策とCO2の削減目標を出すことになっている。日本もそれに向けて、5月までにはエネルギーミックスを決めることになっているが、あいかわらず「原子力を何%にするか」という問題に論議が集中している。
1.最優先の問題は原発の運転の正常化である
経済同友会は、2030年に原子力比率を20%以上にするよう求める提言を発表し、この20%が攻防ラインになってきたようにみえる。しかし原子炉等規制法の「40年ルール」では、建設から40年たった原発は廃炉になる。新設は政治的に不可能なので、2030年に運転できる原発の総発電量は約2300億kWh、現在(28.6%)のほぼ半分である。これがすべて稼働しても14%程度だ。
さらに原子力規制委員会の安全審査が今のペースで続くと、動く原発はもっと少ない。川内原発(鹿児島県)の2基が今年夏にも動くといわれるが、審査申請から2年かかっている。2年で2基だから毎年1基と考えると、来年以降1基ずつ動くとすると、2030年には17基が動くことになる。これは現在の原発の総発電量の約1/3で、総発電量の10%以下だ。
つまり現在の安全審査のペースが続くと、2030年には原子力で電力の10%もまかなえないのだ。2030年にどんな目標を立てようと、原発が止まっているうちは日本のCO2排出量はその目標値を上回る。鳩山元首相が2009年に国際公約した「2020年までに1990年比で25%削減する」という目標どころか、2013年度のCO2排出量は前年度から1.6%増え、1990年より10.6%も多い。
20年以上も原発を止めて行なう原子力規制委員会の異常な安全審査が続く限り、どんな「エネルギーミックス」を計画しても絵に描いた餅である。議論の出発点として、原子力規制委員会の違法な行政指導をやめさせ、原発の運転を正常化する必要がある。
2.原発なしでCO2削減はできない
1997年、京都で開催されたCOP3で、温室効果ガスの削減を決めた京都議定書が締結され、日本の国会は満場一致でそれを批准した。しかし議定書が2005年に発効してからも温室効果ガスの削減は進まず、京都議定書は2012年で終了した。日本政府は2013年以降の議定書の延長には参加しない。「ポスト京都議定書」の体制は決まっておらず、実質的に地球温暖化対策は白紙に戻った。
鳩山氏の公約にもとづいて民主党政権は、原子力発電の比率を50%以上にするエネルギー基本計画を立てた。しかし福島第一原発事故のあと、政府は「2030年代までに原発ゼロにする」という方針を打ち出した。これは明らかに削減目標と矛盾する方針だが、民主党政権では誰もこれを是正しようとしなかった。
しかし安倍政権も政治的リスクを恐れてエネルギー政策は経産省に丸投げし、「安全性の確認された原発は再稼動する」という方針を繰り返してきた。しかし6月にドイツで開かれるサミットには、各国がCO2削減目標を持ち寄る。ここに安倍首相が手ぶらで行くわけにはいかないので、いよいよ決断を迫られるわけだ。
京都議定書の失敗でも明らかなように、不可能な理想を掲げても実現できない。大事なのは、各国の経済を悪化させない範囲で、気候変動のリスクを最適化することだ。このための方法としては、排出権取引より炭素税のほうが望ましい。たとえば炭素1トンあたり5000円の炭素税をかけると、石炭火力の発電単価はほぼ2倍になる。
現在の原発の発電単価は石炭火力とほぼ同じなので、事故の賠償保険などを発電単価に加えても、原発は化石燃料より圧倒的に安くなる。他の省エネや再エネなどのCO2削減策が成長率を低下させるのに対して、原発の発電単価は火力より低い。つまり原発は、温暖化を防ぐもっとも効率的な方法なのだ。
3.大気汚染にも配慮が必要だ
原発を止められたおかげで各電力会社は石炭火力を新設しているが、大気汚染のリスクは原子力より石炭火力のほうが大きい。WHO(世界保健機関)の調査によると、毎年世界で700万人が大気汚染で死亡しているが、その最大の汚染源が石炭だ。特に中国では、石炭による大気汚染で年間100万人が死亡しているともいわれる。
エネルギー政策は「原子力か否か」という神学論争になりがちだが、本質的には、いかに最小のコストで環境汚染を最小化するかという経済問題であり、それは価格メカニズムで行なうべきだ。再生可能エネルギーも火力や原子力と競争できるなら、固定価格買取制度などの補助金は廃止し、価格で競争すればよい。
どんな電源が効率的かは、こうした「炭素の価格」に依存する。炭素1トンあたり数万円の炭素税をかければ、原子力や再生可能エネルギーが有利になるが、それは(排出権でも炭素税でも)国民負担になる。気候変動だけでなく大気汚染なども含めた環境汚染をいくら減らすのかという目標を明確にし、その費用を明らかにした上で国民的な論議が必要である。
今までは多くの国民が原発事故でパニック状態だったので、「原発をゼロにするか否か」という問題が話題になったのもしょうがないが、原発と同様に、気候変動も多くの環境リスクの一つに過ぎない。それを個別に議論するのではなく、限られた政策資源をどう配分することが効率的か、という冷静な議論をそろそろしてはどうだろうか。
(2015年3月30日掲載)

関連記事
-
アゴラ研究所では、NHNジャパン、ニコニコ生放送を運営するドワンゴとともに第一線の専門家、政策担当者を集めてシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を2日間かけて行います。
-
「脱炭素社会の未来像 カギを握る”水素エネルギー”」と題されたシンポジウムが開かれた。この様子をNHKが放送したので、議論の様子の概略をつかむことができた。実際は2時間以上開かれたようだが、放送で
-
前稿において欧州委員会がEUタクソノミーの対象に原子力を含める方向を示したことを紹介した。エネルギー危機と温暖化対応に取り組む上でしごく真っ当な判断であると思う。原子力について国によって様々な立場があることは当然である。
-
2024年3月18日付環境省報道発表によれば、経済産業省・環境省・農林水産省が運営するJ-クレジット制度において、クレジットの情報を管理する登録簿システムやホームページの情報に一部誤りがあったそうです。 J-クレジット制
-
スマートフォン向けゲームアプリ「ポケモンGO(ゴー)」。関係なさそうな話だが、原子力やエネルギーインフラの安全についての懸念を引き起こす出来事が、このゲームによって発生している。
-
GEPRを運営するアゴラ研究所は毎週金曜日の午後9時から、インターネットの映像配信サービス、ニコニコ生放送で「アゴラチャンネル」という番組を放送している。22日は、アゴラ研究所の池田信夫所長をホスト、元経産官僚の石川和男氏をゲストにして「原発停止、いつまで続く?」というテーマで放送した。
-
影の実力者、仙谷由人氏が要職をつとめた民主党政権。震災後の菅政権迷走の舞台裏を赤裸々に仙谷氏自身が暴露した。福島第一原発事故後の東電処理をめぐる様々な思惑の交錯、脱原発の政治運動化に挑んだ菅元首相らとの党内攻防、大飯原発再稼働の真相など、前政権下での国民不在のエネルギー政策決定のパワーゲームが白日の下にさらされる。
-
ドイツの温室効果ガス排出量、前年比10%減 3月15日、ドイツ連邦政府は2023年の同国の温室効果ガス排出量が前年比10%減少して6億7300万トンになったとの暫定推計を発表した※1。ドイツは温室効果ガス排出削減目標とし
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間