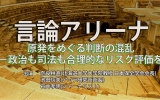原子力規制委、未熟な運用体制と欠陥(上)
(GEPR編集部より)
原子力規制委員会は、3月25日の日本原電敦賀発電所の2号機と東北電力東通原子力発電所の敷地内破砕帯について、「将来活動する可能性のある断層等」に該当するとした有識者会合の評価書を受理した。2年半の調査、評価はこれで終了し、評価書が確定した。

12年に施行された原子力の新安全基準によれば、原子炉の重要な構造物は活断層の上に建ててはならないとされており、規制委がこの評価書の意見を採用すれば、原電敦賀2号機、東北電東通1号機は事実上廃炉に追い込まれる。規制委は報告書を「重要な知見として参考にする」としており、活断層かどうかの認定は、今後両社が行う新規制基準の適合性審査で争われる。
この審査に、科学的な知見が反映されず、有識者の選定も恣意的であるなど、多くの問題があることは、これまでGEPR、アゴラで示してきた。
敦賀原発の活断層判定、再考が必要(上)対話をしない原子力規制委
敦賀原発の活断層判定、再考が必要(下)・行政権力の暴走
原子力規制委員会の活断層審査の混乱を批判する
「御用学者」を追放したらどうなったか?
今回は、政府の原子力政策をめぐる公職を務め、各国の原子力法制に詳しい石橋忠雄弁護士に、原子力規制委の行政活動について、法律論からの問題点の寄稿をいただいた。この原稿はエネルギーの論説誌エネルギーレビューの4 月号から転載をした。委員会の評価書の正式受理前の論考だが、問題点は変わらない。掲載を認めていただいた関係者の皆さまに感謝を申し上げる。
(以下本文)
原子力規制委員会(規制委)が新規制基準で、「耐震重要施設は変位を生ずるおそれがない地盤に設けなければならない」と定めたことから一昨年来、各地の原発や核燃料サイクル施設で地盤調査が行われている。
調査は規制委と電力会社等の事業者の双方から行われている。これまでのところ、事業者側の調査(または検証)は当初、旧原子力安全・保安院(旧保安院)の指示に従って実施されたりしたが、平成24年(2012年)9月に規制委が発足し、いわゆる「有識者会合」が設置されて以来、有識者会合の評価書案やそのとりまとめの方法をめぐって規制委と事業者との間で見解が対立し、大きな溝ができている。
問題は評価書案で施設の地盤に活断層の存在またはその可能性が指摘された場合、事業者側が従来のように、当局の指示に従って追従的に調査をするというのではなく、外部専門家による独自の調査を行い、評価書案と異なる資料を規制委に提出しても、これが規制委に採用されず、有識者会合の論議の対象とならない中で、評価書案のとりまとめが進んでいくことにあると思われる(注1)。
規制委側からは「議論の度ごとに新しい資料を出されると(断層評価が)終わらない」(注2)とされるのに対し、事業者側からは「一方的な決めつけであり、推論だ。反論、反証できると確信している」(注3)とか、「根拠を示していただけないので納得感が得られない。アプローチが異なり、議論がかみ合っていない」(注4)との声がでている。
このような状況の中で、昨年12 月、青森市において「エネルギー講演会 青森」(主催・東北エネルギー懇談会等)が開かれたが、地震地質学の専門家である講師からは、有識者会合は根拠なく活断層の可能性を主張しているとして「証拠にもとづく議論」が必要である、との意見が示されている(注5)。
規制委は平成24年11月、敷地内破砕帯の調査をする16名の学識経験者からなる「有識者会合」を設置し、5つの原発と「もんじゅ」の調査に四名ずつ分担配置した。規制委によると、これらの有識者は、日本活断層学会等、国内の地震や地質関係の学会の内、四つの学会から推薦をうけた専門家であるという(注6)。
そして4名の有識者らがまとめた評価書案は、4名を除いた12名の有識者による「ピア・レビュー」を行うとしていたが、これは「当該破砕帯の再評価をするのではなく、評価書案をより良いものとすることを目的とする」としている(注7)。そうだとすれば4名の有識者は実際に現地に入り、敷地内で破砕帯の調査をして活断層の有無(またはその可能性)の調査をした上で評価書案をまとめているのであるから、それが規制委において新基準適合審査の判断に大きな影響を与えることになると思われる。
筆者は本稿を執筆するにあたり、原子力基本法、規制委設置法、同組織令、同組織規則、原子炉等規制法(規制法)をみてみたが、「有識者」についての規定はなかった。そうすると、改めてそもそも「有識者」または「有識者会合」とは一体、何なのか、換言すると、規制委が法的に何の根拠もない「有識者」を任意選任し、「有識者会合」を設置して、現地調査や評価書作成の任務を与えていいのか、ということが問われなければならない。
3条行政委員会の意義-「有識者」は法令に根拠せず
有識者会合が法令上の根拠をもたない存在である以上、前述のような有識者会合の問題は規制委が国家行政組織法第三条二項の規定にもとづいた、講学上いわゆる三条行政委員会(三条委)であるという視点から検証されなければならない。
三条委員会が「設置される目的ないし理由は…その所掌事務の性質に基づく」が「公正かつ慎重な判断に基づいて処理せしめることが委員会制度の目的」であるとされる(注8)。規制委設置法第一条によると、規制委は「原子力利用における安全の確保を図る」ことを目的として発足したが、「専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使」しなければならないのである。これが故に規制委は三条行政委員会であるとされる。
ところで現在、三条委は規制委のほか、公害等調整委員会等四委員会があり、また平成一一年の内閣府設置法の制定に伴って内閣府の外局となった公正取引委員会等四委員会・庁も講学上、三条委であるといわれる(注9)。
三条委の所掌事務は例えば警察庁を管理する国家公安委員会から労使の利害を調整する中央労働委員会まで各々、独自性をもっていて分類になじむものではないが、民間事業者の経済活動を規制するという点では規制委は公正取引委員会や公害等調整委員会と性格が似ている。その場合、三条委は身分や権限について府省から独立した地位を与えられているが、それ故にその身分、権限も絶対的なものではなく、職権の発動は「中立公正な立場」でなければならず、単に「専門的な知見」に基づいて判断すればよいというものではない。
しかし「中立公正」といっても抽象的な文言にすぎず、これを具現し、担保する条件が制度化されているのでなければ意味がない。その点で現今の有識者ないし有識者会合は次の二つの点で「中立公正な立場で独立して職権を行使する」という規制委設置法第一条に違反する存在であると考える。
その一つは、そもそも有識者または有識者会合は規制委に係わる諸法令上の根拠がなく、従って法令上、秘密の保持義務等もなく、自らの言動に責任もない者である(注10)。規制委設置法によると、規制委員は身分保障があると同時に公正中立を保つための様々な服務規律が課せられている。有識者は新基準に適合するか否かの調査と評価を行うのであるから、実質的な審査に参加しているにも拘らず、三条委に求められている高い倫理性、信頼性、独立性という要件に欠け、従って中立公正とはいえない存在なのである。
以下(下)に続く。
(注)
1・例えば日本原子力発電は平成27年(2015年)1月6日、「敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合ピア・レビュー会合で出されたご意見の整理について」を公表したが、その中で「ピア・レビューの専門家の方々から出された評価書(案)の根幹に係る数多くのコメントや、当社が今までに提示した調査結果にもとづく観察事実、科学的データ等を十分に勘案して、評価書(案)を見直して頂くよう、強く求めたい」とした上で評価書(案)につき63箇所の問題点を指摘している(日本原子力発電ホームページ)
2・産経新聞・2014年10月13日、委員長代理の発言
3・朝日新聞・2014年11月20日、日本原電市村泰規副社長の発言
4・東奥日報・2014年12月13日、東北電力佐藤敏秀青森支店長の発言
5・東奥日報・2014年12月23日、首都大学東京山崎晴雄大学院教授の発言
6・16名の有識者がどの施設の担当になるのか、割り振りの理由、根拠は示されていない。因みに、原電敦賀発電所については4名の有識者の内、3名が変動地形学者である
7・原子力規制委員会の平成25年3月8日「ピア・レビューの具体的実施方法」、原子力規制庁の平成26年10月1日「敷地内破砕帯の評価に関するピア・レビュー会合の座長の交代について」
8・佐藤功・行政組織法(新版)・有斐閣法律学全集212頁
9・なお国税庁や消防庁等はその所掌事務は本来、府、省の事務であるが、その裏が厖大であることから他の局とバランスを失するので独立して設けられたものであり、所掌事務の質的な理由に基づくのではないから外局ではあっても三条委員会ではない(佐藤功・前掲書209頁)
10・因みに規制委設置法は三つの審議会と緊急事態応急対策委員の設置を定め、各々、専門委員が委嘱されている
石橋忠雄 青森弁護士会所属弁護士。石橋法律事務所代表。中央大学法学部卒、日弁連公害対策環境保全委員会原子力部会長、原子力委員会高レベル放射性廃棄物処分懇談会委員、原子力研究・開発・利用長期計画策定会議委員などを務め、日米欧の原子力施設を調査し、米国にて原子力法制の調査・研究に携わるなど経て、現在に至る。
(2015年3月30日掲載)

関連記事
-
2023年4月15日(土曜日)、ドイツで最後まで稼働していた3機の原発が停止される。 ドイツのレムケ環境大臣(ドイツ緑の党)はこの期にご丁寧にも福島県双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪れ、「福島の人々の苦しみ
-
欧州のエネルギー環境関係者とエネルギー転換について話をすると、判で押したように「気候変動に対応するためにはグリーンエネルギーが必要だ。再生可能エネルギーを中心にエネルギー転換を行えば産業界も家庭部門も低廉なエネルギー価格
-
10月22日、第6次エネルギー基本計画が7月に提示された原案がほぼそのままの形で閣議決定された。菅前政権において小泉進次郎前環境大臣、河野太郎前行革大臣の強い介入を受けて策定されたエネルギー基本計画案がそのまま閣議決定さ
-
以前書いたように、再生可能エネルギー賦課金の実績を見ると、1%のCO2削減に1兆円かかっていた。 菅政権が26%から46%に数値目標を20%深堀りしたので、これは年間20兆円の追加負担を意味する。 20兆円の追加負担は現
-
16年4月29日公開。出演は原子力工学者の奈良林直(北海道大学大学院教授・日本保全学会会長)、経済学者の池田信夫(アゴラ研究所所長)、司会は石井孝明(ジャーナリスト)の各氏。4月の九州地震、3月には大津地裁で稼動した高浜原発の差し止めが認められるなど、原子力の安全性が問われた。しかし、社会の原子力をめぐるリスク認識がゆがんでいる。工学者を招き、本当のリスクを分析している。
-
東京電力福島第一原発の直後に下された避難指示によって、未だに故郷に帰れない避難者が現時点で約13万人いる。
-
3月10日から久しぶりに米国ニューヨーク・ワシントンを訪れてきた。トランプ政権2.0が起動してから50日余りがたち、次々と繰り出される関税を含む極端な大統領令に沸く(翻弄される)米国の様子について、訪問先の企業関係者や政
-
自民党の岸田文雄前首相が5月にインドネシアとマレーシアを訪問し、「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」の推進に向けた外交を展開する方針が報じられた。日本のCCUS(CO2回収・利用・貯留)、水素、アンモニアなどの
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間