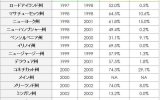地球環境は経済問題『地球温暖化とのつきあい方』

地球温暖化とのつきあいかた [単行本]
杉山大志
ウェッジ
★★★☆
著者はIPCCの統括執筆責任者なので、また「気候変動で地球が滅びる」という類の終末論かと思う人が多いだろうが、中身は冷静だ。人類の出すCO2が原因で地球が2100年までに2~4℃温暖化するというIPCCの予想が正しいとしても、その生態系への影響は、人類のやっている地球環境の破壊に比べれば大したことはないという。
ほとんどの報道はIPCC第5次報告書のSPM(政策決定者むけ要約)にもとづいているが、これはマスコミ受けをねらって誇張されている。たとえばSPMには、2100年までに地球の平均気温が2℃上がると多くの動植物が絶滅するかのような図が描かれているが、人類が1970年から今まで行なってきた大規模な環境破壊は、4℃以上の気温上昇に匹敵する。
もちろんこれは、温暖化を放置してもいいということではない。CO2の排出量を抑制する努力は必要だが、日本はすでに世界一の省エネ先進国である。残るのは再生可能エネルギーの固定価格買取のような高コストの対策だが、こういう方法でCO2を1%減らすには約1兆円かかるという。
だから今後、日本政府がCOP21に向けて2030年までのCO2の削減目標を出すとき必要な予算は、EU並みに1990年比40%の削減を行なうには57兆円、アメリカ並みに2005年比で30%としても36兆円かかることになる。これを15年で割っても、EU並みの対策を実施するにはGDPの1%近いコストがかかる。
環境保護派は「省エネでコストが下がる」とか「環境投資で成長できる」などという夢を振りまくが、日本ではそういう低コストの温暖化対策はやり尽くしているので、残っているのは経済的にマイナスになる対策だけだ。唯一経済的にプラスになる温暖化対策は、原発を再稼動することである。
地球温暖化は、こうした環境と成長のトレードオフで考える経済問題なのだ。政府では「20%台の削減目標」という方向で調整が行なわれているようだが、これだとコストは20兆円以上かかる。環境政策の目的はCO2濃度ではなく、快適な生活を守ることだ。今後マイナス成長になる日本で、さらに成長率を下げる環境政策に、国民の合意は得られるのだろうか。
(2015年4月27日掲載)

関連記事
-
昨年3月11日以降、福島第一原子力発電所の事故を受け、「リスクコミュニケーション」という言葉を耳にする機会が増えた。
-
国土交通省の資料「河川砂防技術基準 調査編」を見ていたら印象的な図があった。東京の毎年の1日の降水量の最大値だ。 ダントツに多いのが1958年。狩野川台風によるものだ。気象庁ホームページを見ると372ミリとなっている。図
-
割高な太陽光発電等を買い取るために、日本の電気料金には「再生可能エネルギー賦課金」が上乗せされて徴収されている(図)。 この金額は年々増え続け、世帯あたりで年間1万円に達した注1)。 これでも結構大きいが、じつは、氷山の
-
経産省は高レベル核廃棄物の最終処分に関する作業部会で、使用ずみ核燃料を再処理せずに地中に埋める直接処分の調査研究を開始することを決めた。これは今までの「全量再処理」の方針を変更する一歩前進である。
-
米国における電力自由化の失敗例としては、電力危機を引き起こしたカリフォルニアの事例が有名である。他方、成功例としてテキサス州があげられることがある。
-
オーストラリアの東にあるグレートバリアリーフのサンゴ礁は絶好調だ。そのサンゴ被覆度(=調査地域の海底面積におけるサンゴで覆われた部分の割合)は過去最高記録を3年連続で更新した(図)。ジャーナリストのジョー・ノヴァが紹介し
-
6月21日記事。ドイツ在住の日系ビジネスコンサルタントの寄稿。筆者は再エネ拡充と脱原発を評価する立場のようだが、それでも多くの問題を抱えていることを指摘している。中でも電力料金の上昇と、電力配電系統の未整備の問題があるという。
-
GPIFがサステナ投資方針を月末公表へ、ESGの姿勢明確化―関係者 ブルームバーグ 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、サステナビリティー(持続可能性)投資に関する方針を初めて策定し、次期基本ポートフォリオ(資
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間