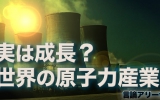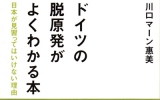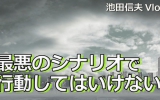IAEA、福島事故最終報告書を発表
IAEA(国際原子力機関)は8月31日、東京電力福島第一原発事故を総括する事務局長最終報告書を公表した。ポイントは3点あった。
第1に事故の主な要因として日本の原子力関係者に「日本に原発が安全だという思い込みがあり備えが不十分だった」と指摘した。第2にこの知見を取り入れた対策の徹底を、世界の関係者に求めた。第3に福島と日本の市民の健康については、これまでのところ事故を原因とする影響は確認されていないと確認し、報告された被ばく線量が低いため、健康影響の発生率が将来、識別できるほど上昇するとは予測されないとしている。
この報告書は、40を超える加盟国からおよそ180人の専門家が参加してまとめ、1200ページ以上になる。
この中でIAEAは、事故の主な要因として「日本に原発は安全だという思い込みがあり、原発の設計や緊急時の備えなどが不十分だった」「責任がいくつもの機関に分散し、権限の所在が明確でなかった」と指摘。複数の原子炉の事故、自然災害の同時発生、全電源喪失の想定と事前対策が、東京電力と規制当局になかったとしている。一方で、事故後に規制権限の強化などの改善がみられたとも評価した。
その上で加盟各国にIAEAの勧告に基づく安全な原子力の活用を求めた。そしていくつかの自然災害が同時に発生することなどあらゆるリスクを考慮する、基準に絶えず疑問を提起して定期的に再検討するなど、「安全文化」と呼ばれる関係者の態度が必要と提言している。
また福島の甲状腺検査で異常が見つかったことには、事故と関係づけられる可能性は低く、この年代の子どもたちの自然な発生を示している可能性が高いと分析。一方で、住民の中には、不安感やPTSD=心的外傷後ストレス障害の増加など、心理面での問題があったと指摘しており、その影響を和らげるための対策が求められると強調している。
リンク・「IAEA福島第一原子力発電事故・事務局長報告書 巻頭言及び要約」(日本語版)
(2015年9月7日掲載)

関連記事
-
2015年7月15日放送。出演は村上朋子(日本エネルギー経済研究所研究主幹)、池田信夫(アゴラ研究所所長)、石井孝明(ジャーナリスト)の各氏。福島原発事故後、悲観的な意見一色の日本の原子力産業。しかし世界を見渡せば、途上国を中心に原発の建設が続く。原子力産業の未来を、最新情報と共に考えた。
-
【記事のポイント】1・一つのリスクを減らすと他のリスクが高まる「リスク・トレードオフ」という現象が起こりがち。2・「絶対反対」の主張を政治的な運動体は好む。しかし現実を動かさない。3・原発事故後に政府の対策はリスクの分析をせず、誰もが責任から逃げている。
-
自民党は「2030年までに温室効果ガスの排出量を2013年度比で26%削減する」という政府の目標を了承したが、どうやってこの目標を実現するのかは不明だ。経産省は原子力の比率を20~22%にする一方、再生可能エネルギーを22~24%にするというエネルギーミックスの骨子案を出したが、今のままではそんな比率は不可能である。
-
産経新聞、4月18日記事。政府は18日、原発再稼働の条件である審査を担う原子力規制委員会の委員長に更田(ふけた)豊志委員長代理(59)を昇格させるなど、国会同意が必要な12機関28人の政府人事案を衆参両院の議院運営委員会理事会に提示した。
-
西浦モデルの想定にもとづいた緊急事態宣言はほとんど効果がなかったが、その経済的コストは膨大だった、というと「ワーストケース・シナリオとしては42万人死ぬ西浦モデルは必要だった」という人が多い。特に医師が、そういう反論をし
-
いろいろ話題を呼んでいるGX実行会議の事務局資料は、今までのエネ庁資料とは違って、政府の戦略が明確に書かれている。 新増設の鍵は「次世代革新炉」 その目玉は、岸田首相が「検討を指示」した原発の新増設である。「新増設」とい
-
2017年1月からGEPRはリニューアルし、アゴラをベースに更新します。これまでの科学的な論文だけではなく、一般のみなさんにわかりやすくエネルギー問題を「そもそも」解説するコラムも定期的に載せることにしました。第1回のテ
-
米国ではスリーマイル島事故などの経験から、原子力の安全規制は大きく改善されてきている。日本の原子力規制委員会(以下「規制委」)も、規制の仕組みを改善してきたNRC(アメリカ合衆国原子力規制委員会: Nuclear Regulatory Commission)を参考にして、現在の独善的な審査の仕組みを早急に改めるべきである。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間