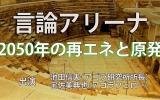私の提言-総集編(下)
原子力事業環境、整備の必要性
こうした環境変化に対応して原子力事業を国内に維持するには、個別施策の積み重ねではなく、総合的なパッケージとなる解決策を示す必要がある。その解決策として出した提案の柱の第一は、民間主導でのリプレースが行われることであり、そのための資金調達が可能となる事業環境整備である。
原子力技術を維持し、これを効率的・安全に使うという観点から主体を考えると、民間事業者によるリプレースを可能にすることが制度設計の出発点となった。
あわせて第二に、使用済み燃料の処理や廃炉以降最終処分に至る、いわゆるバックエンドは、国主導の体制に移行させていくべきであると考えた。基本的にバックエンド事業は収益を生む構造になく、また、相当長い期間安定的に事業を担いうる主体が行う必要があるためだ。
第三に、原子力の安全規制を合理的なものにしていかねばならない。国民負担による大きな投資を行った経済的資産である原子力発電設備を安全に運転し、豊富低廉な電力供給を可能にするためには、合理的な安全規制の制度設計が必要となる。そのうえで、賠償制度の見直し、地域コミュニティ崩壊という特殊な被害に対応する、賠償制度とは別の施策の構築など、事故リスクの対策が必要となる。
これら原子力事業に関する課題の総合的な解決フレームとして原子力事業環境整備法案を提示したのが、「原子力事業環境・体制整備に向けて」(注4・21世紀政策研究所パンフレット)である。原子力技術を日本に維持するための必要条件の整理と、そのためにはどこまで目配りをすればよいかを書いたこの政策提言は、不透明性に覆われ立ちすくんでいた原子力事業を、我が国において維持することを提示するための総合的な解を示したものであり、今後の羅針盤となりうるものと自負している。
核燃料サイクル政策をどうするべきか
次に我が国の原子力政策の最大のボトルネックと言っても過言ではない、核燃料サイクル政策の改革に向けての提言「核燃料サイクル政策改革に向けて」を示した。(注5・21世紀政策研究所パンフレット)
この提言は、時間的にある程度余裕のある最終処分についてではなく、廃炉や中間貯蔵、再処理、プルトニウム利用問題などより喫緊に検討が必要な課題に焦点を当てたものである。
国策としてこれまで我が国が推し進めてきた核燃料サイクル政策は、あまりに大きく、そしてそれぞれの施策が密接に関わりあっており、一つの施策の成功が他の施策の前提になっていることも多くある。そのため、その一部でも見直そうとすれば大きなきしみが生じるため、これまでいくつものほころびがあったものの、全体としての見直しが議論されることなく既定路線を継続するという判断が繰り返されてきた。
しかしここに前述したような原子力事業を取り巻く環境の大きな変化が起これば、それでなくとも行き詰っていた政策が破たんに至ることは明らかであると言えよう。改革に向けての必要な視点として①政策責任の所在の明確化、②原子力事業の外部不経済性を正当に評価し、それを内部化するための政策措置、③国際的な説明責任が果たせること、④これまでの歴史的経緯を十分に踏まえること、しかし必要があれば方針を変更せざるを得ない局面を覚悟し、地元自治体や住民と真摯に向き合うこと、⑤技術の継承といった5つのポイントを整理し、実現すべき政策目標、現実的な制約要因と解決すべき課題など、今後描くべき設計図に必要なものをすべて洗い出したつもりである。
「原子力発電はトイレ無きマンション」などと言ってため息をついているだけでは、わが国がこれまで享受してきた豊富低廉な電力の結果生まれた放射性廃棄物の問題は解決しない。現世代の責任として核燃料サイクル政策を改革する道筋を本気で考える必要があり、その議論に必要な視点はすべてここに集約したつもりである。
原子力安全規制の改革
最後に取り組んだのが安全規制の改革である。事業環境の整備がよしんばうまくいったとしても、原子力技術に対する国民の信頼が回復されなければ、その利用は適切に行われない。
事故によって失われた信頼回復を急ぐあまりにであろうか、規制者も事業者も共に態度が硬直化しているように見えた。まずは事故後導入された新たな規制活動の問題点を整理したうえで、規制者、事業者それぞれに求められる取り組みについて明らかにしようと考えたのである。
安全規制を語るうえで最も重要な「予見可能性」を確保するためには、法的にこれを明確化する必要がある。そのため、具体的に原子炉等規制法の改正条文案まで含めた「原子力安全規制の最適化に向けて-炉規制法改正を視野に」(注6・21世紀政策研究所パンフレット)を発表した。
安全規制は何のために行われるかと言えば、原子力を安全に稼働させるためである。原子力を停止させるためではなく、当然のことながら原子力技術の安全性向上に寄与しなければならない。安全性向上にゴールは無いという認識を関係者が共有したうえで、向上させ続ける仕組みを具体的に提案したつもりである。
しかし、安全規制に最も重要な哲学を語るという点において、この時の報告書では十分にできたとは言いがたい。もう二度と福島原子力事故のような事態が引き起こされることがないよう、安全規制に魂を込める必要性がある。そのため、この続編として「続・原子力安全規制の最適化に向けて-原子力安全への信頼回復に向けて」(注7・6・21世紀政策研究所パンフレット)を発表した。ここにおいては、規制哲学の確立と共有に向けて必要なエッセンスを8つ指摘している。
事業者や規制委員会・規制庁、政府・国会関係者やその他原子力の安全性向上について関心と熱意を持つ方々と共有したい危機感、本質的な問題点について指摘したものである。この報告書が各関係者の共通理解の醸成と原子力安全の向上につながることを切に願っている。
原子力と世論の関係
パズルはこれで終わりではない。この安全規制の哲学が関係者だけでなく、広く一般国民にも理解される必要がある。安全規制の哲学とはすなわちリスクというものに対する考え方そのものであるからだ。一般国民、特に立地地域における原子力技術に対する合意形成のプロセスやリスクコミュニケーションについて今後も研究を深めたいと思っており、竹内研究員が現在取り組んでいる川内原子力発電所再稼働プロセスを例にとった研究も踏まえてさらに進化させたい。原子力事業の再編も課題だ。
考えなければならない課題は山積している。今後への見通しを少し述べておけば、政府は規制委員会の安全審査に合格した原子力発電所の再稼働は進めていくことを明言しているものの、そこには地元合意を得ることが必要となる。
すべての原子力発電所立地地域に対して政府が事故時のリスク(賠償、事故対応)に対してこれまでよりも積極的な役割を果たすことを丁寧に説明していく必要がある。
再稼働を待つ原子力発電所の中でも最も厳しいハードルを越えなければならないのは、新潟県の柏崎刈羽原子力発電所であろう。事故を起こした東京電力がどこまでその安全に対する取り組みを向上させる仕組みを構築し、地域から理解を得る努力をどこまで進められるか。全国知事会危機管理・防災特別委員長を務める新潟県泉田知事から了解を得ることができれば、その後の再稼働プロセスの大きな参考となるだろう。東京電力には必死の努力を期待したい。
また電力システム改革を契機に、ぜひ電力会社には民間事業者としての野性味を取り戻してもらいたい。安定供給に対する矜持に安住することなく、民間の活力を電力事業者が取り戻すことができなければ、システム改革という外科手術をする意味がそもそも無に帰すことを、心に刻んでもらいたい。
エネルギー問題は公益の最たるものである。筆者がしばしば「インフラ中のインフラ」という言葉を使って表現してきた通り、国民生活や産業の基盤であり、極めて現実的に議論されねばならない。すでに公僕たる立場を離れて長い筆者ではあるが、公益に尽くす情熱は捨てがたく、混乱するエネルギー政策を立て直す議論に貢献すべく心血を注いできたつもりである。理想論や対症療法の積み重ねでなく、わが国のエネルギー政策が広い視野に基づく新たな思想理念を構築することに今後も微力ながら尽くしていきたいと考えている。
しかしながら、自身の健康管理不行き届きにより、しばらくこうした提言活動から身を引き、療養に専念せざるを得ない状態となってしまった。今回のブログは、これまで描いてきた構想の整理をして皆様にお伝えしたいと考えたものである。
しばらくこのブログの更新が滞ってしまうであろうことをお詫びするとともに、その間も変わらずこの国際環境経済研究所へのご支援をお願い申し上げます。皆様も健康第一でお過ごしください。皆様にとって2016年が良き年となりますように。
(2016年1月18日掲載)(IEEI掲載は1月4日)

関連記事
-
G7気候・エネルギー・環境大臣会合がイタリアで開催された。 そこで成果文書を読んでみた。 ところが驚くことに、「気候・エネルギー・環境大臣会合」と銘打ってあるが、気候が8、環境が2、エネルギー安全保障についてはほぼゼロ、
-
トランプ次期政権による「パリ協定」からの再離脱が噂されている中、我が国では12月19日にアジア脱炭素議員連盟が発足した。 この議連は、日本政府が主導する「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」構想をさらに推進させ、
-
はじめに リスクはどこまで低くなれば安心できるのだろうか。泊原子力発電所は福一事故後7年も経ったのにまだ止まったままだ。再稼働できない理由のひとつは基準地震動の大きさが決っていないことだという。今行われている審査ではホモ
-
映画好きのAさんは最近、自宅に大画面テレビとホームシアターの設備を備えつけた。「大型テレビは電気の消費が増えるからエコじゃないね」と友人に揶揄されたAさん、「我が家の大画面テレビの電気は、北海道の稚内にある風力発電所から届いたものなんだよ」と得意気だ。
-
日本の電気料金は高騰を続けてきた。政府は、産業用及び家庭用の電気料金推移について、2022年度分までを公表している。 この原因は①原子力停止、②再エネ賦課金、③化石燃料価格高騰なのだが、今回は、これを数値的に要因分解して
-
1月17日付日経朝刊に、日本原子力発電株式会社の東西分社化検討の記事が載っていました。 同社は、日本が原子力発電に乗り出した1950年代に電力各社の出資によって設立されたパイオニア企業で、茨城県東海村と福井県敦賀市に原子力発電所を持っており、他の電力会社に電気を卸しています。
-
「インフレ抑止法」成立の米国・脱炭素の現状 8月16日、米国のバイデン大統領は、政権の看板政策である気候変動対策を具体化する「インフレ抑止法」に署名し、同法は成立した。 この政策パッケージは、政権発足当初、気候変動対策に
-
言論アリーナ「2050年の再エネと原発」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 経産省は2050年に向けてのエネルギー戦略を打ち出しました。そこでは再エネがエネルギーの中心に据えられていますが、果たして再エネは主役に
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間