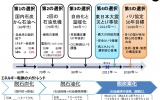原子力停止、石炭火力縮小、洋上風力推進で、いったい何兆円かかるのか
菅首相の所信表明演説を受けて、政府の温暖化対策見直しの作業が本格化すると予想される。いま政府の方針は「石炭火力発電を縮小」する一方で「洋上風力発電を拡大」する、としている。他方で「原子力の再稼働」の話は相変わらずよく見えない。

北九州市沖の洋上風力発電(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構サイトより:編集部)
話が複雑なことは百も承知で、「それで一体幾らお金はかかるのか?」という、シンプルだが重要な問いに、最もシンプルな概算で答えよう。
以下では、「2030年代のある1年」を想定して費用を概算する。
データとしては、透明性・再現性の観点から、一貫して政府資料を用いる。なお計算の詳細については研究ノートにまとめてあるので参照されたい。
1 原子力が再稼働しないことのコスト
原子力発電は9月末現在、合計で3308万kWあった。このうち稼働中は僅か441万kWで、残りの2867万kWは停止中である。これを再稼働すると、必要な燃料費は3391億円である一方で、発電される電力には2兆6223億円の価値がある。差し引き、再稼働しないことで、年間2兆2832億円の便益が失われている。
2 非効率石炭火力の9割減のコスト
日本政府は非効率な石炭火力発電の縮小について検討している。具体的な規模についてはその結果を待つことになるが、一部の報道にあるように、仮にその9割が削減されるならば、どうなるか。
対象となっている非効率石炭火力の発電電力量は 1650億kWhである。この9割は1485億kWhである。既設の発電設備なので、これで発電するための最低限の費用は燃料費と運転維持費の合計であり、それは政府資料によれば6.8円/KWhとなる。
この費用を、発電される電力の価値から差し引くと、「非効率石炭火力の9割減」で失われる便益は年間7128億円となる。
3 洋上風力1000万KWのコスト
日本政府は洋上風力発電の拡大についても検討している。そこでは、2030年までに1000万KWという目標が言及されている。これは幾らかかるだろうか。
洋上風力の発電コストは高く、政府資料では30.3~34.7円/kWhとなっている。
1000万KWを建設すると発電コストは年間8541億円となる。他方で発電される電力の価値は2628億円しかない。
両者を差し引くと、5913億円となる。つまり洋上風力1000万kWの建設によって年間5900億円が失われる。
4 おわりに
以上の試算に沢山のご意見があることはよく承知している。だが、敢えて数字を示すのは、結論というよりは、問題の規模感を示すこと、及び、注意喚起の為である。
明らかに、原子力の再稼働の便益は巨大である。石炭火力の廃止のコストも大きい。洋上風力も、相当なコストダウンが実現しないと、新たなコスト要因になってしまう。
既に再生可能エネルギーの賦課金は年間2.4兆円を超え、増え続けている。今後も政策が原因でエネルギーコストが嵩んでゆくと、日本経済へのダメージはますます大きくなってしまう。

関連記事
-
経済産業省において「エネルギー情勢懇談会」の提言が4月13日にまとめられた。現在政府が策定した長期のエネルギー政策としては、2014年に策定したエネルギー基本計画があり、ここでは主として2030年のエネルギーミックス目標
-
新ローマ教皇選挙(コンクラーベ)のニュースが盛り上がる中、4月30日付の「現代ビジネス」に川口マーン恵美さんが寄稿された記事「ローマ教皇死去のウラで~いまドイツで起きている『キリスト教の崩壊』と『西洋の敗北』」を読んでい
-
EUのエネルギー危機は収まる気配がない。全域で、ガス・電力の価格が高騰している。 中でも東欧諸国は、EUが進める脱炭素政策によって、経済的な大惨事に直面していることを認識し、声を上げている。 ポーランド議会は、昨年12月
-
規制委の審査、判断の過程はそれによって不利益を受ける側の主張、立証の機会が法律上、手続的に保障されていないのである。従って規制委ないしは有識者会合において事業者側の資料の提出を受けつけなかったり、会合への出席や発言も認めなかったりしても形式上は何ら手続き違反とはならないという、おかしな結果になる。要するに対審構造になっていないのである。
-
先日紹介した、『Climate:The Movie』という映画が、ネット上を駆け巡り、大きな波紋を呼んでいる。ファクトチェック団体によると、Xで150万回、YouTubeで100万回の視聴があったとのこと。 日本語字幕は
-
スウォーム(swarm)とはウジャウジャと群れる・・・というイメージである。 スウォームについては、本稿「AIナノボットが核兵器を葬り去る」にて論じたことがある。 今回はスウォームのその後の開発展開とその軍事的意味合いに
-
トランプ途中帰国で異例のG7に 6月16-17日にカナダのカナナスキスで開催されたG7サミットは様々な面で異例のサミットとなった。トランプ大統領はイラン・イスラエル戦争によって緊迫する中東情勢に対応するため、サミット半ば
-
監督:太田洋昭 製作:フィルムボイス 2016年 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から5年間が過ぎた。表向きは停電も電力不足もないが、エネルギーをめぐるさまざまな問題は解決していない。現実のトラブルから一歩離れ、広
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間