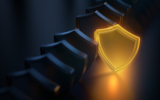大学が抱える諸問題を考える
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智
前稿で、現代の諸問題について現役の学者・研究者からの発言が少ないことに触れた。その理由の一つに「同調圧力」の存在を指摘したが、大学が抱えている問題はそれだけではない。エネルギーの問題からは少しずれるが、大学問題は重要なのでこの機会に論じておきたい。

Designalicious/iStock
現役の大学教員の多くが発言しない大きな理由として、彼らが目前の仕事に追われ続けて時間がないことが挙げられる。世間の人々の中には、大学のセンセイなんて、ヒマを持て余しているんじゃないの・・?と思っている方も多いかも知れないが、実情は大きく違う。筆者は理科系、特に工学部しか知らないが、理系教員はとにかく忙しい。筆者も現役時代は、土日でも最低限午前中は研究室にいた。平日は授業・学生の面倒見・各種会議・研究費稼ぎ等々に追いまくられているので、借金のように溜め込んだ仕事(依頼原稿や論文書き等)を少しでも消化するには、土日休日を使うしかなかったからである。もちろん、労働基準法の定める1日8時間、週40時間労働など、守りようもなかった(今だから言えるが)。むろん、休日・残業手当などは裁量労働制の教員には出ない。
なぜそんなにも忙しいかと言えば、大学教員が常に「評価」にさらされているからである。誰を昇進や昇給させるかを決めるために、大学では「業績評価」が行われている。そのためのデータ取得や大学の宣伝のために、半年に一度、各教員がどんな仕事をしたのかを自己申告することになっている。書いた論文、稼いだ外部資金(科研費や各種プロジェクト、共同研究など)、学会発表やTV新聞報道への露出回数などが主な評価指標で、担当授業や指導学生数などの教育関連も申し訳程度に評価項目に入っているが、実質的な比率はごく小さい。また理系では著作もほとんど評価されない(分担執筆が多いこともある)。
助教→准教授→教授と進む昇進レースでは、論文数が圧倒的に大きな因子となる(有名人や高級官僚等がいきなり「教授」になる例は除く)。また、最近はどんな学術雑誌に載った論文であるかが重視され、その雑誌のインパクトファクター(IF)も記載することになっている。IFは英語論文誌の影響力の指標とされており、様々な批判を受けながらも、業績評価に使われることが多い。特に問題なのは、IFはあくまでもその雑誌自体の評価であるのに、現実には載った雑誌のIFでその論文が評価されてしまうことである。
これはある意味必然とも言える。昇進のための資料には、論文リストと主要論文コピー5部ほどが付されるのが通常だが、審査委員の全員が候補者全員の全論文を精査することなど、まず無いと思う。審査委員とて、そんなにヒマじゃないからだ。また、専門分化が極度に進んでしまった現状では、ほんの少し分野が異なると、専門論文を読んでも理解するのが難しくなっている。勢い、論文の中身ではなく「数」で評価することになり、論文誌の質の客観的指標としてIFが多用される事態となる。
論文「数」が重視されると、必然的に起こるのは、共同研究の増加である。つまり、複数の研究者が相互に研究内容を分担し、論文発表時には共著者として名前を連ねることになる。最近の学術論文で、著者名がやたらに多い例がたくさんあるのは、その証拠である。1つの論文が、複数の研究者の論文リストに載ることになるから、オイシイのである。筆者のように一人で研究してきた者は、その点で不利を免れなかったが、論文数を稼ぐための共同研究には気が進まず、結局ほとんどやらずに定年を迎えた。その結果、筆者の論文リストでは論文数自体も多くはないが、全体に著者数が少ない(1〜4人以内)。論文の大半は自分一人で一字一句書き、共著者はほぼ全員実験してくれた学生たちである。
また、この研究業績偏重主義は、教育活動にも悪い影響を与える。授業や学生指導にどれだけ労力を割いても、それらはほぼ評価されない。評価そのものが難しい面もあり、教育活動の評価指標としては、担当授業本数や博士課程学生数などしかなく、結局ここでも「数」主義が評価結果を支配する。学生の「指導」として、卒論や修論研究でたくさんの実験をさせ、より多くデータを出した学生を可愛がる、と言ったことも普通になる。学生は要するに兵隊さん、戦力と心得る教員が出てくる(世に言う「ブラック研究室」)。特に、任期が期限付きの教員にとっては、目の前の結果を出すことが全てとなり、そのために指導学生を「育てる」などは眼中になく、徹底的にこき使うことしか考えなくなる。それが「アカデミック・ハラスメント(アカハラ)」の温床になる。教員間にも「あいつが講義に熱心なのは研究がパッとしないからさ」と言った風潮が生まれる。本当は、充実した講義には活発な研究活動が必須であり、両者は車の両輪であるのだが。
こうした事態が、高等教育機関であるべき大学によろしくないことは、誰でも分かるし、特に大学上層部にとっては、大学の存在意義に関わる深刻な問題であることは真面目に憂慮されているのであるが、現場の教員たちとしては、目の前の自分の「業績」を積み上げることしか考えられない、キレイゴトを言うヒマは無いと言うのが、多くの場合本音である。
もう一つの側面として、現役の中堅以下の教員たちは、いわゆる「教養部」廃止後に大学教育を受けてきた世代であることにも、要因の一つがあると思う。これら若い世代の教員たちと話をすると、全体に話題の範囲が狭く、知的好奇心を刺激されるような会話が少ない印象を受ける。頭の中が、目前の研究成果や研究費申請内容等で一杯になっており、世の中がどうなっているのか等の問題に真剣に向き合えないのではないかと推測する。いわゆる「教養・知性」を感じさせる若い世代が少ないと言うべきか。しかしそれは、単に若い世代だけでなく、日本社会全体にまん延する風潮でもある。知性や教養の何たるかを知らずに冷笑する「反知性主義」の横行がそれを示す(教養のない人間ほど教養をバカにする)。スマホをいじくるだけでは、知性は育たない。
科学(サイエンス)の追究には、世の中を無視して済む面がある。役に立つ・立たないを指標にしない真理探求が本質であるから。しかし、工学(テクノロジー)は違う。工学・技術は世の中で使われるのであり、社会にとってどんな技術が求められているかを敏感に見極める必要がある。もちろん、基礎研究の中には、目前の応用を視野に入れないものもあり得るとしても、工学研究であれば最終的な応用面を視野に入れない研究は考えにくい。そのためには、今、世界は世の中はどうなっているのかを正確に把握しなければならない。地球環境・資源エネルギー・廃棄物処理・情報通信・交通・食料・生命科学・人口関連(少子高齢化、健康栄養等)など様々な分野で今後開発が必要な技術がたくさんある。AIや情報技術が進めば万事解決、とはならない。その中で何を追究すべきを決めるには、広い視野と深い洞察力が要るはずである。今の若い研究者たちは、そうした問題意識をお持ちだろうか?もしその種の素養がなければ、軍事研究にも抵抗感なく取り組むことにもなるだろう(詳説しないが、それは学問研究自滅への道である)。
教養部廃止や独立法人化などの「大学改革」以後、全国の大学はおしなべて活力を失ったと思う。論文数の減少などもそうだが、現場の教員たちがあまりにも目前の仕事に追われ、自らの教育や研究への考えをじっくり深める余裕がなくなったことが大きな原因であると思う。文科省や財務省は、ひたすら評価や予算で縛り上げれば大学教員もボヤボヤせず馬車馬のように働くとお考えなのかも知れないが、それは学問研究というものを知らない人間の発想である。
もし、学問研究が日本国の未来にとって重要であると考えるならば、何とかして大学を「元気」にしてやる必要がある。そのために必要な方策は、おそらく、評価や予算で締め上げるタイプの「北風」政策ではなく、もっと大胆に自由なお金と時間を与える「太陽」政策である他はないと、筆者は考える。しかし今の政権上層部に、そんな度量や哲学を期待して良いものかどうか疑問である。
■
松田 智
2020年3月まで静岡大学工学部勤務、同月定年退官。専門は化学環境工学。主な研究分野は、応用微生物工学(生ゴミ処理など)、バイオマスなど再生可能エネルギー利用関連。

関連記事
-
これは今年1月7日の動画だが、基本的な問題がわかってない人が多いので再掲しておく。いま問題になっている大規模停電の原因は、直接には福島沖地震の影響で複数の火力発電所が停止したことだが、もともと予備率(電力需要に対する供給
-
先日、「国際貿易投資ガバナンスの今後」と題するラウンドテーブルに出席する機会があった。出席者の中には元欧州委員会貿易担当委員や、元USTR代表、WTO事務局次長、ジュネーブのWTO担当大使、マルチ貿易交渉関連のシンクタンク等が含まれ、WTOドーハラウンド関係者、いわば「通商交渉部族」が大半である。
-
ウクライナ戦争は世界のエネルギー情勢に甚大な影響を与えている。中でもロシア産の天然ガスに大きく依存していた欧州の悩みは深い。欧州委員会が3月に発表したRePowerEUにおいては2030年までにロシア産化石燃料への依存か
-
はじめに 映画「Fukushima 50」を観た。現場にいた人たちがフクシマ・フィフティと呼ばれて英雄視されていたことは知っていたが、どんなことをしていたのかはもちろんこの映画を観るまで知らなかった。 中でも胸を打ったの
-
アメリカは現実路線で石炭火力シフト、日本は脳天気に再エネ重視 アメリカの研究機関、IER(エネルギー調査研究所)の記事「石炭はエネルギー需要を満たすには重要である」によると、「ドイツでは5兆ドル(750兆円)を費やし、電
-
日本の防衛のコンセプトではいま「機動分散運用」ということが言われている。 台湾有事などで米国と日本が戦争に巻き込まれた場合に、空軍基地がミサイル攻撃を受けて一定程度損傷することを見越して、いくつかの基地に航空機などの軍事
-
福島第一原子力発電所の津波と核事故が昨年3月に発生して以来、筆者は放射線防護学の専門科学者として、どこの組織とも独立した形で現地に赴き、自由に放射線衛生調査をしてまいりました。最初に、最も危惧された短期核ハザード(危険要因)としての放射性ヨウ素の甲状腺線量について、4月に浪江町からの避難者40人をはじめ、二本松市、飯舘村の住民を検査しました。その66人の結果、8ミリシーベルト以下の低線量を確認したのです。これは、チェルノブイリ事故の最大甲状腺線量50シーベルトのおよそ1千分の1です。
-
以前、世界全体で死亡数が劇的に減少した、という話を書いた。今回は、1つ具体的な例を見てみよう。 2022年で世界でよく報道された災害の一つに、バングラデシュでの洪水があった。 Sky Newは「専門家によると、気候変動が
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間