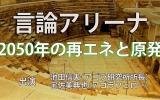バイデンの矛盾に矛盾を重ねた石油政策
バイデンの石油政策の矛盾ぶりが露呈し、米国ではエネルギー政策の論客が批判を強めている。
バイデンは、温暖化対策の名の下に、米国の石油・ガス生産者を妨害するためにあらゆることを行ってきた。党内の左派を満足させるためだ。

kodda/iStock
バイデンは大統領に就任した当日に、カナダからメキシコ湾岸の精製業者に石油を輸送するためのキーストーンXLパイプラインの許可を取り消し、石油・ガス生産のための連邦政府の土地の新規リースを停止した。
ところが一方で、サウジアラビアやロシアなどに対しては、価格を下げるために石油を増産するよう口説いていた。
しかし今月初め、石油生産者のカルテルであるオペックは、世界市場への原油放出の要請をあっさりと拒否し、バイデン政権は屈辱を味わうことになった。
米国のジェイク・サリバン国家安全保障顧問は、サウジアラビアやロシアを含むオペック・プラス(拡大したオペック)に対して、「世界的な景気回復の重要な時期に不十分な原油生産レベル」であると不満を述べていた。だがオペック・プラスは、現状の生産計画で十分に需要が賄える、として応じなかった。
米国では医療(メディケア)、税額控除、気候変動対策などに関する3.5兆ドルの予算案が上院で承認された。だが足元ではインフレ懸念が高まりつつあり、野党共和党の攻撃材料にもなって、バイデン政権も神経質になっている。
中でもガソリン価格の高騰は、庶民の目に最も公然と判るだけに、厄介な問題である。折しも米国のガソリン価格は今夏、2014年以来の高水準を記録している。
それにしてもタイミングが悪かった。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が第6次評価報告書を発表し、アントニオ・グテーレス国連事務総長が「世界の気候が危機にある」と訴えた僅か2日後に、米国がオペック・プラスに石油増産を要請したのは、まったく矛盾している。
のみならず、バイデン政権は、世界最大の石油・ガス生産国である自国の石油・ガス産業を全力で妨害する一方で、ガソリン価格が上がることで政権が批判されるのを回避すべく、サウジアラビアやロシアなどの必ずしも友好的ではない石油大国には増産を求める、というこれまた矛盾したことをやってきた。
まるきりチグハグで、国益を損なうものだ。
■

関連記事
-
これが日本の産業界における気候リーダーたちのご認識です。 太陽光、屋根上に拡大余地…温室ガス削減加速へ、企業グループからの提言 245社が参加する企業グループ、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)は7月、GH
-
ネット上で、この記事が激しい批判を浴びている。朝日新聞福島総局の入社4年目の記者の記事だ。事故の当時は高校生で、新聞も読んでいなかったのだろう。幼稚な事実誤認が満載である。 まず「『原発事故で死亡者は出ていない』と発言し
-
COP27が終わった。筆者も後半1週間、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された国連「気候変動枠組条約」締約国会合であるCOPの場に参加してきたが、いろいろな意味でCOPの役割が変貌していることを痛感するとともに、
-
6月21日の某大手新聞に、同社が6月前半に実施した主要100社への景気アンケート調査結果が掲載された。その中に「原発」に関する調査結果が記載されている。
-
前2回(「ごあいさつがわりに、今感じていることを」「曲解だらけの電源コスト図made by コスト等検証委員会」)にわたって、コスト等検証委員会の試算やプレゼンの図について、いろいろ問題点を指摘したが、最後に再生可能エネルギーに関連して、残る疑問を列挙しておこう。
-
前稿で触れた「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については、このアゴラでも既に杉山大志氏とノギタ教授の書評が出ており、屋上屋を架すの感なしとしないが、この本体価格2200円の分厚い本を通読する人は少ない
-
今回も嘆かわしい報道をいくつか取り上げる。 いずれも、筆者から見ると、科学・技術の基本法則を無視した「おとぎ話」としか受け取れない。 1. 排ガスは資源 CO2から化学原料を直接合成、実証めざす 排ガスは資源 CO2か
-
言論アリーナ「2050年の再エネと原発」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 経産省は2050年に向けてのエネルギー戦略を打ち出しました。そこでは再エネがエネルギーの中心に据えられていますが、果たして再エネは主役に
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間