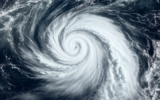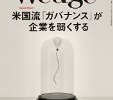原発がミサイル攻撃されたらどうするか
全国知事会が「原子力発電所に対する武力攻撃に関する緊急要請」を政府に出した。これはウクライナで起こったように、原発をねらって武力攻撃が行われた場合の対策を要請するものだ。
これは困難である。原子力規制委員会の更田委員長は国会で「攻撃を受けても核爆発のような被害をもたらすわけではないが、著しい環境汚染を引き起こす」と説明し、「対策は事実上ない」と答えた。

チェルノブイリ原発(iStock)
爆撃するなら原発より東京のほうが合理的
しかし原発攻撃は、現実には大きなリスクではない。ロケット弾ぐらいでは原子炉は破壊できないので、破壊するなら巡航ミサイルだが、これには目的に的中させるミサイル誘導技術が必要である。原子炉のような小さな標的に命中させて破壊する誘導技術は、中国も北朝鮮ももっていない。
やるなら1981年にイスラエル軍がイラクの原子炉を爆撃したように、爆撃機から落とすしかない。イスラエルの場合は建設中の原発を爆撃したのだが、稼働中の原発を破壊すると環境汚染が起こるだけで、効果は少ない。
核ミサイルなら命中させなくても原子炉を破壊できるが、このときは核爆発の被害のほうがはるかに大きいので、わざわざ原発のある人口密度の低い地域を核攻撃することは考えられない。
だから原発は、標的としては合理的ではない。規制委員会の田中前委員長が発言して問題になったように「原発をねらうより東京のど真ん中に落としたほうがよっぽどいい」のである。
不合理な「テールリスク」に備える戦時体制
このように原発攻撃は不合理だが、プーチンをみればわかるように、侵略戦争を仕掛ける独裁者は合理的ではない。こういうリスクをどう考えるかは、通常の安全審査とは別の問題である。
いま各地の原発で審査が行われている特重(特定重大事故等対処施設)は、テロや戦争を想定した対策だが、ミサイル攻撃には耐えられないので、航空機が落ちる程度の衝撃に耐えられるかどうかを審査している。
こういうテールリスクを考えると、原発だけではなく、都市近郊にある危険物もチェックする必要がある。たとえば東京湾のLNG(液化天然ガス)貯蔵基地を爆撃すれば、ガスが半径数kmに拡散し、大爆発を起こすので、戦術核兵器ぐらいの効果はある。
つまりミサイル攻撃に対する対策を考えることは、戦争に対応する戦時体制を考えることと同じなのだ。戦争こそ究極のテールリスクである。
「特重」の審査は原発の運転とは切り離せ
通常の正規分布に従うリスクは「ハザード×確率」という期待値で考えることができるが、戦争の起こる確率は正規分布に従わないので、期待値が存在しない。こういう場合は、万が一起こったときの最悪の被害を最小にするミニマックス原理で考えるしかない。
軍備もミニマックス原理だが、それをどのぐらいの規模にするかは期待値では決まらない。それはフランク・ナイトのいう不確実性だから、事前にリスクを計算できず、政府が決断し、それが誤っていた場合には政権を変えるしかない。
だが少なくともいえるのは、最適値はゼロリスクではないということである。原発のリスクをゼロにする簡単な方法は、すべての原発を廃炉にすることだが、日本では1人も死んでいない原発事故のリスクをゼロにするために原発を止め続けることには合理性がない。
特重はテロや航空機の墜落というさらに確率の低いテールリスクを対象にしているので、それがすべて終わってから運転しろというのは、戦時体制ができるまで飛行機も新幹線も運行するなというに等しい。
維新も提言しているように、設置変更許可の出た原発は特重と切り離して再稼動し、運転しながら審査すればいいのだ。それが原子炉等規制法の想定している手続きである。

関連記事
-
気象庁は風速33メートル以上になると台風を「強い」以上に分類する※1)。 この「強い」以上の台風の数は、過去、増加していない。このことを、筆者は気候変動監視レポート2018にあった下図を用いて説明してきた。 ところでこの
-
このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。
-
福島第1原子力発電所の事故以降、メディアのみならず政府内でも、発送電分離論が再燃している。しかし、発送電分離とは余剰発電設備の存在を前提に、発電分野における競争を促進することを目的とするもので、余剰設備どころか電力不足が懸念されている状況下で議論する話ではない。
-
経済産業省は排出量取引制度の導入を進めている。今年度内にルールを策定し、26年度から27年度にかけて本格的な導入を進める予定だ※1)。 対象となるのは日本の大手企業であり、政府から毎年排出枠を無償で受け取るが、それを超え
-
菅首相の16日の訪米における主要議題は中国の人権・領土問題になり、日本は厳しい対応を迫られると見られる。バイデン政権はCO2も重視しているが、前回述べた様に、数値目標の空約束はすべきでない。それよりも、日米は共有すべき重
-
ドイツで薬不足が続いている。2年前の秋ごろも、子供用の熱冷ましがない、血圧降下剤がない、あれもない、これもないで大騒ぎになっていたが、状況はさらに悪化しており、現在は薬だけでなく、生理食塩水までが不足しているという。 生
-
知人で在野の研究者である阿藤大氏の論文が、あれこれ紆余曲折の末、遂に公表された。 紆余曲折と言うのは、論文が学術誌に掲載されるまでに、拒否されたり変な言いがかりを付けられたりで、ずいぶん時間がかかったからだ。これは彼に限
-
熊本県、大分県を中心に地震が続く。それが止まり被災者の方の生活が再建されることを祈りたい。問題がある。九州電力川内原発(鹿児島県)の稼動中の2基の原子炉をめぐり、止めるべきと、主張する人たちがいる。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間