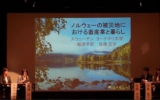「見せかけ」脱炭素宣言の氾濫は企業だけが悪者ではない
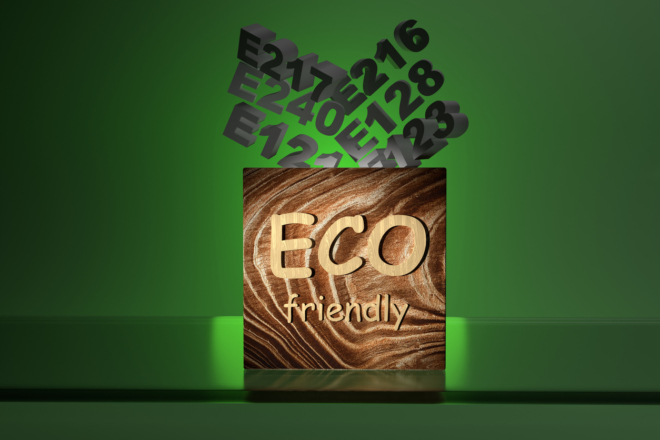
Nebasin/iStock
現在、エジプトのシャルムエルシェイクで国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)が開催されています。連日様々なニュースが流れてきますが、企業で環境・CSR業務に携わる筆者は以下の記事が気になりました。
企業の排出ゼロ宣言、見せかけ排除へ提言 国連専門家(日本経済新聞 2022年11月8日)
国連の専門家グループは8日、温暖化ガスの排出を実質ゼロにすると宣言した企業や自治体などの行動が、実際に目標に沿っているかを見極めるための提言を公表した。温暖化防止に役立っていない見せかけの「グリーンウオッシュ」を排除する狙いがある。金融機関の融資や取引の選定の基準として使われる可能性がある。
企業や自治体に詳細な排出削減計画を示した上で、サプライチェーン(供給網)全体の温暖化ガスの排出を減らし、進捗状況を公表するよう求めた。
自らの排出を減らしたとみせるために排出枠の購入に安易に頼るべきではない。
排出ゼロを守らせるため、自発的な宣言から当局などの規制に移していく必要性に言及した。規制することで進捗状況を毎年報告するよう義務付けるという。
排出実質ゼロの「見せかけ」排除で新基準、国連専門家が提案(ロイター 2022年11月9日)
自社が排出を継続しながら、それを他社の排出削減分である「カーボンクレジット」を購入して穴埋めする場合、信頼性が低く安価なクレジットを用いることは実質ゼロ戦略として認めていない。
専門家グループを率いる元カナダ環境相のキャサリン・マッケナ氏は記者会見で、「実質ゼロの約束の多くは空疎なスローガンや誇大広告に過ぎない」と指摘。「虚偽の実質ゼロ宣言は、最終的に誰もが支払うコストを押し上げる」と述べた。
2050年カーボンニュートラルや2030年CO2半減などの脱炭素宣言をしてしまった企業の中には、戦々恐々としている担当者が多いのではないでしょうか。
2030年CO2半減を宣言した企業のリリースを読むと、省エネ活動や再エネ導入などの自助努力に加えて、日本政府の2030年46%削減を前提条件と明記している企業も散見されます。つまり購入電力のCO2排出係数(電力1kWh当たりのCO2排出量)が46%程度改善するという期待が含まれています。
リリースやウェブサイトで明言していない企業であっても、社内の試算では多かれ少なかれ発電側での低炭素化を前提としていることが多いはずです注1)。例えるなら「8年後に売上を10倍にする」という野心的な経営計画を公表し、その前提条件として自助努力ではどうしようもない為替や物価上昇率などを折り込んでいるようなものです。
実現性や根拠が乏しくてもとにかく脱炭素に向けた宣言さえすれば投資家やメディアがムーンショット、ビジョン優先、バックキャスティングと称賛してくれて、投資が集まる社会が健全とは思えません。
僭越ながら、脱炭素宣言を行った企業でもしも日本の46%削減が実現可能だと本気で考えている経営者がいるとしたら認識が甘すぎます。逆に46%削減が不可能だと考えていながらこれを前提として中期計画を公表したとすれば投資家やステークホルダーを欺く行為ではないでしょうか。見せかけ、グリーンウォッシュと指弾されても反駁できないはずです。
さらに、万が一日本全体で2030年46%削減を達成した場合でも購入電力のCO2排出係数が46%改善する可能性は極めて低いのです。
かつて京都議定書では「2008年~2012年の平均で1990年比6%削減」という国の目標を達成しましたが、これはクレジット購入と森林吸収分の算入による見かけ上の辻褄合わせであり、現実のCO2排出量では単年ですら一度も6%削減を達成できませんでした。
当時、企業個社ではエネルギー使用量を削減したものの、購入電力のCO2排出係数が大幅に悪化したため環境中期計画未達の企業が続出しました。第6次エネルギー基本計画で示された2030年の電源構成も実現は困難なことから、今回も同じ歴史を繰り返すと考えるのが当然の帰結となります。
さて、脱炭素を進める多くの企業が安価な非化石証書に殺到していますが、非化石証書は再エネを増やす拡大効果(いわゆる追加性)がなく、また国民が再エネ賦課金で負担した「環境価値」を企業側がタダ同然の費用で取得するというきわめて非倫理的な制度です。
森林クレジットに関しても、将来の乱開発予定を過大に評価するなど算出根拠が不明瞭だったり、CO2削減効果を超えて大量のクレジットが発行される事例も存在するなど、詐欺まがいの行為が横行しています。
筆者は、実際にCO2を排出しているにもかかわらず見かけ上のCO2排出量を減らして事業活動の脱炭素化を訴求したり、製品・サービスを宣伝する行為が、将来グリーンウォッシュ、顧客に優良誤認を招く、などと批判されることを懸念していたため、アゴラ記事でたびたび言及してきました。
仮に、この記事を読んで脱炭素に貢献できるのだと思い込んで環境価値を購入した企業が、後になってNGOなどから「CO2排出の免罪符!」「グリーンウォッシュ!」と糾弾されたとしたら、この記者や出版社はどう反応するのでしょう。
これは企業のCO2削減に対する免罪符であり、イメージアップのためのグリーンウォッシュと言われても反論ができないと思います。
心当たりのあるCSR・サステナビリティ部門の担当者はぜひ経営者と対話し、自社の脱炭素宣言や脱炭素にかかわる製品・サービスについて虚心坦懐にふり返ることをおすすめします。グリーンウォッシュ認定される可能性がある場合は、勇気をもって自社の脱炭素宣言や脱炭素施策を見直すべきです。ESGやSDGsを掲げる廉潔な組織であれば、外部から指摘を受けて取り下げる前に自浄作用が働くはずです。
冒頭の記事にある通り、残念ながら産業界の実態としては見せかけの脱炭素宣言や安易な排出枠の購入が少なくないことでしょう。筆者は企業の脱炭素宣言もあらゆるカーボン・オフセット(非化石証書、森林クレジット、排出権取引など各種の排出枠購入)も否定的な立場ですが、脱炭素宣言をした上でカーボン・オフセットを利用せざるを得ない企業担当者の心情は理解できます。
一方で、こうした風潮をつくり出してきた頭目の国連が上記のような提言を出すのはご都合主義、マッチポンプと言わざるを得ません。そして国連や欧州、米国民主党政権が主導してきた気候危機や急進的脱炭素政策を日本に広めることで利益を得てきたSDGs・ESGコンサル、機関投資家、メディアなども同様です(「企業の理解不足だ」と後から言うのもご都合主義)。
削減計画の公表や進捗報告の義務化など規制を強化し抜け道となる手法も認めないのであれば、今後脱炭素宣言を撤回する正直で誠実な企業が現れてもメディアや投資家の皆さんは批判しないでいただきたいものです。「見せかけ」脱炭素宣言の氾濫は、産業界に対して気候変動リスクを煽ったすべての皆さんの活動成果でもあるのです。
注1)自助努力のみで8年後にCO2半減が可能という計画ができていればよいのですが、その企業はこれまであまり省エネ・CO2削減を行っておらず削減余地が大きいか、または莫大な再エネ投資を行って経営を圧迫し(ESG投資家以外の)株主利益に反する可能性があります。
■
11月15日に宝島社から新刊が出ました。是非ご覧ください。

関連記事
-
NHKで流れた福島原発事故の映像、ここに使用済核燃料が保管され一時的にその溶融の危険が指摘された。
-
アゴラ研究所の運営するインターネット放送の「言論アリーナ」。8月6日の放送は自民党衆議院議員の細田健一氏を招き「エネルギー危機を起こすな」を放送した。それを報告する。
-
政府が2017年に策定した「水素基本戦略」を、6年ぶりに改定することが決まった。また、今後15年間で官民合わせて15兆円規模の投資を目指す方針を決めたそうだ。相も変わらぬ合理的思考力の欠如に、頭がクラクラしそうな気がする
-
時代遅れの政治経済学帝国主義 ラワースのいう「管理された資源」の「分配設計」でも「環境再生計画」でも、歴史的に見ると、学問とは無縁なままに政治的、経済的、思想的、世論的な勢力の強弱に応じてその詳細が決定されてきた。 (前
-
今回は気候モデルのマニア向け。 気候モデルによる気温上昇の計算は結果を見ながらパラメーターをいじっており米国を代表する科学者のクーニンに「捏造」だと批判されていることは以前に述べた。 以下はその具体的なところを紹介する。
-
私は翻訳を仕事にしている主婦だ。そうした「普通の人」がはじめた取り組み「福島おうえん勉強会・ふくしまの話を聞こう」第一回、第二回を紹介したい。
-
EV補助金の打ち切り…その日は突然訪れた 12月17日、夜7時のニュースをつけたら、「EVの補助金は明日から中止されることになりました。あと5時間です」。 寝耳に水。まるでエイプリスフールだ。 政府はいくらお金がないとは
-
米国エネルギー長官クリストファー・ライトの指示によって、気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた報告書が2025年7月23日に発表された。タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間