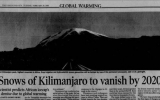柏崎・刈羽原子力発電所の再稼働:日暮れて途遠し

CampPhoto/iStock
運転禁止命令解除
原子力規制委員会は27日午前の定例会合において、東京電力ホールディングスが新潟県に立地する柏崎刈羽原子力発電所に出していた運転禁止命令を解除すると決定した。その根拠は原子力規制委員会が「テロリズム対策の不備が改善したと判断した」ことにある。
21年4月に事実上の運転禁止命令が原子力規制委員会から出されてから2年8カ月が経過している。東京電力がすでに適合性審査に合格している柏崎刈羽6、7号機を再稼働するには地元の同意を取り付けなければならない。

事実上の運転禁止命令解除を発表する山中規制委員長
2つの原子力発電所と2人の首長
柏崎刈羽原子力発電所は柏崎・刈羽原子力発電所、つまり柏崎原子力発電所&刈羽原子力発電所なのである。7基の原子炉のうち、1から4号機が柏崎市にあり、残りの5、6、7号機が刈羽村に設置されている。

東京電力柏崎刈羽原子力発電所の敷地
出所:東京電力ホールディングス「柏崎刈羽原子力発電所の現況について」、2016年6月21日
すなわち柏崎刈羽(KK)とひとまとめにされているが、二つの原子力発電所があると言った方が適切である。運営しているのが東京電力なので、東電側の都合で一括りにされているだけだ。
柏崎市と刈羽村は別々の行政区であるので、一括りの扱いは違和感もあろう。私は、柏崎市も刈羽村も度々訪れてきたが、その風土・文化・人には共通点もあれば異なる趣もかなりある。
一言でいえば、刈羽村は純朴であり、柏崎市はやや複雑である—遠慮なくいわせていただければいささか〝偏屈〟と言ってもいい側面がある。柏崎市の旧知は、「愛はいつでも憎悪に衣替えする」と言った。そのことを東電はもっと真摯に捉えたほうが良いという文脈だと私は思った。
地元の民意は首長が受け止める。
刈羽村の品田村長は一貫して原子力推進、日本のため再稼働は不可欠の信念の人である。
柏崎市の桜井市長は、若い頃から原発推進を信条とすることが知られた人物だった。しかし、市長に当選した頃から少し旗色が変わってきた・・・かなり慎重な発言が目立ち始め、やがて集中立地の危険性に言及したり、再稼働の条件として廃炉にする号機を明確にすることを論ったりしていた。
柏崎から出雲崎をへて刈羽に至る地域は江戸時代は幕府直轄の天領地として栄えた土地柄である。その歴史や自負は今も地域に根付いていると私は感じている。
テロ対策の不備が改善したのか
テロ対策の不備に関する事案は2つある。
A. 2020年9月下旬、社員Bが入室IDカードを紛失し、当日未出勤の社員Aの入室IDカードを無断で使用し、中央制御監視室に出入りしていたことが発覚、原子力規制委員会も報告が遅れたことが発覚した。
B. 2021年3月16日、テロリズム対策に関わる侵入検知装置が、長期間機能喪失に陥っていたことが発覚し、原子力規制委員会が、問題の重要度を「最悪」と評価したことに対して、東京電力HD社長小早川智明が謝罪した。2021年4月14日、原子力規制委員会は東京電力HDに対し、状況の改善が追加検査で確認されるまで、柏崎刈羽原発内で核燃料の移動を禁じる是正措置命令(命令は原子炉内への核燃料装填も禁じるため、命令が解除されるまで発電できず、再稼働は不可能になる)の行政処分を下した。
(Wikipediaより)
ケースAについては、偶発的な出来事のようにも見えるが、同様のケースは2015年(平成27年)8月にも起こっていたことが後に明らかになっている。そしてこのケースはシステムの問題というよりは、ヒトと運用の問題とみなすこともできる。
ケースBは、ヒトと運用の問題に加えて、侵入検査装置というシステム自体が壊れていたことに気が付いていなかった。しかもそれが長期間に及んでいたということでより深刻と捉えられよう。壊れていたのに気づかなかったのか、気がついていても長期間対処しなかったのか——いずれにしてもそれに関わるヒトと組織の問題である。
こういったケースの原因をたどっていけば、結局「〝ヒトと組織の劣化〟につながる問題はそう簡単に改善解消できるのだろうか?」という疑問にたどり着く。
地元からすれば東電はかつては優良エリート企業であり、地域の若者の就職先としては東電以上のものはなかった。しかし、私がその筋から仄聞したところ、もう何年も前からそのような地位は消え失せ、地元の有能な若者の採用に苦心していたとのこと。
ヒトの劣化の問題は地元の問題ではない。それは企業ガバナンスの問題であるから、東電そのもののガバナンスが劣化していることの現れとみるべきだろう。
テロリズム対策の不備が改善したと判断したというが、根底の問題はヒトの問題であり組織ガバナンスの問題である。そうそう容易に改善されるのであろうか——というのが私が抱く深い悩みである。
再稼働の条件—地元のパワーバランス・県民意思
刈羽原子力発電所6、7号機を再稼働するには地元の同意が得られないといけない。地元とは、刈羽村、柏崎市、そして新潟県である。
柏崎市の桜井市長は近頃は再稼働容認に前向きだと聞く。
よく分からないのは、新潟県知事の花角氏である。花角知事は27日、再稼働の是非に関しては最終的には県民の意思を確認するために「信を問う」としている。
知事は「『信を問う』とは自身の存在をかける意味合いが強いと思う。いま決めているものはないが、方法としては選挙ももちろんある」と述べて、県知事選を県民意思の確認の選択肢の一つと考えているようだ。
前知事の米山隆一氏は「やり残した仕事がある」と仮に県知事選があれば、代議士職を辞して出馬する意向をほのめかしている。

前知事の米山隆一氏
Wikipediaより
政府は「再稼働への関係者の総力の結集」を謳い再稼働を加速する意向である。再稼働はもちろん東電の悲願である。
しかし、柏崎・刈羽原子力発電所の再稼働は日暮れて途遠しの感が否めない——という他ないと私は思う。

関連記事
-
ロシア軍のウクライナ攻撃を「侵攻」という言葉で表現するのはおかしい。これは一方的な「武力による主権侵害」で、どうみても国際法上の侵略(aggression)である。侵攻という言葉は、昔の教科書問題のときできた言い換えで、
-
「2020年までに地球温暖化で甚大な悪影響が起きる」とした不吉な予測は多くなされたが、大外れだらけだった。以下、米国でトランプ政権に仕えたスティーブ・ミロイが集めたランキング(平易な解説はこちら。但し、いずれも英文)から
-
太陽光発電を導入済みまたは検討中の企業の方々と太陽光パネルの廃棄についてお話をすると、ほとんどの方が「心配しなくてもそのうちリサイクル技術が確立される」と楽観的なことをおっしゃいます。筆者はとても心配症であり、また人類に
-
国家戦略室が策定した「革新的エネルギー・環境戦略」の問題を指摘する声は大きいが、その中でも、原子力政策と核燃料サイクル政策の矛盾についてが多い。これは、「原子力の長期利用がないのに再処理を継続することは、矛盾している」という指摘である。
-
原発事故から3年半以上がたった今、福島には現在、不思議な「定常状態」が生じています。「もう全く気にしない、っていう方と、今さら『怖い』『わからない』と言い出せない、という方に2分されている印象ですね」。福島市の除染情報プラザで住民への情報発信に尽力されるスタッフからお聞きした話です。
-
ロシアの原子力企業のロスアトム社は2016年に放射性ヨウ素125の小線源の商用販売を開始する。男性において最も多いがんの一つである前立腺がんを治療するためのものだ。日本をはじめとした国外輸出での販売拡大も目指すという。
-
オーストラリアのジャーナリストJoNova氏のブログサイトに、オーストラリアの太陽光発電について、「導入量が多すぎて多い日には80%もの発電能力が無駄になっている」という記事が出ていました。 日本でも将来同様のことになり
-
原子力政策の大転換 8月24日に、第2回GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議が開催された。 そこでは、西村康稔経産大臣兼GX実行推進担当大臣が、原子力政策に対する大きな転換を示した。ポイントは4つある。 再稼
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間