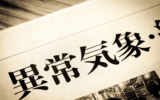日本より排出の多い世界の4大排出国は脱炭素などしない

「世界はカーボンニュートラルへ一丸となって歩み始めた」「米国トランプ政権がパリ協定を離脱しても、世界の脱炭素の流れは変わらない」——といった掛け声をよく聞く。そして日本では脱炭素のためとしてグリーントランスフォーメーション(GX)計画が着々と推進されており、2050年CO2ゼロが公式の目標となっている。
しかし、実際のところ、世界はどこに向かっているのだろうか。
2023年の世界のCO2排出量は過去最高になり、37.4Gt(ギガトン)であった。上位10か国を並べると、1位は中国で世界の33%を排出していた。以下、2位は米国で13%、3位はインドで7%、4位はロシアで5%、5位は日本で3%であった。より正確に言えば日本は2.6%なので、もうすぐ2%と言うときが来るだろう。この5か国で、じつに世界の60%を占めている。
つまりは、これら大排出国がどうするかで、世界の排出がどうなるか、その趨勢は決まるということだ。それで、どうなっているのか?
ロシアの経済そして国家財政は、化石燃料に依存している。2024年の原油・天然ガス関連歳入は11.1兆ルーブル(約1,080億ドル)に達し、これはロシア連邦予算の約3分の1を占めていた。これは対ウクライナ戦争で膨らむ軍事費の源泉でもある。このロシアが石油採掘を止めるはずも、ガス輸出を止めるはずもない。そんなことは誰が強制できるはずもない。
では、そのロシア産原油を買っているのはどの国か。答えは中国とインドだ。2024年の1〜3月の間に中国が輸入したロシア産原油は日量217万バレルに達した。これは日本の総石油消費(約日量330万バレル)の3分の2に当たる莫大な量だ。インドも日量190万バレル前後をロシアから輸入している。両国合わせると、ロシアの原油輸出の半分以上を吸収していることになる。欧米はロシアに経済制裁を課しており、輸入を制限してきたが、中国もインドも聞く耳を持たなかった。
中国は石炭火力発電も諦めてなどいない。中国では、2023年の1年間だけで石炭火力が47.4GW(=4,740万kW)も新規に運転開始した。さらに同年、中国は94.5GW分もの石炭火力に新たに着工している※1)。
インドも同じ道を歩む。政府計画では35 GW超の石炭火力が開発中で、昨年だけで複数の大型発電所が着工した※2)。温室効果ガス削減より、14億人の電力需要と経済成長が明らかに優先されている。
世界全体の石炭消費も2023年に86億トンと過去最高を更新した※3)。
世界の60%の排出を占める5大排出国は、どこも脱炭素などしていない——例外は、2.6%を占める第5位の日本だけである。
※1)Global Energy Monitor “Boom & Bust Coal 2024” China section
※2)Global Energy Monitor “Boom & Bust Coal 2024” India section
※3)International Energy Agency “Coal 2024 – Analysis and forecast to 2026”
■

関連記事
-
日本政府はどの省庁も「気候変動のせいで災害が激甚化・頻発化している」と公式文書に描いている。だから対策のために予算ください、という訳だ。 表1を見ると、内閣府、内閣官房、環境省、国土交通省、農林水産省、林野庁とみな「激甚
-
豪州と欧州で停滞する水素プロジェクト 昨年11月のニュースだが、関西電力が丸紅などと豪州で計画していた水素製造事業から撤退するとの報が流れた。プラントや収支計画などの基本設計を詰める中で、製造コストが想定以上に高く、採算
-
きのうのシンポジウムでは、やはり動かない原発をどうするかが最大の話題になった。 安倍晋三氏の首相としての業績は不滅である。特に外交・防衛に関して日米安保をタブーとした風潮に挑戦して安保法制をつくったことは他の首相にはでき
-
以下の記事もまったく日本語で報道されません。 Fintech firm Aspiration Partners’ co-founder pleads guilty to defrauding investor
-
以前紹介したように、米国エネルギー長官クリストファー・ライトの指示によって、気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)の報告書が2025年7月23日
-
1992年にブラジルのリオデジャネイロで行われた「国連環境開発会議(地球サミット)」は世界各国の首脳が集まり、「環境と開発に関するリオ宣言」を採択。今回の「リオ+20」は、その20周年を期に、フォローアップを目的として国連が実施したもの。
-
去る4月16日に日本経済団体連合会、いわゆる経団連から「日本を支える電力システムを再構築する」と題する提言が発表された。 本稿では同提言の内容を簡単に紹介しつつ、「再エネ業界としてこの提言をどう受け止めるべきか」というこ
-
前回の英国に引き続き今度はアイルランドのアンケートの紹介。 温暖化対策のためにエネルギー(電気、ガス、石油、ディーゼル)へ課税することに、82%が反対、賛成は14%のみ(図1)。 他の項目は図2のとおり。 図の一番下の2
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間