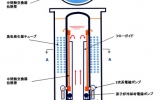正確だった国の“脱線”:ドイツ鉄道という国家の縮図

Stadtratte/iStock
昔は“正確”が自慢だったドイツ鉄道が、今ではその反対で、“不正確”の代名詞になってしまった。とにかく遅延の度合いが半端ではない。
ヨーロッパの遠距離列車は国境を超えて相互に乗り入れているケースが多く、周辺国ではドイツからの電車が来ないと乗り継ぎが乱れ、ダイヤ全体が狂って多大な迷惑を被っている。特に、正確で有名なスイス鉄道はとうとう痺れを切らし、今年の5月より、ハンブルク、およびドルトムントからの列車にはスイスに乗り入れをさせなくなった。
本来ならインターラーケンとチューリヒまで直通で乗り入れるはずの列車だが、現在は、スイスの国境を越えたところのバーゼル駅が終点。バーゼルは接続駅なので、多くの乗り換え客が、いつ着くかわからないドイツからの列車を延々と待つ事態が度重なり、我慢の限界を超えたらしい。今では、バーゼルから先の区間はスイス鉄道のみが運行している。
ただ、反対方向では、スイス鉄道はこれまで通りドイツに乗り入れ、直通で終点まで行けるというから、要するに機能していないのはドイツ鉄道だけ。CEOが何度も変わり、その度に華々しく改善が約束されてきたが、未だに何も変わらないばかりか、どんどん悪くなる。
このドイツ鉄道の落ちこぼれぶりがヨーロッパ中で急激に知れ渡ったのは、昨年6月、サッカーの欧州選手権がドイツで開催された時だった。オランダ、フランス、オーストリアなど隣国からのファンが、朝早くドイツに向かったものの、列車は例の如くあちこちで立ち往生。ひどいケースでは、突然の行き先変更で違うところに着いてしまい、夜9時のキックオフに間に合わなかったとか、とにかく気の毒な話が飛び交った。
実は私も、遅延や突然の運休はもちろん、行先が変わってしまった列車にも乗ったことがあるし、「今度の電車には○号車が付いていませんので、予約している人はどこか他の車両で席を探してください」という不思議な構内放送を聞いたこともある。
しかも、雪が降れば止まるし、夏はクーラーが故障する。だから、今ではどんな話を聞いてもそれほど驚かないが、他の国の普通の人がこういう事態に遭遇すれば、かなり衝撃的だということはわかる。
10月1日にはエヴェリン・パッラというイタリア人女性がドイツ鉄道のCEOに就任したが、その前月9月の遅延率は61.9%で、これまでの最悪記録52%をさらに更新したとのこと。挽回はあるのか? 蛇足ながら、ドイツで遅延に計上されるのは6分以上遅れた場合で、しかも運休は計算に入っていない。
笑ったのは、スイスのジャーナリストが11月6日に自分の番組の中で話していた“大冒険”。その前夜、ドイツのビーレフェルトから乗ったリーザ行きの列車が突然、何もない野原の真ん中で停車した(日本なら1分以内になぜ停車したかの放送があるが、ドイツではかなり長く待たされる)。ただ、この時の車内放送には、さすがの私も驚いた。
「乗客の皆さん、残念ながら運転士がいなくなりましたので、交代要員が来るまで発車できません」。夜9時半。
「???」 遅延のため、運転士が交代するはずの駅まで辿り着かないうちに、安全規定の労働時間に達してしまったのだろう。とはいえ、駅でもないところで運転士が職場を離れるとは常軌を逸している。とにかく、何故こんなことになるのかが全くわからない。
ただ、しばらくして代わりの運転士が来て、ようやく列車は動き出したものの、またもや車内放送で、「乗客の中にお医者さんはいませんか?」
乗客は皆、新しい運転士が病気になったのかと思ったらしいが、そうではなく、(あまりの遅延のため?)本当に病人が出た。そこで列車はまた止まって救急車を待ち、結局、4時間40分だったはずの旅程が7時間あまりとなり、深夜を回ってようやく目的地に到達したという。ただ、そんな遅くに知らない町に着いても、家族が迎えに来てくれる人以外は絶望するしかない。
実は目下のところ、ドイツ鉄道は全土で大々的な改修工事の最中だ。16年のメルケル施政下、ロシアからの安いガスと、東欧からの良質な安い労働力のおかげで、ドイツ経済はEUの一人勝ちなどと言われた。
しかし、ドイツは輸出で大儲けしながらも、内需にはほとんど投資せず、その付けが今、回ってきており、道路も、橋も、学校も、全てボロボロ。特にドイツ鉄道は、架線もポイントも枕木も、何十年も放っておけばこうなるという見本のような状態だという。
ただ、その工事のやり方がまたもや異色。たとえば、ベルリン〜ハンブルクというドイツ1位と2位の大都市を結ぶ幹線が、現在、9ヶ月間の予定で通行止めとなっている。日本の新幹線の東京〜名古屋間が止まっているようなもので、はっきり言ってあり得ない。
その結果、毎日、この路線を利用していた3万人の乗客は、1時間も余計に時間のかかる路線に迂回させられ、しかも、それがまた頻繁に遅延するという悪夢だ。他の国は皆、たいていの工事は列車を止めずに行っているのに、ドイツの場合、なぜこうなるのか、これもよくわからない。
ドイツ人は辛抱強い。私の友人は特急に乗って発車を待っていたら、そのまま発車まで1時間半も待たされたという。しかし、その間、乗客の間には妙な連帯感が芽生えたそうだ。同じようなことは、前述のジャーナリストも言っていた。「皆、イラつきながらも、意外とユーモアがあった」と。
私は、ドイツ人というのは艱難辛苦に強い民族だと思っている。不幸が襲って来ると連帯し、皆で助け合い、しかも、突然、生き生きとし始める。たとえば、どこかの町が洪水で泥に埋まってしまったと聞くと、近隣からスコップを持った人たちがゴム長を履いて続々と集まってきて、一生懸命に泥と戦う。この光景を見ていると、普段、病欠が異常に多い国の国民だとはとても信じられないほどだ。
だから、列車が止まり、どうしようもない状況になった時にも、やおら、この感情がムクムクと湧いてくるのだ。そして、皆で冗談を言いながら頑張る。ドイツ人は根はいい人たちなのだ。
ただ、本来は頭もいいはずなのに、なぜ、鉄道を時間通りに走らせられないのか、それが謎である。

関連記事
-
菅直人元首相は2013年4月30日付の北海道新聞の取材に原発再稼働について問われ、次のように語っている。「たとえ政権が代わっても、トントントンと元に戻るかといえば、戻りません。10基も20基も再稼働するなんてあり得ない。そう簡単に戻らない仕組みを民主党は残した。その象徴が原子力安全・保安院をつぶして原子力規制委員会をつくったことです」と、自信満々に回答している。
-
私は原子力の研究者です。50年以上前に私は東京工業大学大学院の原子炉物理の学生になりました。その際に、まず広島の原爆ドームと資料館を訪ね、原子力の平和利用のために徹底的に安全性に取り組もうと決心しました。1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故は、私の具体的な安全設計追求の動機になり、安全性が向上した原子炉の姿を探求しました。
-
2025年6月15〜17日、カナダのカナナスキスでG7サミットが開催される。トランプ第2期政権が発足して最初のG7サミットである。 本年1月の発足以来、トランプ第2期政権はウクライナ停戦、トランプ関税等で世界を振り回して
-
マサチューセッツ工科大学(MIT)の科学者たちによる新しい研究では、米国政府が原子力事故の際に人々が避難すること決める指標について、あまりにも保守的ではないかという考えを示している。
-
GEPR編集部より。このサイトでは、メディアのエネルギー・放射能報道について、これまで紹介をしてきました。今回は、エネルギーフォーラム9月号に掲載された、科学ジャーナリストの中村政雄氏のまとめと解説を紹介します。転載を許諾いただきました中村政雄様、エネルギーフォーラム様に感謝を申し上げます。
-
英国の環境科学者で地球を1つの生命体とみなす『ガイア理論』を提唱したジェームズ・ラブロック氏が103歳で亡くなってから、間もなく2ヶ月になろうとしている。 CNNは次のように報じた。 ラブロック氏は科学界に多大な功績を残
-
1.メディアの報道特集で完全欠落している「1ミリシーベルトの呪縛」への反省 事故から10年を迎え、メディアでは様々な事故関連特集記事や報道を流している。その中で、様々な反省や将来に語り継ぐべき事柄が語られているが、一つ、
-
私は太陽光発電が好きだ。 もともと自然が大好きであり、昨年末まで勤めた東京電力でも長く尾瀬の保護活動に取り組んでいたこともあるだろう。太陽の恵みでエネルギーをまかなうことに憧れを持っていた。いわゆる「太陽信仰」だ。 そのため、一昨年自宅を新築した際には、迷うことなく太陽光発電を導入した。初期投資額の大きさ(工事費込み304万円)には少々尻込みしたが、東京都と区から合わせて約100万円の補助金を受けられると聞いたこと、そして何より「環境に良い」と思って決断した。正確に言えば、思考停止してしまった。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間