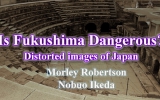今週のアップデート — 中西準子博士に学ぶ、放射能とリスク(2014年7月14日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
1) 福島除染、年5mSv目標を新提案・中西準子氏【言論アリーナ・本記】
2) 除染目標は年5mSvに=中西・池田対談【言論アリーナ要旨(上)】
3) 「絶対反対」の政治運動に疑問=中西・池田対談【言論アリーナ要旨(中)】
4) 除染対策でコストと効果の分析を=中西・池田対談【言論アリーナ要旨(下)】
5) 映像「放射線のリスクを科学的に考える–反公害運動50年の歴史から」
福島原発事故の後始末で、住民被ばく量で年1mSv(ミリシーベルト)までの除染を目標にしたために、手間と時間がかかり、福島県東部の住民の帰還が遅れています。この問題に取り組む、日本の環境リスク研究の第一人者である中西準子博士(産業技術総合研究所フェロー)にアゴラ研究所の運営するネット放送、言論アリーナに出演いただきました。池田信夫アゴラ研究所所長との対談の報告です。
中西氏は日本の環境リスク研究を1970年ごろから先駆的に行い、科学者の立場から環境保護活動に向き合ってきました。その提案が日本の下水道政策や、化学物質管理政策に大きな影響を与えてきました。現在は福島の除染、放射線防護問題に取り組んでいます。
除染目標5mSvという新提案、そしてリスク分析の解説など、中西さんの知恵は、放射線問題、そして環境・エネルギー問題を考える際に、大変参考になります。ぜひ、ご一読ください。
今週のリンク
池田信夫アゴラ研究所所長。中西準子氏の最新刊の書評です。リスクを確率で分析するという、本の主張の主要部分を紹介しています。
環境問題の解説で著名な安井至東大名誉教授のブログ「市民のための環境学ガイド」。今回の番組で説明の少なかった、日本政府の被ばく線量の評価が、実効値よりかなり高くなっているという問題について、中西氏の見解を解説しています。
産経新聞7月13日記事。九州電力川内原発の1、2号機が、原子力規制委員会による新安全基準の適合性審査が了承される方向になりました。16日に判定がくだり、再稼動に向け、一歩進むことになります。ただし、地元住民などとの折衝の問題が残ります。
読売新聞7月14日記事。13日に投開票の滋賀県知事選挙で、与党の自民、公明両党推薦の小鑓隆史氏が前民主党衆院議員の三日月大造氏に敗れました。三日月氏は、卒原発を掲げた嘉田由紀子知事の継承を訴え、原発も強調したものの、主要な論点ではありませんでした。しかし、この選挙を軸に、原子力問題が再び政治問題として注目を浴びる可能性があります。
日本経済新聞7月13日記事。米国のモニツ・エネルギー省長官のインタビューです。これまで米国が原則輸出していなかった天然ガスについて、輸出解禁の可能性を示唆。一方、原発の重要性も強調しています。既存の政策の確認として、参考になる記事です。

関連記事
-
震災から10ヶ月も経った今も、“放射線パニック“は収まるどころか、深刻さを増しているようである。涙ながらに危険を訴える学者、安全ばかり強調する医師など、専門家の立場も様々である。原発には利権がからむという“常識”もあってか、専門家の意見に対しても、多くの国民が懐疑的になっており、私なども、東電とも政府とも関係がないのに、すっかり、“御用学者”のレッテルを貼られる始末である。しかし、なぜ被ばくの影響について、専門家の意見がこれほど分かれるのであろうか?
-
14年10 月28日公開。モーリー・ロバートソン(作家、DJ)、池田信夫(アゴラ研究所所長)。福島の現状について、海外でどのように受け止められているかをまとめた。(大半が英語)
-
福島第一原発の処理水問題が、今月中にようやく海洋放出で決着する見通しになった。これは科学的には自明で、少なくとも4年前には答が出ていた。「あとは首相の決断だけだ」といわれながら、結局、安倍首相は決断できなかった。それはな
-
ICRP勧告111「原子力事故または放射線緊急事態後における長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」(社団法人日本アイソトープ協会による日本語訳、原典:英文)という文章がある。これは日本政府の放射線防護対策の作成で参考にされた重要な文章だ。そのポイントをまとめた。
-
第1回「放射線の正しい知識を普及する研究会」(SAMRAI、有馬朗人大会会長)が3月24日に衆議院議員会館で行われ、傍聴する機会があった。
-
鳩山元首相が、また放射能デマを流している。こういうトリチウムについての初歩的な誤解が事故処理の障害になっているので、今さらいうまでもないが訂正しておく。 放射線に詳しい医者から聞いたこと。トリチウムは身体に無害との説もあ
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
波紋を呼んだ原田発言 先週、トリチウム水に関する韓国のイチャモン付けに対する批判を書かせていただいたところ、8千人を超えるたくさんの読者から「いいね!」を頂戴した。しかし、その批判文で、一つ重要な指摘をあえて書かずにおい
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間