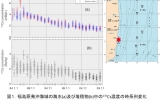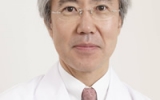復興は今後5年が正念場【復興進む福島4】
 青木基(もとい) 楢葉町議会議長
青木基(もとい) 楢葉町議会議長私は獣医師で震災の年まで福島県の県職員だった。ふるさとの楢葉のために働きたいと思い、町議に立候補し、議長にも選んでいただいた。
楢葉町では原発事故によって3つのものが失われたと思う。一つは家族の絆だ。この町は農業が中心で2~3世代の同居が多かった。ところが避難でばらばらになった。若い世代は職場、また子どもの学校の近くにすみ、別居を余儀なくされた。
第2に地域の絆だ。長くこの地域に住んできた人が多く、地域の人がそれぞれ顔見知りだった。それがなくなってしまった。とてもさびしいことだ。
第3に、命と健康だ。災害関連死では今年3月までに112人。避難生活による健康被害や自殺を含んだものだ。家族や地域の絆が壊れたことで、精神的な健康がむしばまれている。特に高齢者の孤立が深刻になっている。そして住民の健康はかなり悪化している。慣れない生活での引きこもり、過食での肥満などで生活習慣病などを悪化させている。ストレスを訴える人も多い。
地域の傷は大きい。避難指示の解除は、もちろん復興のための重要な一歩だし、町民はこぞって歓迎している。しかし実際に住めるのかというと話は別だ。
春に当初8月の盆前に避難指示を解除すると打診されたが、町議会は住民の声を聞き「準備がまだ整っていない」と意見を出し9月の解除となった。医療、買い物や飲食の場所、住居がまだ整っていない。そして雇用の場がない。住民の帰還は大半が50歳代より上だ。子育て世代がいない。雇用の場、生活環境の改善は進めていくべきだろう。
子どもの声が聞こえない町は、自然に消滅してしまうだろう。今年度で復興計画の5年が終わり、今後5年延長される。この5年が楢葉町にとって正念場となる。もちろん私たちの努力が前提だが、国と県に復興支援をお願いし、それを負担する日本中の皆さんに理解をいただきたいと思う。(談)
(この記事はエネルギーフォーラム9月号に掲載させているものを、同社から転載の許諾を得た。関係者の方に感謝申し上げる。)
(2015年9月24日掲載)

関連記事
-
日本の原子力の利用は1955年(昭和30年)につくられた原子力基本法 を国の諸政策の根拠にする。この法律には、原子力利用の理由、そしてさまざまな目的が書き込まれている。その法案を作成した後の首相である中曽根康弘氏が当時行った衆議院での演説を紹介したい。
-
「死の町」「放射能汚染」「健康被害」。1986年に原発事故を起こしたウクライナのチェルノブイリ原発。日本では情報が少ないし、その情報も悪いイメージを抱かせるものばかりだ。本当の姿はどうなのか。そして福島原発事故の収束にそ
-
新規制基準の考え方を整理し、一般の人に解説したもの。ただし訴訟対策と、同規制委は認めている。
-
3月24日。再掲載。今回の再エネ政策の見直しの背景になった功罪について検証しています。全3回。
-
福島原発事故以来、環境の汚染に関してメディアには夥しい数の情報が乱れ飛んでいる。内容と言えば、環境はとてつもなく汚されたというものから、そんなのはとるに足らぬ汚染だとするものまで多様を極め、一般の方々に取っては、どれが正しいやら混乱するばかりである。
-
商品先物市場を運営する東京商品取引所(TOCOM)の社長に浜田隆道氏が就任した。経済産業省出身で同社専務から昇格した。「総合エネルギー市場」としての発展を目指すという。抱負を聞いた。
-
スマートジャパン 3月14日記事。環境省が石炭火力発電所の新設に難色を示し続けている。国のCO2排出量の削減に影響を及ぼすからだ。しかし最終的な判断を担う経済産業省は容認する姿勢で、事業者が建設計画を変更する可能性は小さい。世界の主要国が石炭火力発電の縮小に向かう中、日本政府の方針は中途半端なままである。
-
低線量放射線の被ばくによる発がんを心配する人は多い。しかし、専門家は「発がんリスクは一般に広がった想像よりも、発がんリスクははるかに低い」と一致して指摘する。福島原発事故の後で、放射線との向き合い方について、専門家として知見を提供する中川恵一・東大准教授に聞いた。(全3回)
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間