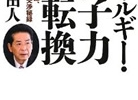今週のアップデート — 核廃棄物、国際管理の必要(2013年8月26日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。
1) 核燃料サイクルを放棄するなかれ・その3 — 六ヶ所の再稼動はなぜ必要か
2) 核燃料サイクルを放棄するなかれ・その4 — 国際的なプルトニウム管理体制の必要
先週に続いて、初代外務省原子力課長の金子熊夫氏の論考です。日本の核燃料サイクルが、原子力をめぐる国際関係の中でどのように位置づけられているかの、分析はあまりありません。今回の議論では、それを明らかにしています。
「余剰プルトニウムを持たない」。日本の原子力政策は、このような政策を重ね、平和利用に特化する形で発展してきました。そこで強調されたのが、核兵器、汚染を拡散する「汚い爆弾」の原料となるプルトニウムを持たないことでした。「その3」ではプルトニウムを減らす核燃料サイクル政策の関係を解説。さらに「その4」でプルトニウム管理の国際体制の整備を訴えています。
3) 真の原子力再生に必要なことは何か?(下)原子力再生に向けて
前週に引き続いて(記事上)、国際環境経済研究所の論考を掲載。福島原発事故前後の電力会社原子力部門の状況を説明しています。
4)原子力により防がれた従来および予測される死亡者数および温室効果ガスの排出量
NASA(米航空宇宙局)とコロンビア大学の共同研究論文。米国化学学会機関誌「Environmental Science and Technology」に掲載。原子力が導入されたことで、大気汚染に関連した184万人の死と温暖化をこれまで抑制したと推計されます。原子力発電はさまざまな問題を抱えていますが、大気汚染と温暖化の抑制という点では大きな成果がありました。
今週のリンク
1) 温暖化「人類が原因」の可能性95% 国連報告書の内容判明
ハフィントンポスト8月22日記事。IPCC(国連気候変動に関する政府間パネル)の第一作業部会報告(気候システムおよび気候変動に関する科学的知見の評価)が今年9月中に発表されます。(残りは来年春まで)日本のメディアには詳細な話は出ていません。(米ニューヨークタイムズ記事)温暖化は人為的なものによる可能性が高いというこれまでの結論が一段と強められています。
日本経済新聞8月23日記事。福島原発の事故現場で、事故処理に基づく汚染水の漏洩が広がっています。原子炉から地下水にしみ出したことに加え、処理済み水で保管したタンクからの漏洩も懸念されています。現時点で、福島他地域の周辺地域の線量上昇などの影響は見られないものの、長期的な海洋汚染が懸念されています。
読売新聞8月24日社説。原子力規制委員会の活断層をめぐる判断の迷走が続いています。結論が出ません。社説はこれを「科学的な議論をしているのか」とその動きを疑問視しています。
ニューヨークタイムズ、8月20日掲載の論説。原題は「Coming Full Circle in Energy, to Nuclear」。米国のジャーナリスト、エデュアルト・ポーター氏の寄稿。オバマ政権の「グリーン・エネルギー政策」が失敗。いろいろ試してみて、結局、原子力は有力な選択肢として残ったという分析です。
ニューヨークタイムズ、8月23日掲載の論説。原題は「The New Nuclear Craze-Fears of climate change are no reason to revive a doomed energy source」。使用済み核燃料の処理方法は決まらず、再生可能エネルギーを伸ばすべきだ。化石燃料の使用を規制を強めて当面はするべきだとの論調です。日本と同じような議論が、米国でも行われています。ただし、その議論はメディアで見る限り理性的です。

関連記事
-
米国の商業用電力消費の動向 さる6月末に、米国のエネルギー情報局(EIA)が興味深いレポートを公表した※1)。米国で2019年から23年の4年間の商業用電力消費がどの州で拡大し、どの州で減少したかを分析したものである。ち
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
イタリアのトリノで4月28日~30日にG7気候・エネルギー・環境大臣会合が開催され、共同声明を採択した。 最近のG7会合は、実現可能性がない1.5℃目標を前提に現実から遊離した議論を展開する傾向が強いが、トリノの大臣会合
-
福井地裁は、5月21日、福井や大阪など22都道府県の189人が関電を相手に運転再開の差し止めを求めた訴訟で、差し止めを命じる判決を言い渡した。報道されているように、「地震の揺れの想定が楽観的で、安全技術や設備は脆弱で、大飯原発の半径250キロメートル以内に住む人の人格権を侵害する具体的な危険がある」というのが判決の骨子である。
-
NHK 6月29日公開。再生可能エネルギー(再エネ)の太陽光発電が増え、買い取り費用が膨らんでいることで、私たちの負担がいま急増しています。
-
東京都が水素燃料電池タクシー600台の導入目標(2030年度)を掲げた。補助金も手当されるという。 燃料電池商用モビリティをはじめとした「水素を使う」アクションを加速させるプロジェクト発表会及びFCタクシー出発式 だがこ
-
影の実力者、仙谷由人氏が要職をつとめた民主党政権。震災後の菅政権迷走の舞台裏を赤裸々に仙谷氏自身が暴露した。福島第一原発事故後の東電処理をめぐる様々な思惑の交錯、脱原発の政治運動化に挑んだ菅元首相らとの党内攻防、大飯原発再稼働の真相など、前政権下での国民不在のエネルギー政策決定のパワーゲームが白日の下にさらされる。
-
各種機関から、電源コストを算定したレポートが発表されている。IRENAとJ.P.Morganの内容をまとめてみた。 1.IRENAのレポート 2022年7月13日、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、「2021年
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間