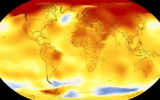COP26の評価と課題②

GraPro/iStock
COP26は成功、しかし将来に火種
COP26については様々な評価がある。スウェーデンの環境活動家グレタ・トウーンベリは「COP26は完全な失敗だ。2週間にわたってこれまでと同様のたわごと(blah blah blah) を繰り返しているだけだ」と酷評している。
COP25においては複数のサイドイベントに登壇し、COPのシンボル的存在であったが、今回はマーク・カーニーCOP26金融顧問主催のイベントでクレジット取引を化石燃料企業と金融企業の「グリーン・ウオッシュ」と罵倒する等、環境原理主義に反資本主義が加わり、過激度がパワーアップした感がある。環境原理主義的な欧州諸国政府も扱いあぐねるような存在に転化したようだ。
しかし1.5℃目標を大きく前面に打ち出し、それに沿った野心引き上げの作業計画策定が盛り込まれたこと、トーンダウンされたとはいえ、石炭火力フェーズダウンが盛り込まれたことでグラスゴー気候協定は「歴史的合意」と大方の環境関係者からは高く評価されている。
筆者はG20でいったん押し込まれながら、COPの場でG20を超える合意を作り上げた英国の外交力に舌を巻くものであるが、パリ協定がまとまったときのような高揚感を感ずることはなかった。むしろグラスゴー気候協定が今後にまいた火種は非常に大きいと感ずるからである。
炭素予算をめぐる先進国・途上国対立の激化
パリ協定は地球全体の温度目標を定めるトップダウンの性格と、各国が国情に応じて目標を設定するボトムアップの性格を併せ持ち、両者が微妙なバランスをとっている枠組みである。ボトムアップのフレキシビリティがあるからこそ、全ての国が参加する枠組みになったのである。
しかし2050年全球カーボンニュートラルを目指すという方針を明確に打ち出すことは、2050年までに排出できるCO2総量に枠をはめることと同義である。その限られた炭素予算をめぐって、今後、先進国、途上国の激しい争奪戦が生ずることは確実だ。
2050年全球カーボンニュートラルとは全ての国が2050年カーボンニュートラルを達成することと同義ではない。事実、インドは先進国が2050年全球カーボンニュートラルを強くプッシュする以上、先進国は2050年よりももっと早いタイミングでカーボンニュートラルを達成し、途上国に「炭素スペース」を与えるべきだ、途上国にカーボンニュートラル目標やNDCの引き上げを要求するならば毎年の支援額を1兆ドルにすべきだと主張している。
2℃目標への道筋ですら大幅に外れている中で、欧米諸国が1.5℃という「大言壮語」を押し通したツケは、今後10年間、カーボンニュートラル目標前倒し、目標引き上げ、途上国支援の大幅上積みを間断なく途上国から要求されるという形で自らに返ってくるだろう。
合意文書ではパリ協定の温度目標に沿った形でNDCを強化し2022年末までに提出することが求められている。米国、EU、日本は「自分たちは2050年カーボンニュートラルを表明し、NDCも強化したのだから、更なる見直しは不要である」と考えている。
しかし中国、インドが新たなNDCを2022年末までに提出するかといえば、その可能性は低い。彼らは「自分たちは2060年、2070年のカーボンニュートラル目標をかかげている。これは今世紀後半のカーボンニュートラルを達成するというパリ協定の規定と整合的である。NDCの評価軸は1.5℃~2℃のパリ協定の温度目標であり、1.5℃決め打ちではない」と主張するに違いない。
来年のCOP27で採択予定の「勝負の10年」における野心引き揚げの作業計画をめぐって先進国と途上国の対立が激化することは間違いないだろう。
そうなると来年のG7議長国であるドイツが「中国、インドの行動を促すため、G7諸国でカーボンニュートラル目標の前倒し、2030年目標の上積みを行うべきだ」と言い出しかねない。
ドイツでは9月の総選挙で議席を伸ばした緑の党が連立政権に参加する。EUの盟主的存在であるドイツがますます環境原理主義に傾くことは日本にとって決して望ましい事態ではない。
エネルギーの現実を無視したCOPの議論
石炭火力についてもフェーズダウンということで今回は決着したが、今後、年限を区切ってフェーズアウトという議論が再燃する、更にその対象が化石燃料全体に話が広がる可能性も十分にある。問題はそうした議論が現実のエネルギー情勢と全く乖離していることだ。
欧州発で日本にも影響が及んできているエネルギー危機の大きな原因は経済回復によるエネルギー需要増に供給が追い付いていないからであり、その背景には石油、ガスの上流投資の停滞がある。
石油、ガス火力の上流投資が停滞している理由は石油価格の低下、コロナ等の要因があるが、過激な化石燃料叩きが広がりを見せる中で、将来の投資に慎重になっている側面も大きい。
COP26では化石燃料セクターへの公的融資の停止に関する有志国宣言に米国、EU諸国が名前を連ねている。これにより上流投資がますます滞れば、エネルギー需給ひっ迫が今後も生ずる可能性が高まる。世界的なガス需要の高まりも石炭を排除する欧州発の環境原理主義の影響が大きい。欧州のエネルギー危機の相当部分は自らの偏った環境原理主義的政策が招いた帰結である。
ところがエネルギー危機に遭遇するや、これまでパイプラインを差し止めにしたり連邦所有地での石油ガス生産を抑制している米国がOPECやロシアに増産を要請したり、風が吹かずに電力不足に陥った英国は古い石炭火力を動かしている等、脱化石燃料という掛け声とは裏腹の動きも生じている。
このことは国民への低廉で安定的なエネルギー供給というエネルギー政策の最も根源的な要請が危うくなれば、温暖化防止を横においてでも現在の国民生活を守らねばならないという当たり前のことを意味している。
先行き不透明な「勝負の10年」
今後、2030年までの道のりは決して平坦ではない。米中対立の行方も不透明だ。COP26では米中共同声明が鳴り物入りでPRされたが、中身はほとんど目新しいものがなく、中国は何も譲歩していない。国内で支持率が低下したバイデン政権が唯一国民から評価されている温暖化分野で成果をあげたいという米側の事情が垣間見える。そこにつけこんで中国はしたたかに米国からの譲歩を得ようとするだろう。
温暖化問題はそれ自体が独立して存在しているのではなく、地政学、地経学的なコンテキストでとらえることが必要だ。中国は間違いなくそういう視点でものを考えている。また米国が2022年の中間選挙、2024年の大統領選挙でどうなるかもわからない。エネルギー需給ひっ迫がいつまで続くのかも不透明だ。
国際連系線もなく、国内石油資源を有さず、再エネ資源にもめぐまれていない日本は欧米諸国に比して大きなハンディキャップを負っている。「勝負の10年」の試練は欧米以上に大きい。
岸田政権は経済安全保障を看板にかかげている。河野、小泉前大臣のような環境・再エネ原理主義者が政権中枢から去った機会を逃さず、国産技術である原発の新設・リプレースをきちんと戦略に位置付けるべきだ。フランスも原発新設を打ち出し、フォンデアライエン委員長も温暖化対策のための原発の重要性を明言している。COP26で打ち出された野心引き上げ圧力は日本の原子力政策の正常化する最後のチャンスになる。
【関連記事】
・COP26の評価と課題①

関連記事
-
パリ協定については未だ明確なシグナルなし トランプ大統領は選挙期間中、「パリ協定のキャンセル」を公約しており、共和党のプラットフォームでも、「オバマ大統領の個人的な約束に過ぎないパリ協定を拒否する」としている。しかし、政
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回は理系マニア向け。 「温室効果って、そもそも存在する
-
新聞は「不偏不党、中立公正」を掲げていたが、原子力報道を見ると、すっかり変わった。朝日、毎日は反対、読売、産経は推進姿勢が固定した。
-
はじめに 原発は高くなったと誤解している人が多い。これまで数千億円と言われていた原発の建設費が3兆円に跳ね上がったからである。 日本では福島事故の再防止対策が膨らみ、新規制基準には特重施設といわれるテロ対策まで設置するよ
-
アメリカでは「グリーン・ニューディール」をきっかけに、地球温暖化が次の大統領選挙の争点に浮上してきた。この問題には民主党が積極的で共和党が消極的だが、1月17日のWSJに掲載された炭素の配当についての経済学者の声明は、党
-
有馬純東京大学公共政策大学院教授の論考です。有馬さんは、経産官僚出身で、地球環境・気候変動問題の首席交渉官でした。日本の現状と技術力という強みを活かした対策の必要性を訴えています。有馬さんが出演する言論アリーナを10月1日午後8時から放送します。
-
きのうの言論アリーナは民進党の高井崇志議員に話を聞いたが、後半はやや専門的な話なので、ちょっと補足しておきたい。核拡散防止条約(NPT)では非核保有国のプルトニウム保有を禁じているが、日本は平和利用に限定することを条件に
-
小泉純一郎元総理(以下、小泉氏)は脱原発に関する発言を続けている。読んでみて驚いた。発言内容はいとも単純で同じことの繰り返しだ。さらに工学者として原子力に向き合ってきた筆者にとって、一見すると正しそうに見えるが、冷静に考えれば間違っていることに気づく内容だ。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間