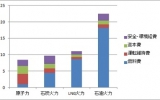今週のアップデート — 適切な放射線防護対策とは?(2012年2月27日)
今週のコラム
1)福島第1原発事故から間もなく1年が経過しようとしています。しかし、放射能をめぐる時間が経過しているのに、社会の不安は消えません。
内科・血液を専門にする医師の王伯銘博士から投稿をいただきました。それを「ある医師からの手紙「放射能と健康についての知識を医師に学んでほしい」—「患者の利益のため」ヒポクラテスの教えに私たちは常に従う」という記事で紹介します。
健康被害に不安を持つ人々の解決策として、医師への相談を呼びかけています。
2)GEPR編集部のフェロー、石井孝明は記事「放射線防護の重要文書「ICRP勧告111」の解説 — 規制の「最適化」「正当化」「住民の関与」が必要」を提供します。日本政府の政策の指針の一つであるICRP勧告111の勧告についての解説です。
この文章は健康被害回避と社会的コストのバランスを保つ「最適化」、住民への負担の同意「正当化」、そして関係する住民の関与が必要と、指摘しています。しかし日本政府の現在までの政策は、いずれの論点でも適切な配慮をしていません。
今週のニュース
1)ニューヨークタイムズは2月10日の記事で、"A Confused Nuclear Clean UP"(混乱する除染)という記事で、日本の除染事業のおかしさを指摘しています。福島県飯館村の現地の報告、そして日本政府の政策の分析です。
効果が疑問視されているのに、費用が1兆円にもなり、ゼネコンばかりが儲かるという事実を述べています。日本のメディアは、なぜか「除染のおかしさ」を報道しません。
2)毎日新聞「帰村か移住か、共同体に亀裂 飯舘」(2月26日記事)
原発事故によって全村避難となった福島県飯館村で、村の意見が、移住か、帰還かに分かれている現状を伝えています。
論文の紹介
ICRP勧告111「原子力事故または放射線緊急事態後における長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」(社団法人日本アイソトープ協会による日本語訳)(原典)
2008年に発表された核災害に際しての放射線防護基準に対する勧告です。

関連記事
-
「万感の書を読み、万里の道を行く」。士大夫の心構えとして、中国の格言にこのような言葉がある。知識を吸収し、実地で確かめることを推奨しているのだろう。私は旅行が趣味だが、この言葉を知って旅をするごとに、その地域や見たものの背景を一層考えるようになった。
-
石野前連合とは、石破ー野田ー前原連合のことである。 ここのところ自由民主党だけでなく、立憲民主党も日本維新の会もなんだか〝溶けはじめて〟いるようである。 いずれの場合も党としての体をなしていない。自民党は裏金問題から解脱
-
米国の保守系シンクタンクであるハートランド研究所が「STOPPING ESG」という特集ページをつくっているので紹介します。同研究所トップページのバナーから誰でも入ることができます。 https://www.heartl
-
気候・エネルギー問題はG7広島サミット共同声明の5分の1のスペースを占めており、サミットの重点課題の一つであったことが明らかである。ウクライナ戦争によってエネルギー安全保障が各国のトッププライオリティとなり、温暖化問題へ
-
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 日本では「ノーベル賞」は、格別に尊い存在と見なされている。毎年、ノーベル賞発表時期になるとマスコミは予想段階から大騒ぎで、日本人が受賞ともなると、さらに大変なお祭り騒ぎになる。
-
「福島の原発事故で放射能以上に恐ろしかったのは避難そのもので、精神的ストレスが健康被害をもたらしている」。カナダ経済紙のフィナンシャルポスト(FP)が、このような主張のコラムを9月22日に掲載した。この記事では、放射能の影響による死者は考えられないが、今後深刻なストレスで数千人の避難住民が健康被害で死亡することへの懸念を示している。
-
サプライヤーへの脱炭素要請は優越的地位の濫用にあたらないか? 企業の脱炭素に向けた取り組みが、自社の企業行動指針に反する可能性があります。2回に分けて述べます。 2050年脱炭素や2030年CO2半減を宣言する日本企業が
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間