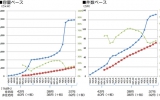今週のアップデート — 東日本大震災1年、エネルギーの未来を考える(2012年3月12日)
今週のコラム
東日本大震災から間もなく1年が経過しようとしています。少しずつ、日本は震災、福島第一原発事故の状況から立ち直っています。
もちろん問題は山積していますが、エネルギー分野では東京電力の処理、また再生可能エネルギーをどのように取り入れるかが課題になっています。
1)エネルギー、環境問題の評論で活躍する竹内純子(たけうち・すみこ)さんに、自宅で太陽光発電を使っている経験から「頭上の太陽光パネルに思う—いじらしさと気まぐれにどのように向き合うべきか」を寄稿いただきました。
人気のある太陽光で、期待はあるものの、その発電量の「気まぐれ」は、笑いながら受け入れられる問題なのか、考えさせられます。
2)一橋大学大学院の橘川武郎(きっかわ・たけお)教授に「東京電力をどうするか—避けられぬ体制変化では「現場力」への配慮を」を寄稿いただきました。東京電力の現場の力を評価した上で、今後の同社、そしてエネルギー体制の有るべき姿について、論点を示しています。
今週のニュース
米国エネルギー庁の調査部門ARPA-Eは「2012年サミット」という国際会議を開き、「21世紀のエネルギー変革」と題して、2011年2月29日、マイクロソフトのビル・ゲイツ会長と、米エネルギー庁長官のスティーブン・チュー氏の対談を行いました。(リンク)ゲイツ氏は、クリーンエネルギー技術の進化が貧困問題を解決すると指摘。米政府の予算拡充を訴えました。一方でチュー長官は、早急な予算の増額は難しいが、米政府も再生可能エネルギーの拡大を意図しており、経済界と協力して成長させたいとしています。
今週のリンク — 生活に役立つエネルギーと放射能情報
震災から1年が経過しており、日本政府の政策を示す公文書、サイトを紹介します。読者の皆様の日常生活で、放射能問題、エネルギー問題を考える材料として使ってください。
1)日本政府・内閣府は昨年11月にまとめた専門家の討議を基に、『「低線量被ばくのリスク管理に基づくワーキンググループ」報告書に基づいた健康への影響とこれからの取り組み』
というパンフレットをまとめました。
内閣府の同ワーキンググループは被曝対策として、「年間20ミリシーベルトの被曝基準」「子供や妊婦への対策を最優先」「地域密着への対話」を打ち出しています。また議論が詳細、かつ分かりやすくまとまっています。
厳格な食品安全基準の設定により農水産業が打撃を受ける、さらには除染コストを検証せず、国民負担が増加しかねないという問題があります。しかし、そうしたことを含めて、政府の対策の現状が分かります。
2)文部科学省は、福島を中心に10分ごとにデータを計測、発表し、時系列で見ることのできる「リアルタイム線量測定システム」を2月から運営しています。自分で放射線量を図る動きがありますが、不正確な測定が行われおかしな情報が拡散されがちです。それよりも不安に思う方は、まずこのシステムによる観察をするべきではないでしょうか。
3)文部科学省は小学校、中学校、高校の「放射線に関する副読本」を公開しています。
一連の副読本では「長期の低線量被曝でも健康被害の可能性は極小である」という、現在の日本に必要な情報についての記述が少ないという問題があります。
それでも、放射線について、分かりやすく、工夫した解説が行われています。それぞれの年代だけではなく、大人にも参考になります。
私たちは放射線を浴びて生活しており、身近にも放射線はあり、工業・医療に利用していることを紹介しています。
4)日本の学会も、放射性物質に関する啓蒙活動を行っています。
日本保健物理学会は専門家による、一般からの細かい質問に答える「暮らしの放射線Q&A」という取り組みを行っています。
中には、「2011年3月11日にマンションで換気してしまった。健康への不安はありますか」など、明らかに過剰な恐怖にとらわれた質問があります。しかし専門家の皆さんは真面目に答え続けています。この活動に深い敬意を持ちます。
誰もが持つ疑問に丁寧に答えているので、必要な方は参照してください。
5)世界の核災害について、日本は広島と長崎の原爆の悲劇ゆえにデータ、研究が蓄積されています。放射線影響研究所では、原爆被爆者の影響について簡単にまとめています。
原爆では遺伝疾患、また100mSv以下の低線量被曝で健康被害は観察されていません。福島・東日本にとって、これはよい情報です。同研究所サイト。
6)1986年のチェルノブイリの核災害について、GEPRはロシア政府報告書、国際原子力機関(IAEA)など8国際機関とウクライナなど3カ国、さらに国連の報告書の要旨を翻訳しています。GEPRの報告書のサイトにあります。
チェルノブイリ近郊では、事故後1991年から被曝限度を年5mSvとして強制移住させるという政策が行われましたが。それによる移住で、社会と経済の混乱が大きかったと指摘しています。
また遺伝疾患、低線量被曝(200mSv)の健康被害は観察されていません。これは福島・東日本にとって、良い情報です。
主に起こったのは事故直後の急性被曝です。その死者は火災のやけど、爆発も含め50人以下です。また放射能に牛乳などが流通したために、子供を中心に甲状腺がんが広がりました。ただし、日本では原発事故後に、福島では同じことが起こっていません。
7)こうした情報を参考に、落ち着いて原発事故、放射能に向き合いましょう。GEPRはリスクコミュニケーションのために、研究員を派遣します。必要ならば、ご連絡ください。
連絡先はこちら。
科学の知見が示すことは、福島・東日本で、「現在の放射線量で健康被害が起こる可能性はほとんどない」ということです。
放射性物質を軽視してはなりませんが、同時に過度に恐れ、それによる社会と個人の負担を広げる必要はありません。今でも過剰に危険を騒ぐ動きがありますが、それは大半が必要のない情報です。
物理学者の寺田寅彦がエッセイで次のように語っています。
「ものをこわがらな過ぎたり、こわがり過ぎたりするのはやさしいが、正当にこわがることはなかなかむつかしいことだと思われた」
「正当にこわがり」ながら、冷静に東日本の大震災と原発事故の復興に、全日本人が取り組みましょう。

関連記事
-
12月16日に行われた総選挙では、自民党が大勝して294議席を獲得した。民主党政権は終わり、そして早急な脱原発を訴えた「日本未来の党」などの支持が伸び悩んだ。原発を拒絶する「シングルイシュー」の政治は国民の支持は得られないことが示された。
-
世界の先進国で、一番再生可能エネルギーを支援している国はどこであろうか。実は日本だ。多くの先行国がすでに取りやめた再エネの全量買い取り制度(Feed in Tariff:FIT)を採用。再エネ発電者に支払われる賦課金(住宅37円、非住宅32円)は現時点で世界最高水準だ。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
東日本大震災からはや1年が経過した。昨年の今頃は首都圏では計画停電が実施され、スーパーの陳列棚からはミネラルウォーターが姿を消していた。その頃のことを思い返すと、現在は、少なくとも首都圏においては随分と落ち着きを取り戻した感がある。とはいえ、まだまだ震災後遺症は続いているようだ。
-
IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は、2030年までに世界の平均気温が産業革命前より1.5℃(現在より0.5℃)上昇すると予測する特別報告書を発表した。こういうデータを見て「世界の環境は悪化する一方だ」という悲観的
-
【要旨】(編集部作成) 放射線の基準は、市民の不安を避けるためにかなり厳格なものとなってきた。国際放射線防護委員会(ICRP)は、どんな被曝でも「合理的に達成可能な限り低い(ALARA:As Low As Reasonably Achievable)」レベルであることを守らなければならないという規制を勧告している。この基準を採用する科学的な根拠はない。福島での調査では住民の精神的ストレスが高まっていた。ALARAに基づく放射線の防護基準は見直されるべきである。
-
時代遅れの政治経済学帝国主義 ラワースのいう「管理された資源」の「分配設計」でも「環境再生計画」でも、歴史的に見ると、学問とは無縁なままに政治的、経済的、思想的、世論的な勢力の強弱に応じてその詳細が決定されてきた。 (前
-
前回書いたように、11月25日に、政府は第7次エネルギー基本計画におけるCO2削減目標を2035年に60%減、2040年に73%減、という案を提示した(2013年比)。 この数字は、いずれも、2050年にCO2をゼロにす
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間