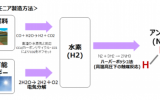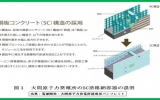今週のアップデート — 持続可能な未来のためのエネルギーの形 (2012年8月20日)
今週のコラム
1)「ポスト福島の原子力」。英国原子力公社の名誉会長のバーバラ・ジャッジ氏から、今年6月に日本原子力産業協会の総会で行った講演について、掲載の許可をいただきました。GEPR編集部はジャッジ氏、ならびに同協会に感謝を申し上げます。
原子力のメリット、デメリットを公平に並べた上で、エネルギーの山積する問題に対して「回答そのものではないが、回答の一部である」という意見を述べています。
福島の事故を受けて海外からを含め、多様な視点から、問題を考えることが必要です。この寄稿は参考になります。
2)アゴラ研究所の池田信夫所長はコラム「エネルギーの本当のコスト」を提供します。
内閣府・国家戦略室が運営する「エネルギー・環境会議」で原発の選択肢の議論が進んでいます。「原発ゼロ」などが示された選択肢では、コストが詳細に検討されていません。そのおかしさを指摘し、客観的なコスト分析の必要を訴えています。
3)今年6月に行われた国連のサミット「リオ+20」についての報告を、NPO国際環境経済研究所の記事から転載します。
「国連サミット「リオ+20」参加報告−(上)合意文書の解説」
「国連サミット「リオ+20」参加報告−(下)企業と産業界にとっての今後の課題」
今後は経済活動、エネルギーの分野で「持続可能性」が欧米の多国籍企業を中心に強調される可能性があります。
今週のリンク
1) 原発事故以来、現時点でも約16万人の福島原発周辺地域の方が、政府が警戒区域を設定したままであるため、故郷に戻れません。
昨秋に帰還基準を20mSvと内閣府の関係会議が定めました。しかしそれに加えて福島県、自治体の要望で、その基準をさらに引き下げ、除染をすることを求める意見が出ました。今、各自治体が除染作業を行っています。
しかし除染にはコストがかかります。また年20mSvの放射線を被曝しても、健康被害の可能性はかなり少ないと推定されます。正確な情報を提供して住民の意向を集め、政治決断を促すことが必要です。しかし政府の動きはとても遅いです。
ようやく一部地域で住民の意向調査が始まりました。「避難区域の住民へ意向調査開始」(NHK)
しかし福島県などは環境省の打ち出した森林除染を全体で行わないという案に、反対を表明しています。「県、環境省に方針転換求める 森林全体除染「不要」方針案で」(福島民報)。
コスト、そして健康被害の可能性の少なさを考え、早急に決断を政治が示すことが求められます。
2) 国家戦略室の「エネルギー・環境会議」が2030年のエネルギー供給体制について、意見募集を8月12日に閉め切りました。(特設ホームページ)
この案は2030年における原発の発電比率に占める割合を「ゼロ」「15%」「20〜25%」の3案を提示して、国民の意見を集めました。
パブリックコメントでは約8万通が寄せられました。その大半が原発ゼロを求めるものでした。国家戦略室「国民的議論の中でいただいた御意見等」
一方で産業界はこぞって反対しています。
日本経団連は「エネルギー・環境政策の選択肢等に関するアンケート結果」で「原発ゼロ」シナリオでは33団体中76%が生産減の影響があると予想をしたことを示しました。
電力会社でつくる電気事業連合会は「「エネルギー・環境に関する選択肢」に対する意見」を公表しています。
「いずれの選択肢も、国民負担や経済への影響、実現可能性等の点から問題が極めて大き く、選択肢たり得ない。算定根拠やデータの開示も不十分。拙速な議論は避け、選択肢 の在り方そのものについて再考すべき」としています。
アゴラ研究所も以下の論文を掲載しています。
間違った情報で日本のエネルギーの未来を決めるのか?=「エネルギー・環境会議」選択肢への疑問 ― 誤った推定、経済的悪影響への懸念など試算は問題だらけ
現実的な「原子力ゼロ」シナリオの検討 ― 石炭・LNGシフトへの困難な道のり
感情論はやめて、科学的データと客観的統計で議論しなければなりません。そして、原発をゼロにするという単純な議論ではなく、経済性、環境、安全保障の面にも配慮をしなければなりません。
エネルギーは、私たちの生活と経済に密接に結びつきます。
今週の論文
1) RITE(地球環境産業技術研究機構)は「エネルギー・環境会議選択肢に替わる選択肢の提案」で、2030年で、経済成長に伴う最適なエネルギー比率の予想を試算しました。
そこでは、発電における原発の割合をゼロから25%まで6つの選択肢を提示。25%の場合には、火力(化石)53%、再生可能エネルギー22%とすることが、一番現実的な目標として推奨しています。
この場合には政府目標の経済成長は確保される一方で、電力料金の上昇も、再エネを最大限導入しても、キロワットアワー当たり最大2円程度の上昇で抑えられるとしています。

関連記事
-
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで3回にわたって、筆者は日本の水素政策を散々にこき下ろしてきたが、日本政府はまだ全然懲りていないようだ。 「水素に賭ける日本、エネルギー市場に革命も」と言う驚くべき記事が
-
東日本大震災、福島原発事故で、困難に直面している方への心からのお見舞い、また現地で復旧活動にかかわる方々への敬意と感謝を申し上げたい。
-
米国のバイデン大統領は去る2月7日に、上下両院合同会議で2023年の一般教書演説(State of the Union Address)を行った。この演説は、年初にあたり米国の現状について大統領自身の見解を述べ、主要な政
-
茨城大学理学部の高妻孝光教授は、福島第1原発事故以来、放射線量の測定を各地で行い、市民への講演活動を行っています。その回数は110回。その取り組みに、GEPRは深い敬意を抱きます
-
日本経済新聞は、このところ毎日のように水素やアンモニアが「夢の燃料」だという記事を掲載している。宇宙にもっとも多く存在し、発熱効率は炭素より高く、燃えてもCO2を出さない。そんな夢のようなエネルギーが、なぜ今まで発見され
-
ドイツで高騰しているのはガスだけではなく、電気もどんどん新記録を更新中だ。 2020年、ドイツの卸電力価格の平均値は、1MW時が30.47ユーロで、前年比で7ユーロも下がっていた。ただ、これは、コロナによる電力需要の急落
-
NRCは同時多発テロの8年後に航空機落下対策を決めた 米国は2001年9月11日の同時多発テロ直後、米国電力研究所(EPRI)がコンピュータを使って解析し、航空機が突入しても安全は確保されると評価した。これで仮に、同時多
-
拝啓 グーグル日本法人代表 奥山真司様 当サイトの次の記事「地球温暖化って何?」は、1月13日にグーグルから広告を配信停止されました。その理由として「信頼性がなく有害な文言」が含まれると書かれています。 その意味をグーグ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間