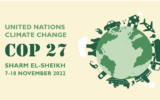シンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」出席者紹介
アゴラ研究所の行うシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」 の出席者を紹介します。この内容は、ニコニコ生放送、BLOGOSで生放送します。
第一部 原発はいつ動くのか(2時間)11月26日 21:30〜23:30
原発はいつ再稼働するのか、その前提となる規制改革や電力自由化はどうするのか、16万人の避難者をどう帰宅させるのか、除染はどこまで必要なのか、など当面の課題を考えます。

片山さつき
自民党参議院議員
東京大学法学部卒。1982年大蔵省(現・財務省)に入省後、フランス国立行政学院に留学。主計局主計官などを経て2005年衆議院議員に就任。10年参議院議員。エネルギー問題には05年に就任した経産大臣政務官としてかかわる。自民党の論客、政策立案の中心の一人として知られる。(ホームページ)

田原総一朗
ジャーナリスト
早稲田大学文学部卒。岩波映画製作所、テレビ東京を経て、77年からフリージャーナリスト。活字と放送の両メディアにわたり精力的な活動を続けている。テレビ朝日系で1987年より『朝まで生テレビ』に出演。02年に早稲田大学で「大隈塾」を開講、05年から早稲田大学特命教授と未来のリーダー育成、教育にもかかわる。『塀の上を走れ 田原総一朗自伝』(講談社)など著書多数。原子力問題、エネルギー問題にも30年以上取り組む。(ホームページ)

石川和男
東京財団上席研究員 社会保障経済研究所代表 政策家
東京大学工学部卒業。1982年通商産業省(現・経済産業省)入省。2007年同省退官。内閣官房などに勤務した後、内閣府・行政刷新会議などの委員を歴任。09年東京財団上席研究員に就任。11年9月社会保障経済研究所を設立し代表に就任。NPO、消費者、社会保障制度に詳しく、経産省時代はエネルギー政策の企画、新エネルギー振興策にかかわった。(ホームページ)

水野義之
京都女子大学・現代社会学部教授(核物理学、社会情報学・情報教育)
京都大学理学部卒、東北大学大学院理学研究科博士課程修了。フランス・原子力研究所、西ドイツ・MPI原子核研究所、欧州素粒子物理研究所CERN、大阪大学核物理研究センターなどを経て現職。福島の原発事故では、市民への情報提供、住民による放射能防護活動「エートスプロジェクト」の支援を行う。(ブログ)
第2部 「原発ゼロ」は可能なのか(2時間) 11月27日 21:00〜23:00
民主党の「原発ゼロ政策」は実現可能なのか、核燃料サイクルをどうするのか、核廃棄物の最終処分は可能なのか、など中長期のエネルギー政策を考えます。

植田和弘
京都大学大学院教授
京都大学工学部卒、大阪大学大学院工学研究科修了。京都大学経済学博士、大阪大学工学博士。環境経済学、財政学を専攻。京都大学大学院経済学研究科教授、同大学地球環境大学院教授を兼任。12年に開催され再生可能エネルギーの固定価格買取制度の概要を決めて、その拡充にはずみをつけた政府の「調達価格等算定委員会」の委員長を務めた。日本の原子力・エネルギー政策には、原発事故前から疑問を示していた。『国民のためのエネルギー原論』(日本経済新聞出版社)など著書多数。(研究室ホームページ)

鈴木達治郎
原子力委員会委員長代理
東京大学工学部原子力工学科卒。米国マサチューセッツ工科大学(MIT)修士、東京大学工学博士。電力中央研究所経済研究所研究参事などを経て現職。原子力政策の立案にかかわる。

山名元
京都大学原子炉研究所教授
東北大学大学院工学研究科博士課程修了。東北大学工学博士。旧動力炉・核燃料サイクル事業団(現・日本原子力開発機構)主任研究員などを経て現職。核燃料サイクルの実務、研究の双方にかかわる。著書に「間違いだらけの原子力・再処理問題」(WAC)など。(研究室ホームページ)

澤昭裕
NPO法人国際環境経済研究所経済研究所所長 21世紀政策研究所研究主幹
一橋大学経済学部卒。通商産業省(現・経済産業省)入省。プリンストン大学行政学修士。資源エネルギー庁資源燃料部政策課長、環境政策課長、東京大学先端科学技術研究センター教授を経て現職。環境・エネルギー問題について、発言と提言を続ける。『精神論ぬきの電力入門』新潮新書(2012年)など著書多数。(IEEIホームページ)

司会
池田信夫
アゴラ研究所所長
東京大学経済学部を卒業後、NHK入社。93年に退職後、国際大学GLOCOM教授、経済産業研究所上席研究員などを経て、現在は株式会社アゴラ研究所所長。慶應義塾大学学術博士。著書に『原発「危険神話」の崩壊』(PHP)など多数。池田信夫blog のほか、言論プラットホーム「アゴラ」
エネルギー問題のバーチャルシンクタンク「グローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)」を主宰。

関連記事
-
「万感の書を読み、万里の道を行く」。士大夫の心構えとして、中国の格言にこのような言葉がある。知識を吸収し、実地で確かめることを推奨しているのだろう。私は旅行が趣味だが、この言葉を知って旅をするごとに、その地域や見たものの背景を一層考えるようになった。
-
電力自由化は、送電・配電のネットワークを共通インフラとして第三者に開放し、発電・小売部門への新規参入を促す、という形態が一般的な進め方だ。電気の発電・小売事業を行うには、送配電ネットワークの利用が不可欠であるので、規制者は、送配電ネットワークを保有する事業者に「全ての事業者に同条件で送配電ネットワーク利用を可能とすること」を義務付けるとともに、これが貫徹するよう規制を運用することとなる。これがいわゆる発送電分離である。一口に発送電分離と言ってもいくつかの形態があるが、経産省の電力システム改革専門委員会では、以下の4類型に大別している。
-
ニューヨークタイムズとシエナ大学による世論調査(7月5日から7日に実施)で、「いま米国が直面している最も重要な問題は?」との問いに、気候変動と答えたのは僅か1%だった。 上位は経済(20%)、インフレ(15%)、政治の分
-
今年も冷え込むようになってきた。 けれども昔に比べると、冬はすっかり過ごしやすくなっている。都市熱のおかげだ。 下図は、東京での年最低気温の変化である。青の実線は長期的傾向、 青の破線は数十年に1回の頻度で発生する極低温
-
11月6日(日)~同年11月18日(金)まで、エジプトのシャルム・エル・シェイクにて国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)が開催される。 参加国、参加主体は、それぞれの思惑の中で準備を進めているようだが、こ
-
トランプ前大統領とハリス副大統領の討論会が9月10日に開催される。大統領選に向けた支持率調査によると、民主党の大統領候補であるハリス副大統領が42%、共和党候補のトランプ前大統領が37%で、ハリス氏がリードを広げていると
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
私は友人と設計事務所を経営しつつ、山形にある東北芸術工科大学で建築を教えている。自然豊かな山形の地だからできることは何かを考え始め、自然の力を利用し、環境に負荷をかけないカーボンニュートラルハウスの研究に行き着いた。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間